水産庁公式ブログ「アワビのステーキ食べてみたいよね」2022年6月

|6月29日|6月24日|6月17日|6月10日|6月3日|6月1日|




【6月29日佃煮の日2022~全力佃煮~】
水産庁職員は仮の姿、佃煮エージェントKがお送りする「佃煮の世界」!
皆さんお待ちかねのこの日がやってきました!
今日6月29日は佃煮の日!
佃煮発祥の地、「佃島」の守り神である住吉神社が建立されたのが、正保2年(1646年)6月29日。
「29」と「佃煮」をかけて、「佃煮の日」となりました。
記念すべき佃煮の日2022にお送りするのは「全力佃煮」!
佃煮エージェントKが佃煮を全力で食べる動画です。
これを見ればあなたも佃煮を食べたくなること間違いなし!
いかがでしたでしょうか。
今日はみんなで佃煮を食べましょう!!
〇昨年の佃煮の日企画「琥珀の魔法」はこちらから→https://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/blog/202106.html#a6
【6月24日隠岐水産高校(島根県)が漁業取締船「白嶺丸」を見学!】
6月20日、島根県の隠岐の島町にて、漁業取締船「白嶺丸(はくれいまる)」の見学会を開催しました。
漁業取締船「白嶺丸(はくれいまる)」
地元の隠岐水産高校の1年生27名、3年生20名、先生方6名が参加し、船内の見学、乗組員制服・取締装具の試着、水産庁の活動内容等の説明を通じて、
水産庁漁業取締船の魅力をたっぷりと味わってもらいました!
見学会の様子を、写真で振り返っていきたいと思います。
学生の整列と点呼がビシッときまっています。
先生に何度かやり直しをかけられますが、その声に取締船乗組員のほうがビクッとしてしまいます。。。
返事や挨拶の声が大きく、立派です!
制服や取締装具の試着は取り合いでした。
みなさん、積極的です。
目を輝かせて機器にふれる学生たち。
説明するたびに、驚いたり、感心したり、喜んだりしてくれるので、説明する側もやりがいがあります。
質問が多く出され、時間が足りないほどでした。
記念撮影!
名残惜しそうに白嶺丸と別れる学生たち。
礼儀正しく、明朗快活な良い子ばかりでした。
次は乗組員として再会できるかも!?
参加した学生や先生から、見学後に以下のコメントをいただきました!
「島まで来ていただき、このような機会をくださったことに大変感謝しています。」
「学生は生き生きと楽しそうに見学会に臨んでいました。」
「今後の進路選定に大いに参考になりました。」
「船内の雰囲気がとても良い。チームワークが素晴らしい。面白い人が多い。」
「白嶺丸」船長及び乗組員の皆様、休憩時間を返上して準備していただき、大変お疲れ様でした。
【6月17日漁業取締船・照洋丸】
ドック(船の定期健康診断)を終えた水産庁の漁業取締船「照洋丸」が晴海埠頭に帰港しているということで、取材をしてきました!
照洋丸は元々漁業調査船として造られ、平成27年に取締船として使用されるようになりました。
水産資源と漁業操業秩序を守るため、24時間体制で取締りに臨んでいます。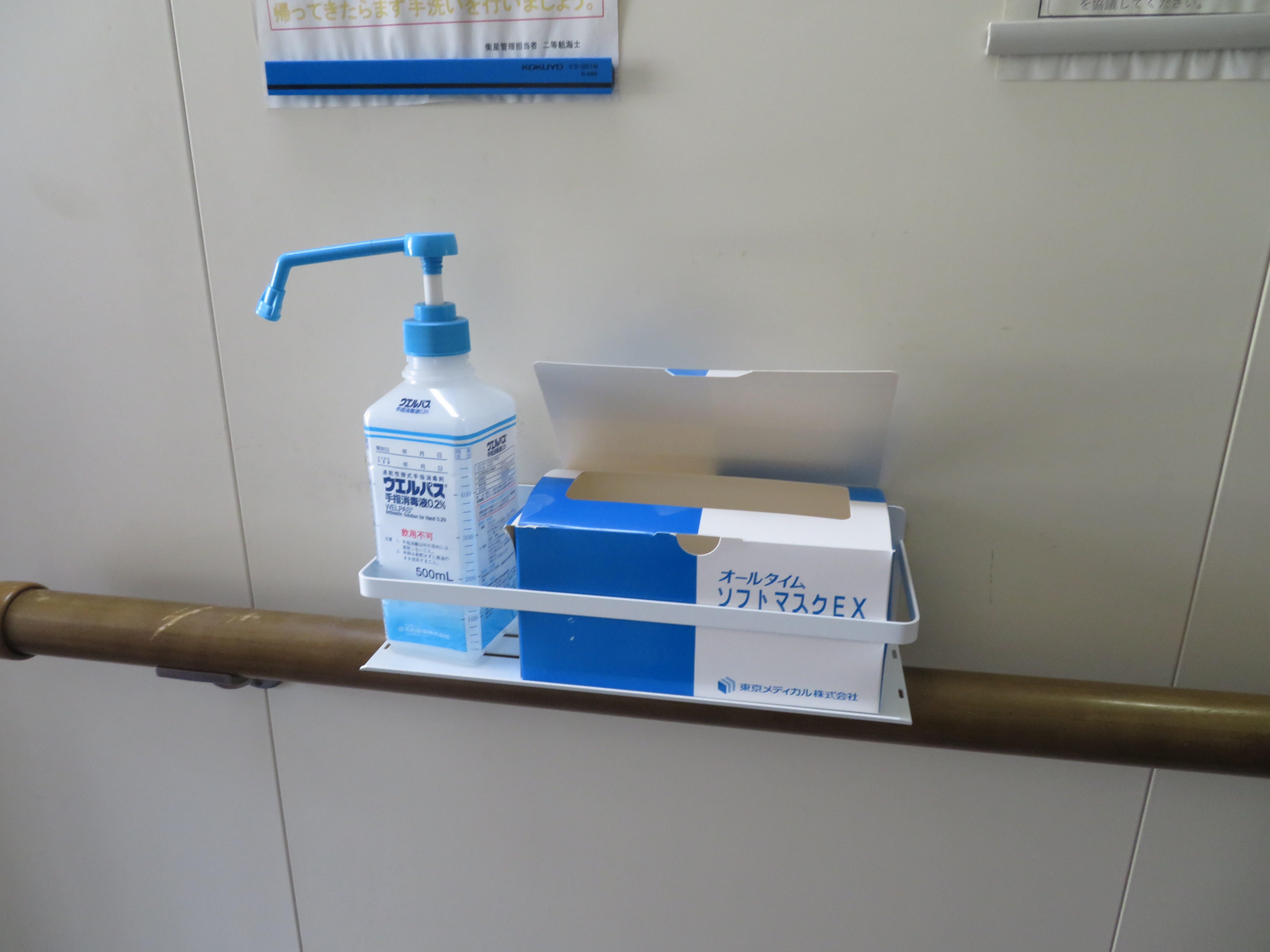
乗船するとアルコール消毒とマスク。感染対策に抜かりはありません。
さっそく、船長、一等航海士のお二人にお話を伺っていきましょう!
Q.他の取締船と異なるところはありますか?
A.水産庁の取締船間では特に違いはありません。漁業関係法令に沿って、取締りを行っています。
ブリッジの様子。ここで操船や監視を行います。
Q.取締船ならではだと思うことはありますか?
A.取締船は24時間運航しており、いつ事件が起きるかわかりません。
そのため、いつでも対応できるように準備はしています。事案発生時には乗組員全員で対応します。
食堂にも「立ち入り検査中」を示す「立検中」の電灯がありました。船内周知のため、立ち入り検査中は電灯が光ります。
Q.船内生活はどのような感じですか?
A.当然ですが、運航中は気が休まりません。体を休められるときを見つけて、1時間だけでも休むようにしています。また、運動不足になりがちなので筋トレを日課にしている乗組員もいるようです。
個人部屋の様子。
「乗船中は常に緊張感を持っている」ということを幾度となくお話しされていたお二人ですが、食堂を案内してくださったときは「すごく美味しいんです。」と笑顔で語ってくださいました。
広々とした食堂。感染対策のため、間にシートを張っています。
ところで、照洋丸は「ドック」を終えて晴海埠頭に寄港していたのですが、「ドック」とは何なのでしょうか?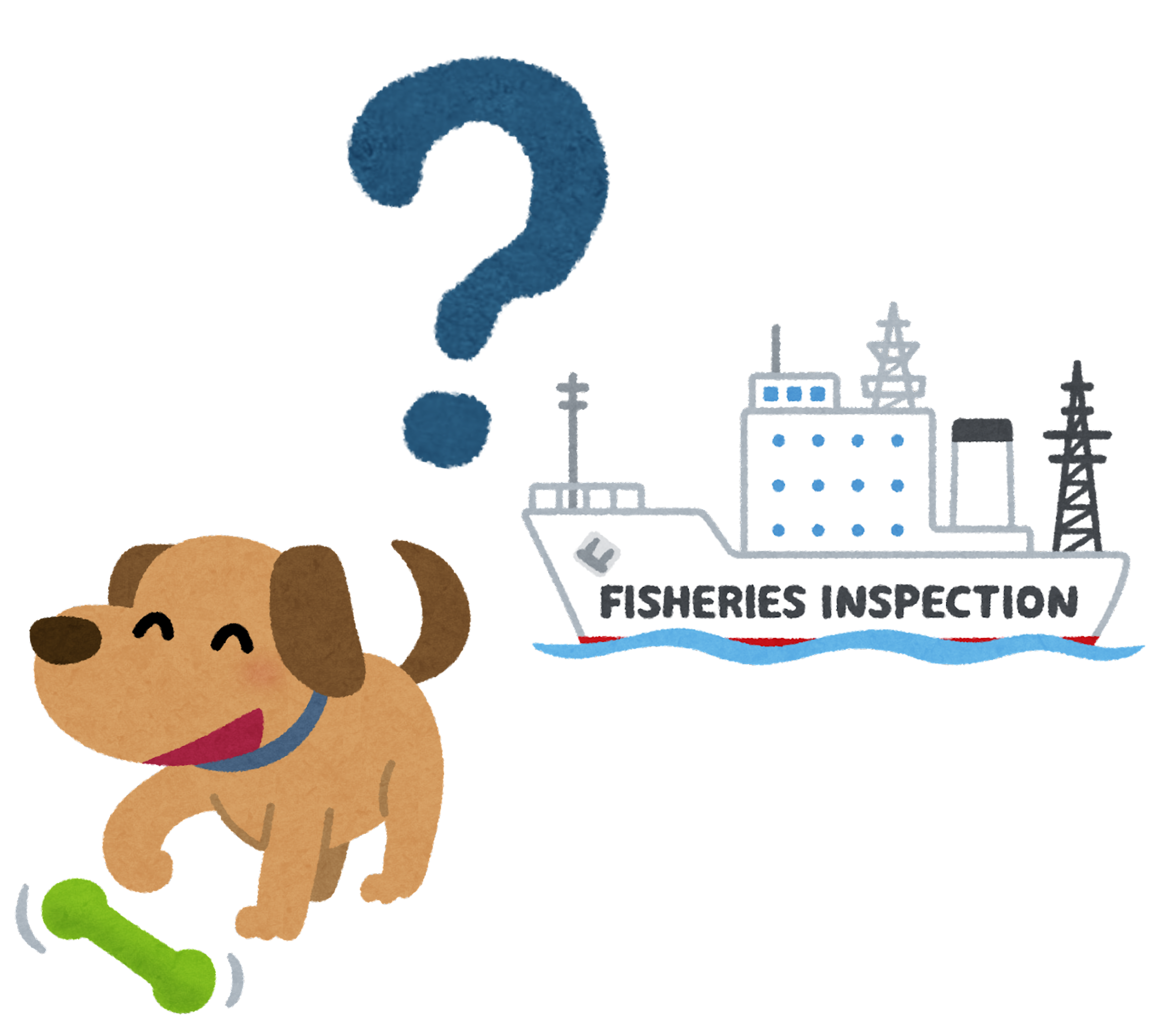
簡単に言うと「船の健康診断」。
船舶安全法により、1年に1回行う「中間検査」と、5年に1回行う「定期検査」が定められています。
今年は5年に1回の定期検査を行う年でした。
検査は造船所で行われます。
ドックと呼ばれる、船の建造、修理や整備を行うための施設に入り、海水を抜くことで船底まで検査を行うことができます。
水を抜いた後のドック。
普段は見ることのできない船底が現れました!!
船体に傷が無いか等も含め、検査を行います。
船体を磨いたり、付着物(フジツボなど)をとったり・・・。写真で見ると、改めて船の大きさを感じられます。
安全に航行ができるよう、造船所の方々と船の乗組員によって、約40日間をかけてエンジンや発電機等、細部まで検査、整備が行われました。
しっかりと定期検査を行い、船も準備万端。
漁業者の皆様の安全のために、これからも日夜取締業務に従事していきます。
~番外編~
これ、何のレバーかご存知ですか?
答えは船の電灯スイッチ、レバーをひねってスイッチをいれます。
船が大きく揺れた際に誤って触れても大丈夫なように工夫されています。
晴海埠頭のゲートがかわいかったです。
照洋丸の皆さん、お忙しいところ取材にご協力いただき、ありがとうございました!
【6月10日フノリ~多方面で大活躍!~】
だいぶ暖かくなり、「暑い!」という日も増えてきましたね。
そんな時に食べたくなるのが、冷たい麺類!
新潟県の郷土料理である「へぎそば」は、海藻「フノリ」をつなぎに使っているため、コシが強く、ツルツルとした滑らかなのどごしを楽しめます。
へぎそば。口に入れると磯の香りがする気がします。
ところで、「フノリ」って何のことか、ご存知ですか?
↑これがフノリです。
漢字で書くと、「布海苔」。
海藻の一種で、全国に分布しています。
古くから、食用としてはもちろん、織物の糊付けの材料や、天然の文化財修復材料等、様々な用途で使用されてきました。
「フノラン」という水溶性食物繊維の名前は聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
フノランを主成分とするフノリは、お味噌汁の具や海藻サラダとして食べられているそうです。
機会があれば、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか?
ちなみに、へぎそばの「へぎ」は、剥ぎ板で作った四角い器のことで、「剥ぐ=はぐ=へぐ」のなまりだそうです。
文化財修復材としての「フノリ」について、特集記事はこちら↓
https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2203/pdf/aff2203-u1.pdf
(農林水産省webマガジン「aff」3月号)
【6月3日漂着した海藻が豚肉に変身!?~鎌倉海藻ポーク~】
みなさんこんにちは。鎌倉市より水産庁に出向しているWです。
今回は出向元である神奈川県鎌倉市における取り組み「鎌倉海藻ポーク」についてご紹介したいと思います。
鎌倉の海岸にはたくさんの海藻が流れ着きます。
通常であれば廃棄処分されるこの海藻を何かの役に立てられないか、そう考えた市内に住む料理家と鎌倉市内に事業所をもつ畜産事業者が中心となり、漂着した海藻を回収→飼料化して、ブランド豚を育てる事業を始めました。
その結果生まれたのがうま味成分を多く含んだ「鎌倉海藻ポーク」です。

この鎌倉海藻ポークができるまでには多くの人が関わっています。
まず、海藻の回収は鎌倉漁業協同組合に所属する漁師さん協力のもと行われています。
秋頃回収された海藻には、種を持った海藻「母藻(ぼそう)」が混じっていることがあるので、漁師さんは魚の産卵や生育する場として貴重な藻場が消失する「磯焼け」を防ぐため、母藻を海に戻します。こうした作業を行うことで、海の環境を守っています。
また、海藻の回収→干す→砕く→粉末にするまでの一連の作業は福祉施設の皆さんがお仕事として取り組まれており、水福連携といった地域共生の一面があります。
農福・水福連携とは・・・障害者や高齢者などが農業・畜産業・水産業分野で活躍することを通じて、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取り組みのこと。
廃棄処分されていた海藻を豚の飼料として生かし、水産業と畜産業さらに福祉事業を連携させブランド豚を生みだしたこのような取り組みが全国に広がるといいですね。

鎌倉海藻ポークは鎌倉市内のレストランで提供されています。私も食べたことがありますが、とてもおいしかったです。
ご興味のある方は鎌倉に行かれた際、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。
【6月1日漁業取締船白嶺丸の船内視察会が開催されました!】
令和4年5月24日、雲一つない快晴の中、白い船体が映える漁業取締船「白嶺丸」に、島根県立浜田水産高校の3年生が船内視察に訪れました。
漁業取締船「白嶺丸」は水産庁が所有する船舶で、乗組員は全員国家公務員です。
「白嶺丸」以外にも水産庁は8隻の取締船を所有しており、いずれも、漁業取締りのスペシャリストとして、水産庁による取締りの要として、活躍しています。
こういった水産庁取締船の魅力を紹介するとともに、将来、水産庁取締船の乗組員になって欲しいとの願いから今回の船内視察会が催されました。
視察会では船橋や機関室の見学、乗組員制服の試着、取締機器の説明や操作体験、船内で提供される食事(種類も豊富で美味しそう)の紹介、年齢の近い新人乗組員との意見交換等が行われました。
船橋説明
機関室見学
船内で提供される食事
生徒の皆さんは一生懸命に話を聞いていただけでなく、貴重かつ刺激的な体験であったろうことが写真からも伺えます。
なお、「白嶺丸」は直前まで取締活動を行っており、この日のため、乗組員は業務の合間に創意工夫を凝らし、互いに協力しながら、視察会の準備をしました。
こういった創意工夫、協力体制の構築は漁業取締りの現場において、非常に役立ちます。このことを生徒の皆さんに、直接お伝えすることは出来ませんでしたので、ここでお伝えします。
視察会の最後には、3年生代表生徒よりお礼の言葉があり、乗組員一同身の引き締まる思いだったようです。
また、引率の先生からは、「3年生はこれから進路を検討するため、一番に良いタイミングであった。優秀な学生を水産庁に薦めたい。」とのお言葉を頂きました。
船長はじめ、乗組員の方々、お疲れ様でした。
お問合せ先
漁政部漁政課広報班
代表:03-3502-8111(内線6505)
ダイヤルイン:03-3502-7987




