(3)安心して暮らせる安全な漁村づくり





ア 漁港・漁村における防災対策の強化、減災対策や老朽化対策の推進
〈防災・減災、国土強靱(きょうじん)化のための対策を推進〉
海に面しつつ背後に崖や山が迫る狭隘(きょうあい)な土地に形成された漁村は、地震や津波、台風等の自然災害に対して脆弱な面を有しており、人口減少や高齢化に伴って、災害時の避難・救助体制にも課題を抱えています。
南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模地震・津波や激甚化・頻発化する自然災害による甚大な被害に備えて、引き続き、漁港・漁村における事前の防災・減災対策や災害発生後の円滑な初動対応等を推進していく必要があります。このため、国は、東日本大震災の被害状況等を踏まえ、防波堤と防潮堤による多重防護、粘り強い構造を持った防波堤や漁港から高台への避難路の整備等を推進しています。
また、水産庁が所管する漁港施設、漁場の施設や漁業集落環境施設等のインフラは、昭和50年代前後に整備されたものが多く、老朽化が進行して修繕・更新すべき時期を迎えています。我が国の財政状況が厳しさを増す中、中長期的な視点から戦略的な維持管理・更新に取り組むため、予防保全型の老朽化対策等に転換し、ライフサイクルコストの縮減及び財政負担の平準化を実現していくことが必要となっています。このため、水産庁は「水産庁インフラ長寿命化計画*1」を策定し、インフラの長寿命化を着実に推進するための中長期的な方向性や具体的な取組を示すとともに、水産庁所管インフラの今後30年間の維持管理・更新費の将来推計を公表しています(図表5-5)。
加えて、令和2(2020)年12月に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」に基づき、甚大な被害が予測される地域等の漁港施設の耐震化・耐津波化・耐浪化等の対策や漁港施設の長寿命化対策、海岸保全施設の津波・高潮対策等を推進しています。
また、気候変動に伴い頻発化・激甚化する自然災害への対応が求められています。このため、令和4(2022)年3月に閣議決定された新たな漁港漁場整備長期計画においては、海洋環境の変化や災害リスクへの対応力強化による持続可能な漁業生産の確保を重点課題として位置付けているところであり、引き続き波浪・高潮に対する防波堤等の性能を向上させていくこととしています。
- 平成26(2014)年8月策定。令和3(2021)年3月31日改定。
図表5-5 30年間の維持管理・更新費の見通し
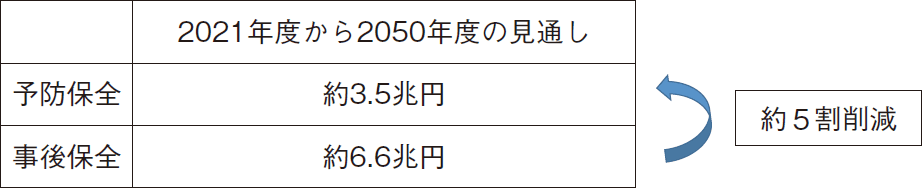

コラム海底火山福徳岡ノ場(ふくとくおかのば)の噴火に伴う軽石等の漂流・漂着について
令和3(2021)年8月13日から15日にかけて福徳岡ノ場(硫黄島から南約50 kmにある小笠原諸島の海底火山)の海底噴火が確認され、この噴火による噴出物により直径約1kmの新島が形成されたほか、火山周辺の海面に多量の軽石等の浮遊物が発生しました。
この多量の軽石等が海流等によって西へ移動し、同年10月上旬以降、沖縄や奄美群島等に次々と押し寄せ、漁港に漂着したり、漁船のエンジントラブルが発生したりするとともに、沖合に漂流する軽石のため沖縄県や鹿児島県では多くの漁業者が操業を自粛するなど、漁業への影響が生じました。さらには、今後の漁場環境への影響を懸念する声も出ています。
そして、同年11月下旬からは伊豆諸島等でも軽石等の漂流・漂着が確認され、関東をはじめとする本州太平洋側の地域では、軽石の漁港への流入防止を図るため、多くの漁港管理者によりオイルフェンスの設置や準備が行われました。
〈軽石の回収〉
沖縄県、鹿児島県等に漂流・漂着した軽石は、漁港における航路や泊地に漂着し、船舶の航行及び係留に重大な支障を及ぼしていることから、緊急的に漁港管理者等が災害復旧事業等を活用し、軽石の回収、運搬及び処分を行っています。また、軽石は海岸にも漂着し、漁港管理者だけでなく地元の漁業関係者やボランティアの方々も参加し、地域一丸となって回収作業が行われています。
〈関係省庁の連携による軽石回収技術の検討〉
軽石の漂着は港湾でも確認され、離島航路等、人流、物流への支障も生じました。また、このような大規模な漂流軽石の回収は前例がないことから、国土交通省港湾局と水産庁が連携し、関係団体や研究機関の協力を得つつ、令和3(2021)年11月5日より「漂流軽石回収技術検討ワーキンググループ」を開催しました。
本ワーキンググループでは、回収実積や回収技術の実証結果、研究機関や関係団体による検討等によって得られた知見や留意点の整理・検討を行いました。その結果を踏まえ、漁港管理者や港湾管理者が現場に応じた回収方法を検討する際の一助とすることを期待し、同月30日に「漂流軽石の回収技術に関する取りまとめ」を公表し、周知しました。
〈処分や利活用〉
軽石の回収作業が進む中、今後、回収した軽石をどのように処分するのかについて課題となっています。処分する場合、成分分析等を行って安全性を確認することが必要であり、また、処分場の不足も問題となっています。このため、これら軽石の利活用方法が検討されているところです。
農業分野においては、軽石を土壌の通気性や透水性を改善するための土壌改良資材として活用している事例がありますが、沖縄県が令和3(2021)年11月に公表した調査結果によると、今般の軽石は塩類濃度が高く、農地へ投入する場合には生育障害の懸念があることから、推奨しないこととしています。
また、建設資材に活用する場合には、一般的に用地の埋立材や用地の舗装等の路盤材、護岸の裏込め材等としての利用が考えられますが、沖縄県は、強度や耐久性などのデータ収集に期間を要することから、まずは強度や耐久性を要しない小規模・簡易的な利活用について、個々に検討していくこととしています。
イ 漁村における生活基盤の整備
〈集落道や漁業集落排水の整備等を推進〉
狭い土地に家屋が密集している漁村では、自動車が通れないような狭い道路もあり、下水道普及率も低く、生活基盤の整備が立ち後れています。生活環境の改善は、若者や女性の地域への定着を図る上でも重要であり、国は、集落道や漁業集落排水の整備等を推進しています。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
FAX番号:03-3501-5097







