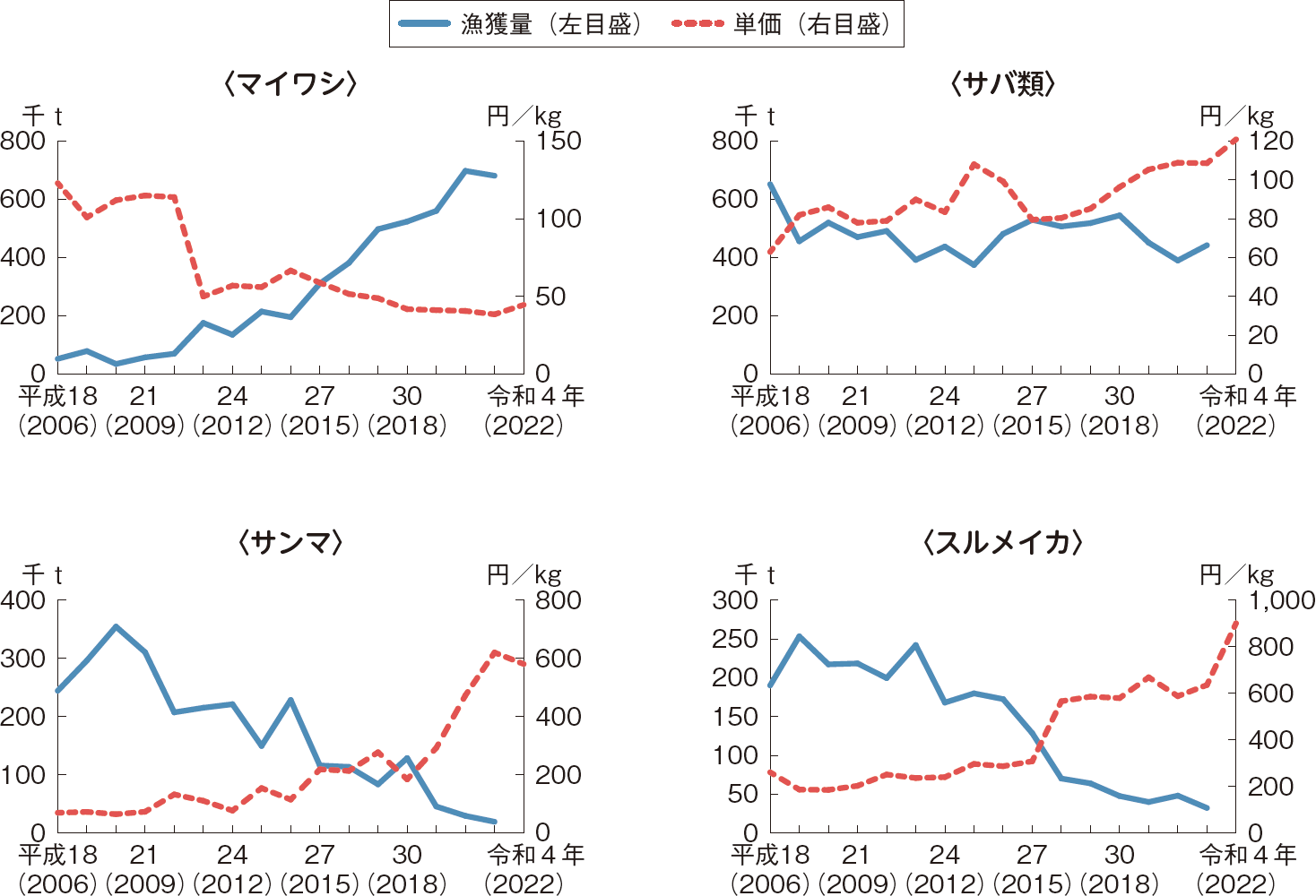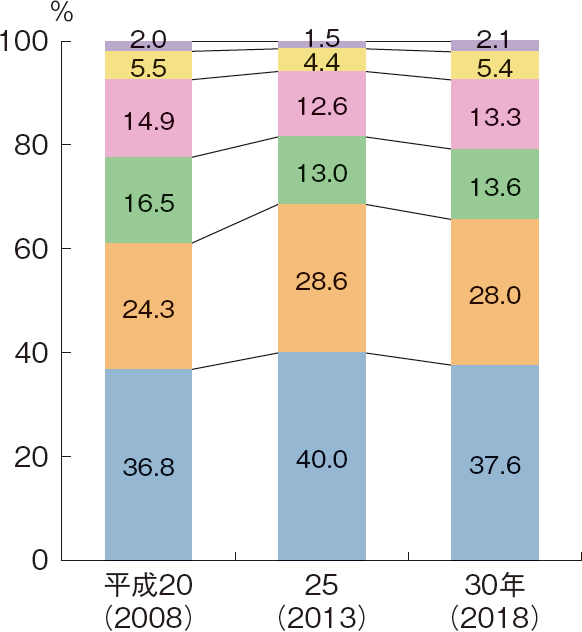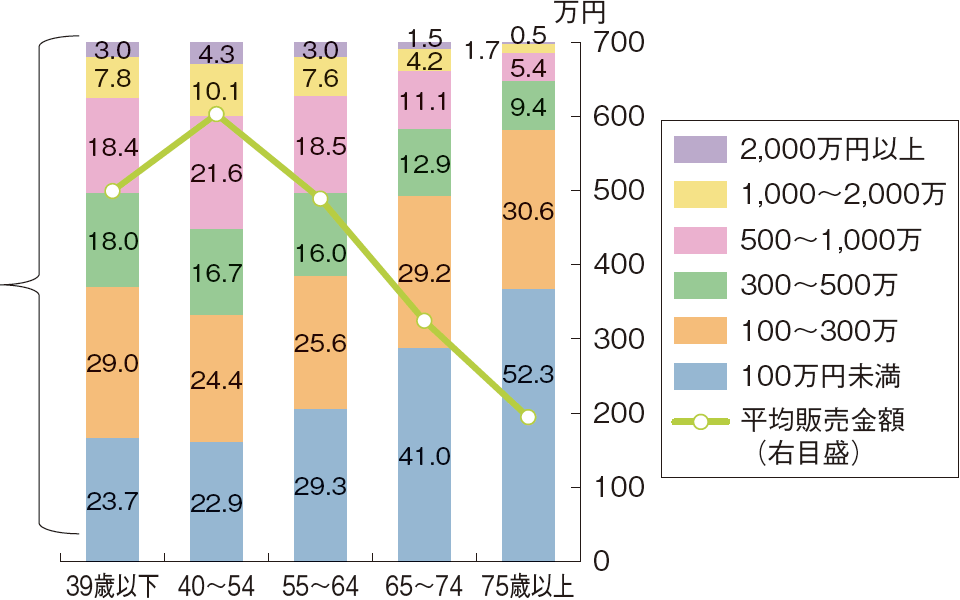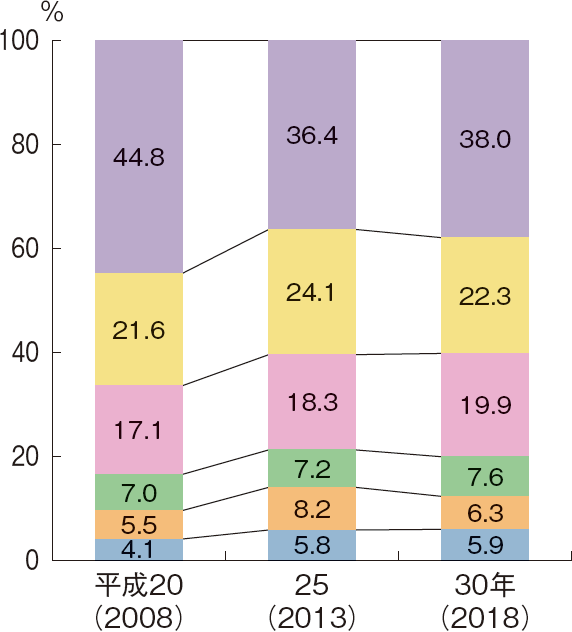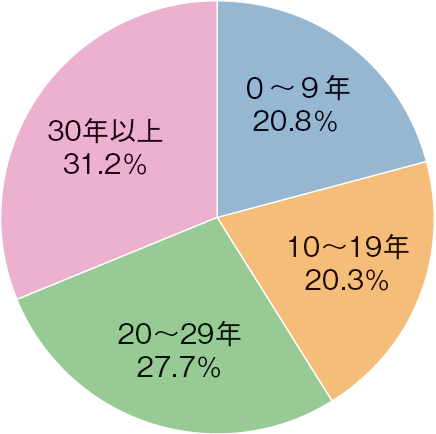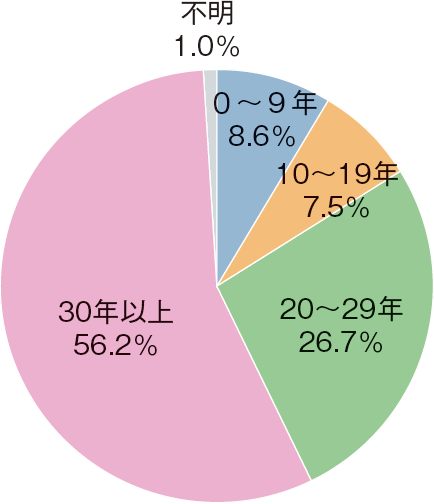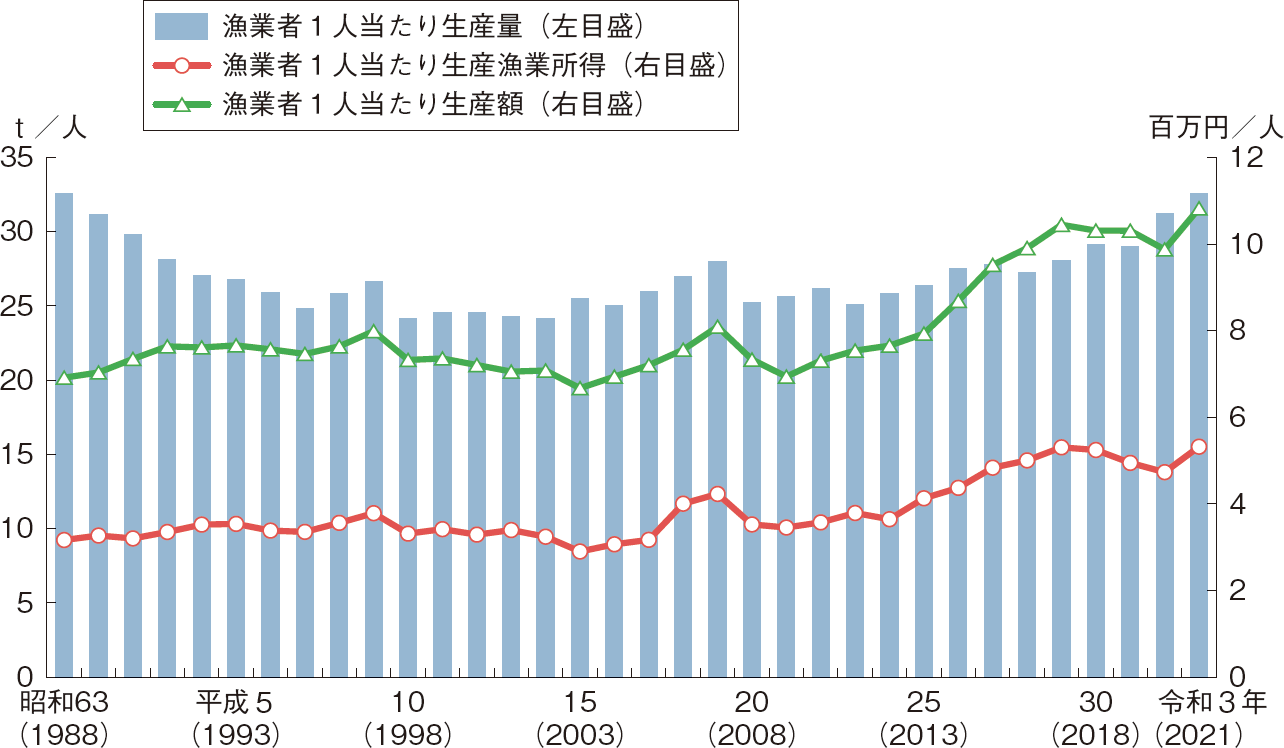(2)漁業・養殖業の経営の動向
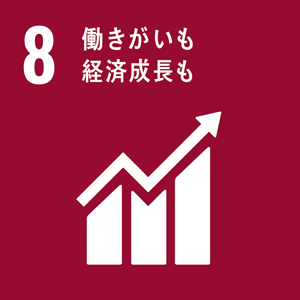


ア 水産物の産地価格の推移
〈不漁が続き漁獲量が減少したサンマやスルメイカは高値〉
水産物の価格は、資源の変動や気象状況等による各魚種の生産状況、国内外の需要の動向等、様々な要因の影響を複合的に受けて変動します。
特に、マイワシ、サバ類、サンマ等の多獲性魚種の価格は、漁獲量の変化に伴って大きく変化します。令和4(2022)年の主要産地における平均価格を見てみると、近年資源量の増加により漁獲量が増加したマイワシの価格が低水準となる一方で、不漁が続き漁獲量が減少しているサンマやスルメイカは高値となっています(図表2-3)。
図表2-3 主な魚種の漁獲量と主要産地における価格の推移
漁業及び養殖業の平均産地価格は、近年の上昇傾向から平成29(2017)年以降は下降傾向となったものの、令和3(2021)年には、前年から16円/kg上昇し、327円/kgとなりました(図表2-4)。
図表2-4 漁業・養殖業の平均産地価格の推移
イ 漁船漁業の経営状況
〈沿岸漁船漁業を営む個人経営体の漁労所得は114万円〉
令和3(2021)年の沿岸漁船漁業*1を営む個人経営体の漁労所得は、前年から2万円増加し、114万円となりました(図表2-5)。これは、漁獲量の増加により、漁労収入が増加したためです。漁労支出の内訳では、修繕費、油費等が増加しました。
なお、水産加工や民宿の経営といった漁労外事業所得は、前年から3万円減少して20万円となり、漁労所得にこれを加えた事業所得は、134万円となりました。
- 船外機付漁船及び10トン未満の動力漁船を使用した漁業。沿岸地域で、主に日帰りで行う漁業であり、一例としては、イワシ、イカナゴ等を漁獲する船びき網漁業、マグロ類を漁獲するひき縄釣り漁業。
図表2-5 沿岸漁船漁業を営む個人経営体の経営状況の推移

沿岸漁船漁業を営む個人経営体には、数億円規模の売上げがあるものから、ほとんど販売を行わず自給的に漁業に従事するものまで、様々な規模の経営体が含まれます。平成30(2018)年における沿岸漁船漁業を営む個人経営体の販売金額を見てみると、300万円未満の経営体が全体の7割近くを占めており、また、このような零細な経営体の割合は、平成25(2013)年と比べると平成30(2018)年にはやや減少していますが、平成20(2008)年と比べると増加しています(図表2-6)。また、平成30(2018)年の販売金額を年齢階層別に見てみると、販売金額300万円未満の割合は64歳以下の階層より65歳以上の階層で多く、65歳以上の階層では販売金額300万円未満が7割以上、75歳以上の階層では販売金額100万円未満が5割以上を占めています(図表2-7)。
〈10トン以上の漁船を用いて漁業を営む個人経営体の漁労所得は269万円〉
令和3(2021)年の10トン以上の漁船を用いて漁業を営む個人経営体*1の漁労所得は、前年から61万円減少し、269万円となりました(図表2-8)。これは、漁労収入が減少したためです。漁労支出の内訳では、油費等が増加しました。
- 日本近海で、1日から数週間かけて行われる漁業が主であり、一例としては、スケトウダラ等を漁獲する沖合底びき網漁業、メバチ、キハダ等を漁獲する近海まぐろはえ縄漁業。
図表2-8 10トン以上の漁船を用いて漁業を営む個人経営体の経営状況の推移
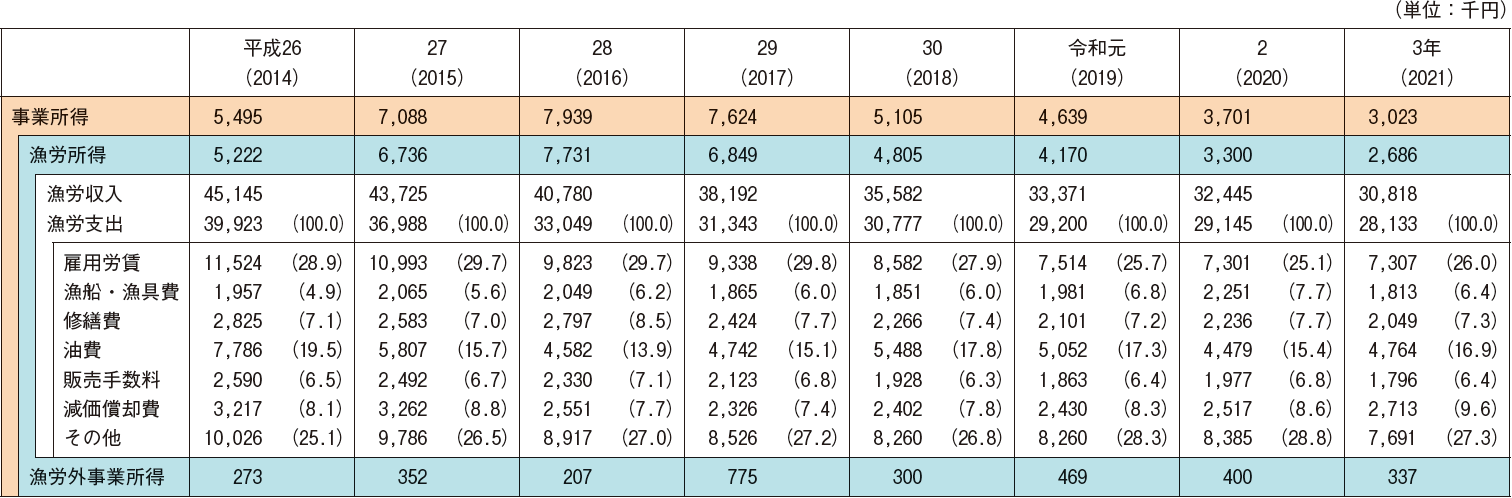
10トン以上の漁船を用いて漁業を営む個人経営体の販売金額は、平成30(2018)年において1,000万円以上の経営体が全体の6割を占めています(図表2-9)。また、平成30(2018)年の販売金額を年齢階層別に見てみると、いずれの階層においても販売金額1,000万円以上が5割以上を占めています(図表2-10)。
〈漁船漁業を営む会社経営体の営業利益は1,158万円の赤字〉
漁船漁業を営む会社経営体では、漁労利益の赤字が続いており、令和3(2021)年度には、漁労利益の赤字幅は前年度から1,400万円増加して5,612万円となりました(図表2-11)。これは、漁獲量の減少により漁労収入が1,971万円減少したことによります。漁労支出の内訳を見ると、前年度から修繕費が166万円増加し、労務費が138万円、油費が103万円減少しています。
また、近年総じて増加傾向が続いてきた水産加工等による漁労外利益は、令和3(2021)年度には、前年度から1,200万円増加して4,453万円となりました。この結果、漁労利益と漁労外利益を合わせた営業利益は1,158万円の赤字となりました。
図表2-11 漁船漁業を営む会社経営体の経営状況の推移
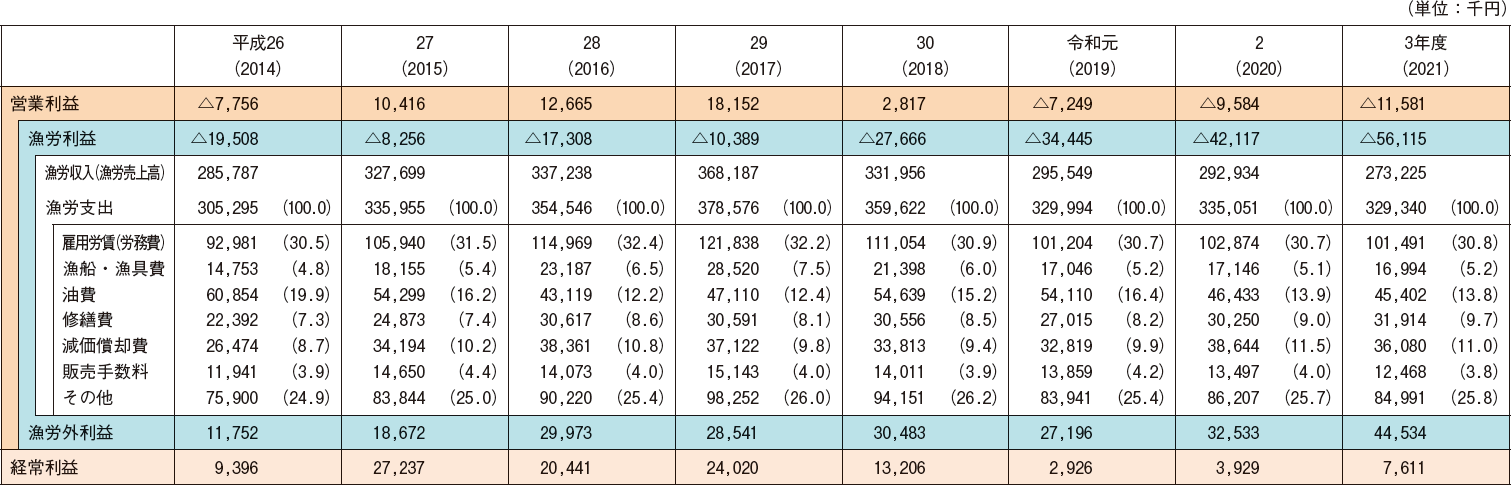
〈10トン未満の漁船では船齢20年以上の船が全体の8割〉
我が国の漁業で使用される漁船については、引き続き高船齢化が進んでいます。令和4(2022)年に大臣許可漁業の許可を受けている漁船では、船齢20年以上の船が全体の約6割、30年以上の船が全体の約3割を占めています(図表2-12)。また、令和3(2021)年度に漁船保険に加入していた10トン未満の漁船では、船齢20年以上の船が全体の約8割、30年以上の船が全体の5割以上を占めています(図表2-13)。
漁船は漁業の基幹的な生産設備ですが、高船齢化が進んで設備の能力が低下すると、操業の効率を低下させ、漁業の収益性を悪化させるおそれがあります。そこで、水産庁は、高性能漁船の導入等により収益性の高い操業体制への転換を目指すモデル的な取組等に対して、漁業構造改革総合対策事業(もうかる漁業)や水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業(漁船リース事業)による支援を行っています。
ウ 養殖業の経営状況
〈海面養殖業を営む個人経営体の漁労所得は496万円〉
海面養殖業を営む個人経営体の漁労所得は変動が大きく、令和3(2021)年は、前年から31万円減少して496万円となりました(図表2-14)。これは、ほたてがい養殖業の漁労収入が増加したこと等により、漁労収入が87万円増加した一方、漁労支出が118万円増加したためです。
図表2-14 海面養殖経営体(個人経営体)の経営状況の推移

エ 漁業・養殖業の生産性
〈漁業者1人当たりの生産額は1,083万円〉
漁業就業者数が減少する中、我が国の漁業者1人当たりの生産額及び生産漁業所得はおおむね増加傾向で推移してきたものの、平成29(2017)年以降は、漁業・養殖業生産額の減少に伴い減少が続きました。しかし、令和3(2021)年は、生産額が1,083万円、生産漁業所得が532万円と前年より増加しました。また、漁業者1人当たりの生産量は32.6tとなっています(図表2-15)。
図表2-15 漁業者1人当たりの生産性
オ 所得の向上を目指す「浜の活力再生プラン」
〈全国で554地区が浜の活力再生プランの取組を実施〉
多様な漁法により多様な魚介類を対象とした漁業が営まれている我が国では、漁業の振興のための課題は地域や経営体によって様々です。このため、各地域や経営体が抱える課題に適切に対応していくためには、トップダウンによる画一的な方策によるのではなく、地域の漁業者自らが地域ごとの実情に即した具体的な解決策を考えて合意形成を図っていくことが必要です。このため、水産庁は、平成25(2013)年度より、各漁村地域の漁業者の所得を5年間で10%以上向上させることで漁村地域の活性化を目指すために、地域の漁業の課題を漁業者自らが地方公共団体等と共に考え、解決の方策を取りまとめて実施する「浜の活力再生プラン」(以下「浜プラン」といいます。)を推進しています。水産庁の承認を受けた浜プランに盛り込まれた浜の取組は、関連施策の実施の際に優先的に採択されるなど、目標の達成に向けた支援が集中して行われる仕組みとなっています。
令和4(2022)年度末時点で、全国で554地区の浜プランが、水産庁の承認を受けて、各取組を実施しており、その内容は、地域ブランドの確立や消費者ニーズに沿った加工品の開発等により付加価値の向上を図るもの、輸出体制の強化を図るもの、観光連携を強化するもの等、各地域の強みや課題により多様です(図表2-16)。
図表2-16 浜の活力再生プランの取組内容の例

これまでの浜プランの取組状況を見てみると、令和3(2021)年度に浜プランを実施した地区のうち、33%の地区は所得目標を上回りました。所得の増減の背景は地区ごとに様々ですが、効果があった取組として、活け締め等による魚価向上に向けた取組や、種苗放流等の販売量向上に向けた取組等が挙げられます。一方で、効果が認められなかった取組については、その要因として新型コロナウイルス感染症拡大の影響による高級魚をはじめとする魚価の低迷や、燃油価格の高騰等が挙げられます。
また、平成27(2015)年度からは、より広域的な競争力強化のための取組を行う「浜の活力再生広域プラン」(以下「広域浜プラン」といいます。)も推進しています。広域浜プランには、浜プランに取り組む地域を含む複数の地域が連携し、それぞれの地域が有する産地市場、加工・冷凍施設等の集約・再整備や、施設の再編に伴って空いた漁港内の水面を増養殖や蓄養向けに転換する浜の機能再編の取組、広域浜プランにおいて中核的漁業者として位置付けられた者が、競争力強化を実践するために必要な漁船をリース方式により円滑に導入する取組等が盛り込まれ、これらの取組は関連施策の対象として支援されます。令和4(2022)年度末までに、全国で142件の広域浜プランが策定され、実施されています。
今後とも、これら浜プラン・広域浜プランの枠組みに基づき、各地域の漁業者が自律的・主体的にそれぞれの課題に取り組むことにより、漁業者の所得の向上や漁村の活性化につながることが期待されます。
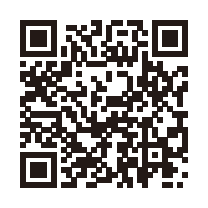
事例地域ごとの実情に即した浜の活力再生プラン
田尻(たじり)地区地域水産業再生委員会
大阪府田尻町(たじりちょう)は大阪市(おおさかし)内から50分以内の場所に位置しているほか、対岸に関西空港を臨むといった立地特性を持ち、刺網漁業やカゴ漁等の比較的小型な漁業を中心に操業されています。また、大阪湾の魚や漁業の魅力を消費者に直接提供することを重視し、日曜朝市を開催するなど海業(うみぎょう)を取り入れた事業を展開しています。当地域では、田尻漁協と田尻町、大阪府で構成する地域水産業再生委員会が、平成28(2016)年度から浜プランを策定し、漁業者の所得向上を目指した取組を実施しています。
本委員会では、アクセス性の良い立地特性を活かし、国内外の観光客を対象とした海業を実施しています。具体的には、漁業者等が出店し水産物を直接販売する日曜朝市や、日帰りバスツアーや小学校の体験授業を受け入れる漁業体験事業、漁業体験で漁獲された魚介類を楽しむことができる海鮮バーベキュー等、田尻の海と水産物を楽しむことができる事業を多く実施しています。令和2(2020)年度には新型コロナウイルス感染症の影響により一部事業を休止せざるを得ない厳しい状況となりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響が比較的少なかった日曜朝市等の事業を強化するとともに、海業への過度な依存を防ぐためにも、わかめ養殖を中心とした養殖業を更に振興していくこととしています。
これらの海業等を通じた取組は地元水産物の販路拡大に大きく寄与し、漁業者の所得向上及び地域活性化を実現しています。



お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344