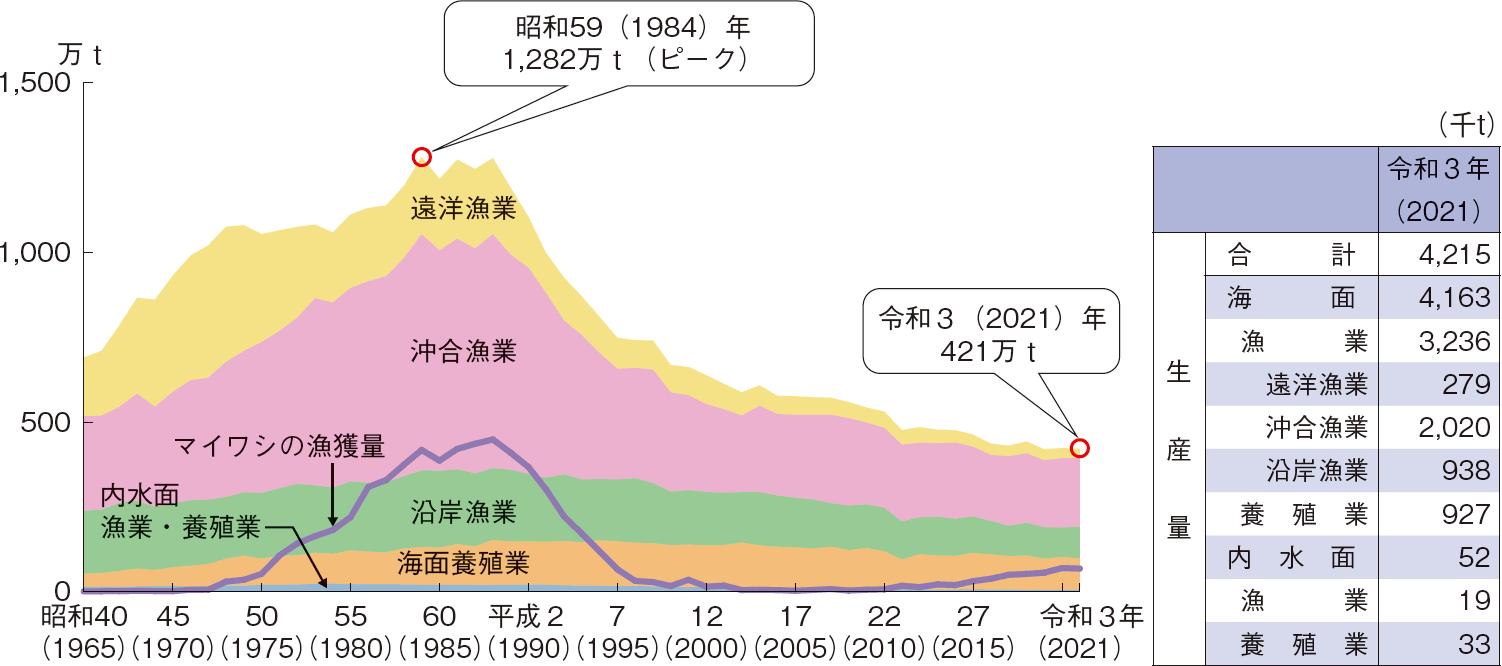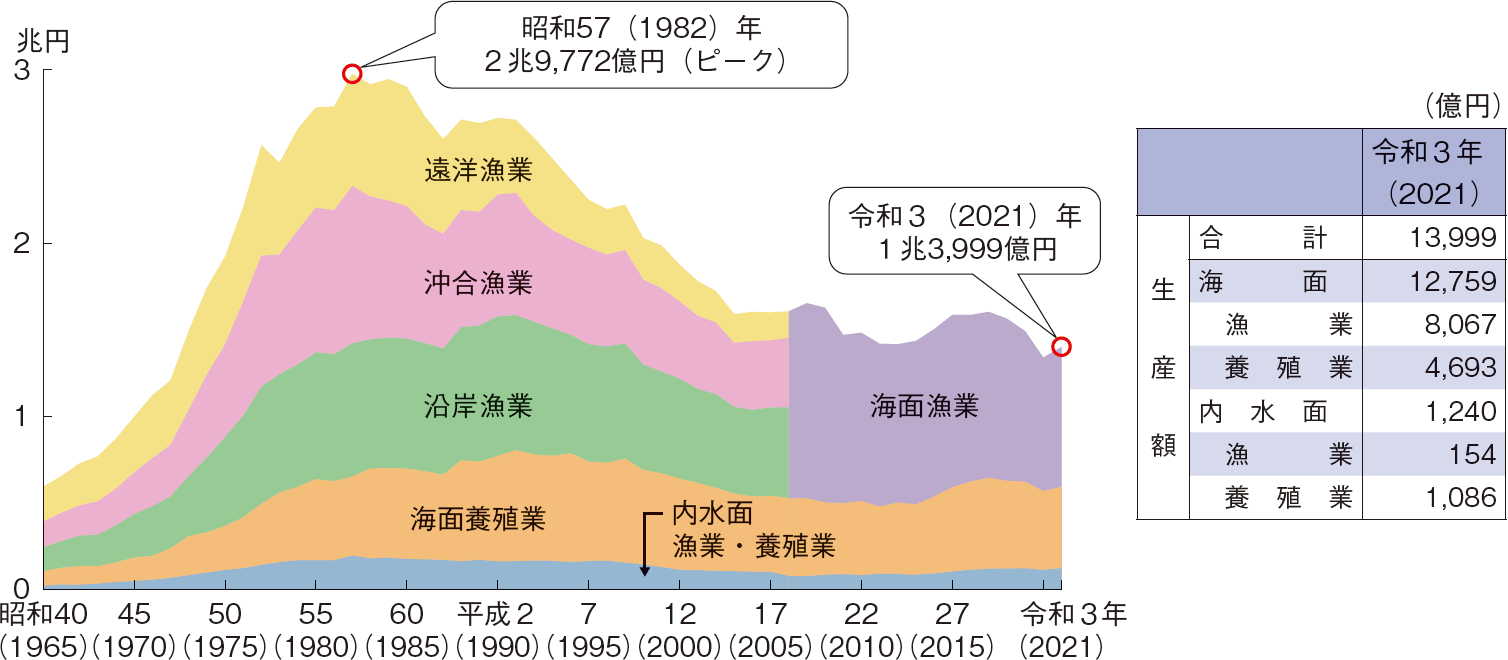(1)漁業・養殖業の国内生産の動向
〈漁業・養殖業の生産量は減少し、生産額は増加〉
令和3(2021)年の我が国の漁業・養殖業生産量は、前年から2万t減少し、421万tとなりました(図表2-1)。
このうち、海面漁業の漁獲量は、前年から2万t増加し、324万tでした。魚種別では、サバ類、カツオ等が増加し、カタクチイワシ等が減少しました。他方、海面養殖業の収獲量は93万tで、前年から4万t (4%)減少しました。これは、海藻類が減少したこと等によります。また、内水面漁業・養殖業の生産量は、5万tで、前年から1千t (2%)増加しました。
令和3(2021)年の我が国の漁業・養殖業の生産額は、前年から602億円(4%)増加し、1兆3,999億円となりました(図表2-2)。
このうち、海面漁業の生産額は8,067億円で、前年から346億円(4%)増加しました。この要因としては、ホタテガイにおいて、輸出需要の増加、外食需要の回復により価格安となった前年に比べ価格が上昇したこと等が影響したと考えられます。
海面養殖業の生産額は4,693億円で、前年から144億円(3%)増加しました。この要因としては、ブリ類、マダイ、ホタテガイ等において、輸出需要の増加、外食需要の回復により価格安となった前年に比べ価格が上昇したこと等が影響したものと考えられます。
内水面漁業・養殖業の生産額は1,240億円で、前年から112億円(10%)の増加となりました。
図表2-1 漁業・養殖業の生産量の推移
図表2-2 漁業・養殖業の生産額の推移
コラム陸上養殖の実態調査
陸上養殖は、漁業権を必要とせず、各地で新規参入が進んでいますが、実態に関する情報が十分にはない状況です。このため、水産庁は、漁業権が設定されていない場所で塩水(海水、人工海水等)を利用して養殖業を営んでいる者等を対象として実態調査を行い、その結果を令和4(2022)年6月に公表しました。
結果によると、回答者(回答率28%)における令和3(2021)年の陸上養殖の推定収獲量は、2,356tであり、ヒラメ、ニジマス、クルマエビ、トラフグ、ウミブドウ(クビレヅタ)が収獲量の上位となりました。
また、養殖地については、ヒラメは西日本に多い傾向であり、ニジマス等のサケ・マス類は東日本に集中し、クルマエビは鹿児島県及び沖縄県が多く、トラフグは全国的に生産されていることが分かりました。
こうした生産実態をより正確に把握していくため、水産庁は、陸上養殖を内水面漁業の振興に関する法律*に基づく届出養殖業とすることとしました。今後は、令和5(2023)年4月1日に開始される届出制に基づき、陸上養殖の実態把握を行い、陸上養殖の持続的かつ健全な発展の振興に努めていきます。
- 平成26年法律第103号
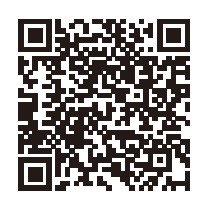
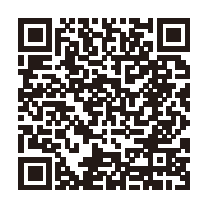
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344