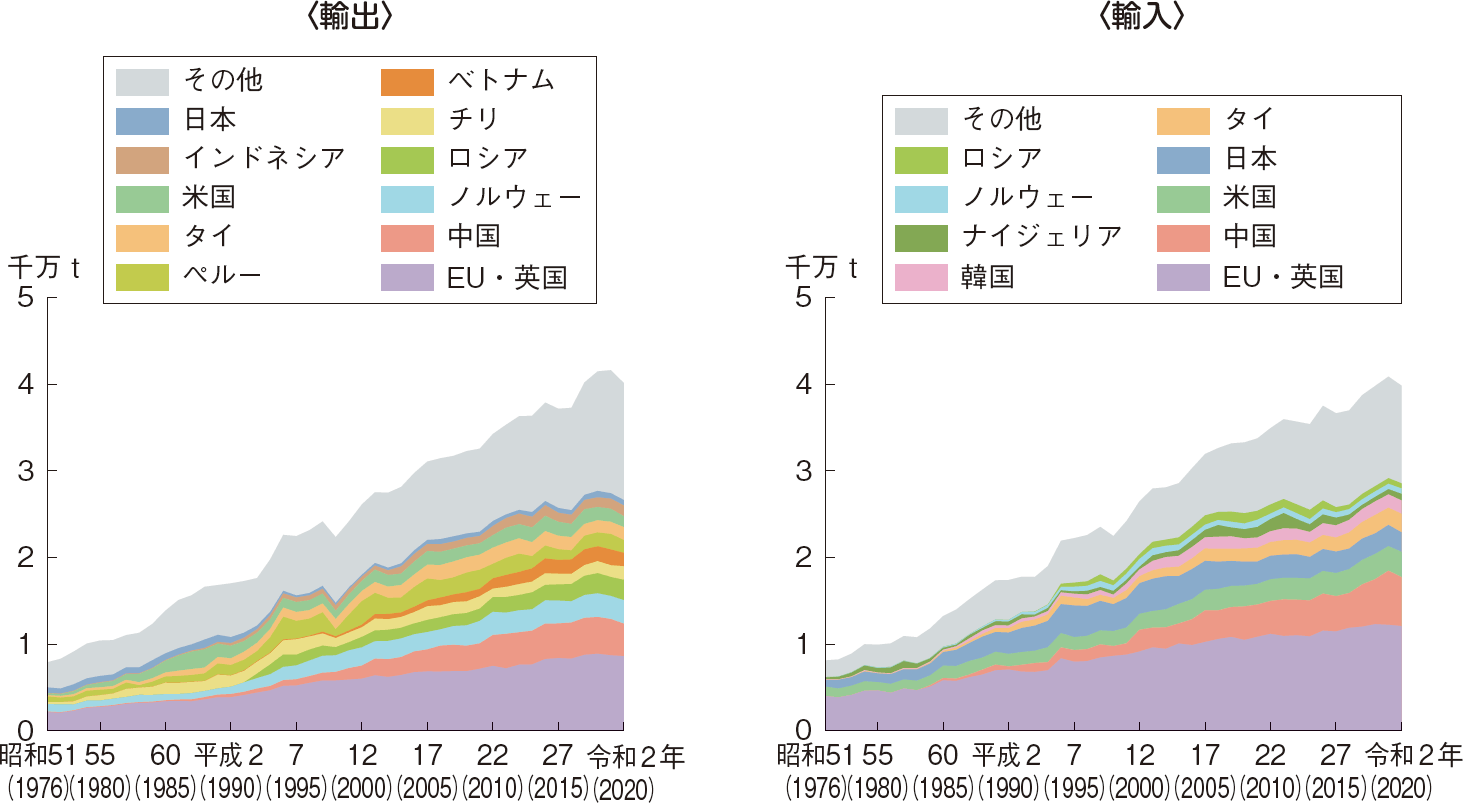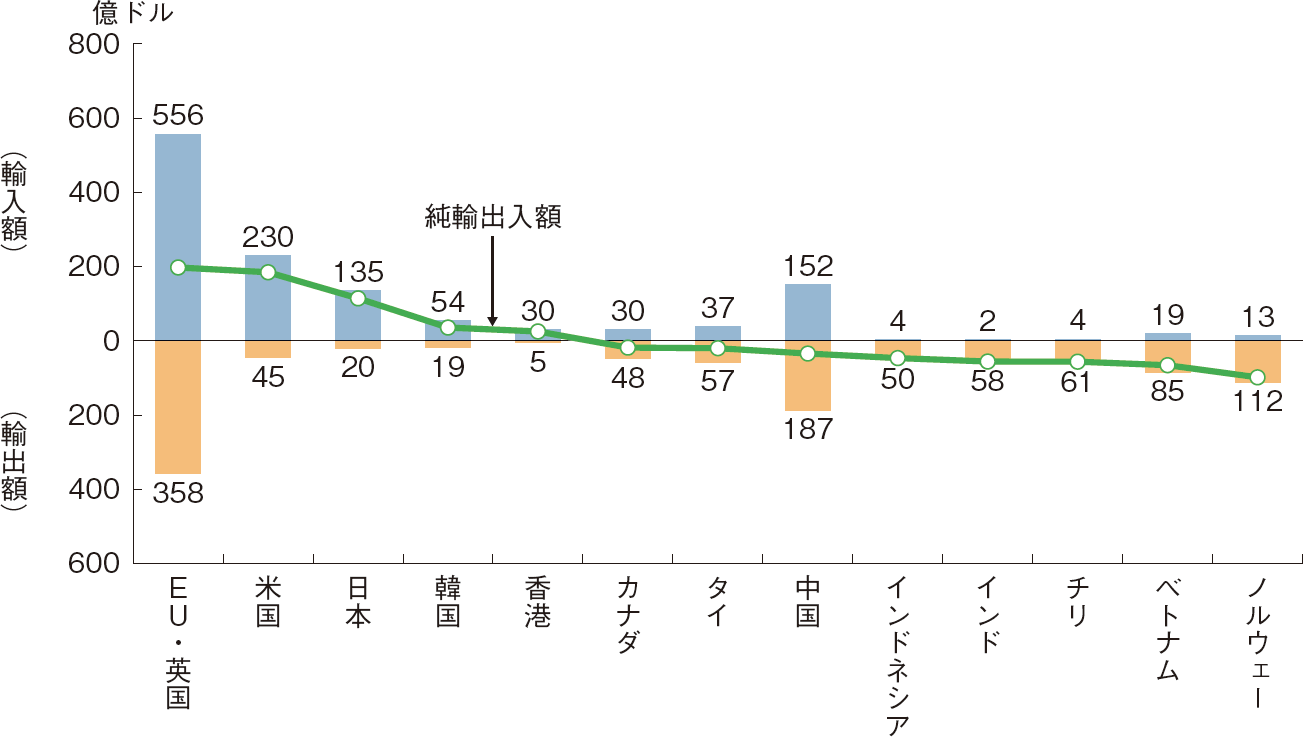(3)世界の水産物貿易
〈水産物輸出入量は増加傾向〉
現代では、様々な食料品が国際的に取引され、中でも水産物は国際取引に仕向けられる割合の高い国際商材であり、世界の漁業・養殖業生産量の3割以上が輸出に仕向けられています*1。また、輸送費の低下と流通技術の向上、人件費の安い国への加工場の移転、貿易自由化の進展等を背景として、水産物輸出入量は総じて増加傾向にあります(図表4-7)。
- FAO「The State of World Fisheries and Aquaculture 2022」。なお、生産量には藻類の生産量は含まれていない。
図表4-7 世界の水産物輸出入量の推移
水産物の輸出量ではEU・英国、中国、ノルウェー、ロシア等が上位を占めており、輸入量ではEU・英国、中国、米国、日本等が上位となっています。特に中国による水産物の輸出入量は大きく増加しており、2000年代半ば以降、単独の国としては世界最大の輸出国かつ輸入国となっています。また、EU・英国、米国、日本等が純輸入国・地域となっています(図表4-8)。我が国の魚介類消費量は減少傾向にあるものの、現在でも世界で上位の需要があり、その需要は世界有数の規模の国内漁業・養殖業生産量及び輸入量によって賄われています。
図表4-8 主要国・地域の水産物輸出入額及び純輸出入額
コラムOECD・FAOによる世界の魚介類の需給予測
経済協力開発機構(OECD)とFAOは、毎年、今後10年間の世界における魚介類を含めた食料等の生産や消費、貿易等の需給予測を行っています。
令和4(2022)年に発表された「OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031」によると、魚介類は栄養価の高い食品であるという認識の高まりから、需要は今後10年間で増加すると見込まれています。ただし、食用魚介類の消費量は、平成24(2012)~令和3(2021)年の年2.0%増加のペースから、令和4(2022)~13(2031)年は、年1.4%増加のペースに減速すると予測されています。この主な理由は、世界の漁業・養殖業生産量の増加のペースの減速や、一部の肉類の価格と比較して魚の価格が高くなること、世界の人口増加のペースが低下することが挙げられます。
また、世界の1人当たりの食用魚介類の消費量(粗食料ベース)は、令和元(2019)~3(2021)年の平均の20.5kgから、令和13(2031)年には21.4kgに達すると予測されています。ただし、低・中所得国、高・中所得国及び高所得国では、今後10年間で1人当たりの消費量は増加する一方、低所得国では、6.1%減少すると見込まれています。
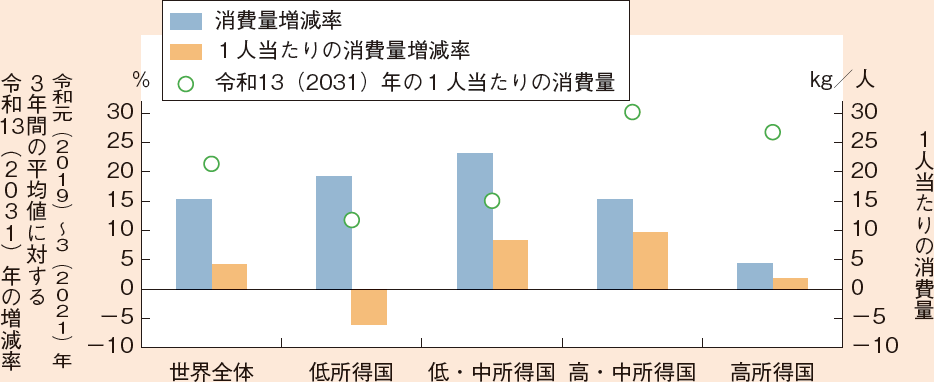
さらに、価格について見てみると、名目値では上昇し、過去の水準に比べて高止まりと予想されています。しかし、実質値では、養殖を除く全ての品目の価格が下落すると予想されています。この主な理由として、食用魚介類については、肉類との競争の激化や養殖の増加、魚油や魚粉については植物由来の代替品の価格の影響等が挙げられます。
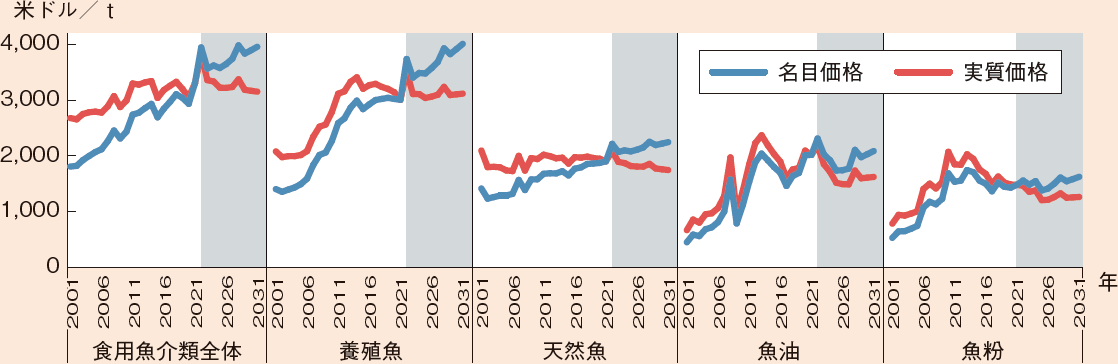
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344