(3)漁村の活性化
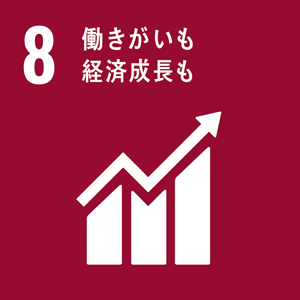

〈海や漁村に関する地域資源を活かした「海業」〉
漁村は、豊かな自然環境、四季折々の新鮮な水産物や特徴的な加工技術、伝統文化、親水性レクリエーションの機会等の様々な地域資源を有しています。漁村の活性化のためには、それぞれが有する地域資源を十分に把握し最大限に活用することが重要です。
令和4(2022)年3月に閣議決定された水産基本計画及び漁港漁場整備長期計画において、「海業(うみぎょう)」という言葉が盛り込まれました。この言葉は、昭和60(1985)年に神奈川県三浦市(みうらし)により提唱されたもので、「海の資質、海の資源を最大限に利用していく」をコンセプトに、漁業や漁港を核として地域経済の活性化を目指すとされています。
両計画において、海業は「海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業」と定義されています。漁村の人口減少や高齢化等、地域の活力が低下する中で、漁業利用との調和を図りつつ地域資源と既存の漁港施設を最大限に活用し、水産業と相互に補完し合う産業である海業を育成し、根付かせることによって、地域の所得と雇用の機会の確保を目指しています。
漁港における海業としては、用地等を活用した水産物等の販売・提供、プレジャーボートの受入れ、陸上養殖を行う事業、水域を活用した蓄養・養殖、漁業体験、海釣りを行う事業等が挙げられます。
また、漁港機能の再編・集約等により生じた空いた漁港の水域や用地等が増養殖や水産物直売所等の海業等に活用され、漁村の活性化に寄与しています。
平成31(2019)年3月時点で144漁港において陸上養殖が、385漁港において水域を活用した養殖等が行われています。この一層の利用促進を図るため、水産庁は、「漁港水域等を活用した増養殖の手引き」(令和2(2020)年9月策定)を周知しました。
また、令和3(2021)年12月時点で60漁港において、水産物直売所等として漁港施設用地が活用されているほか、漁港施設の貸付けにより、民間事業者によって製氷施設等が整備され、漁港機能の高度化が図られています。
このような漁港の有効活用をより一層推進するため、水産庁は、実践的なノウハウや豊富な事例を取りまとめた「漁港施設の有効活用ガイドブック」を公表しています(令和3(2021)年8月)。


〈伝統的な生活体験や漁村地域の人々との交流を楽しむ「渚泊」を推進〉
漁村の活性化のためには、観光客等の来訪者を増やし、交流を促進することも重要な方策の一つです。そのため、全国の漁港及びその背後集落には、令和3(2021)年度末時点で約1,500の水産物直売所等の交流施設が整備されています(図表5-5)。このような取組を推進するためには、1)地域全体の将来像を描くとともに、交流の目的を明確にし、解決すべき地域の課題等を整理し戦略を立てること、2)交流に取り組むメンバーの役割分担を明らかにし、地域の実情に即して実践・継続可能な推進体制をつくること、3)取組の実践と継続を意識し、交流により地域の問題解決を目指すこと、が重要です。また、地域の観光推進組織と連携することで、より効果的に取組を展開することも可能になります。
さらに、マイクロツーリズムやワーケーションといった新たな交流の取組も推進しています。くわえて、今後は、交流においても持続可能性の視点が重要であり、交流を通じて、地域の水産業を中心とした経済活動や、地域の生活・歴史・文化、自然環境等を保全していくことが求められます。
このような中、農山漁村地域に宿泊・滞在しながら我が国ならではの伝統的な生活体験や地域の人々との交流を楽しめる「農泊(のうはく)」(農山漁村滞在型旅行)をビジネスとして実施できる体制を持った地域を、令和4(2022)年度までに621地域創出しました。具体的には地域資源を魅力ある観光コンテンツとして磨き上げる取組等のソフト面での支援や、古民家等を活用した滞在施設や農林漁業・農山漁村体験施設等のハード面での支援を行っており、このうち漁村地域においては「渚泊(なぎさはく)」として推進しています。
図表5-5 全国の漁港及びその背後集落における水産物直売所等の交流施設
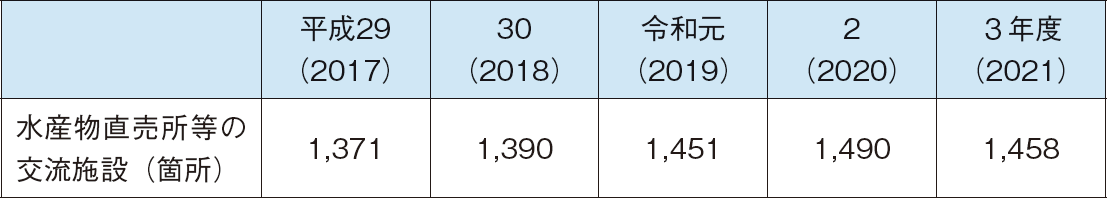
コラム世界農業遺産滋賀県琵琶湖地域の伝統的漁業と食文化
滋賀県琵琶湖地域では、漁業と水田農業を通じて、人々は古来より琵琶湖の恵みを利用してきました。琵琶湖では、エリ漁という伝統的な待ち受け型の漁法を用いた水産資源に配慮した漁を行っており、江戸時代以前から、漁網の目合い及び設置数の制限等の資源保全が受け継がれています。エリ漁をはじめとする特色ある漁法で獲れた湖魚は、ふなずし等伝統食に利用され、祭礼の供え物とするなど琵琶湖地域の文化を形成してきました。
ふなずしの原料であるニゴロブナ等にとって、エサが多く天敵の少ない琵琶湖岸のヨシ帯は重要な産卵繁殖の場です。湖魚たちはそのヨシ帯の環境に近い琵琶湖沿岸部の水田も産卵繁殖の場として上手(うま)く活用しています。漁業者や農業者たちは、ヨシ帯の保全と同時に、湖魚の成育の場となっている水田の環境を守るため、水田への魚道の設置等の取組を行っている「魚のゆりかご水田プロジェクト」や、農薬や化学肥料を通常の半分以下の使用量にする「環境こだわり農業」、明治時代より続く水源林の保全活動等、琵琶湖周辺の水質や生態系に配慮した様々な取組を行っています。
このような、「魚をはじめとする生態系」と「農業を基盤とする文化」の相互作用により、1,000年以上にわたって受け継がれてきた循環型のシステムが評価され、令和4(2022)年7月18日、「森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」として、新たに世界農業遺産*に認定されました。
- 世界農業遺産(GIAHS):社会や環境に適応しながら何世代にもわたり継承されてきた独自性のある伝統的な農林水産業と、それに密接に関わって育まれた文化、ランドスケープ及びシースケープ(レイクスケープ)、農業生物多様性等が相互に関連して一体となった、世界的に重要な伝統的農林水産業を営む地域(農林水産業システム)に対して、国際連合食糧農業機関(FAO)により認定されるもの。

お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344










