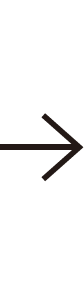(4)令和6年能登半島地震*1からの復旧・復興
〈地震・津波による被害の状況〉
令和6(2024)年1月1日午後4時10分、石川県能登地方(輪島(わじま)市の東北東30km付近)の深さ16kmを震源として、マグニチュード7.6(暫定値)の地震(以下「本地震」といいます。)が発生しました。本地震により、石川県輪島市や志賀町(しかまち)で最大震度7を観測したほか、能登地方の広い範囲で、震度6強や6弱の揺れを観測し、様々な被害が発生しました。この揺れの前後にも、規模の大きな地震が発生し、強い揺れが長く続きました。本地震は、逆断層型で、地殻内で発生した地震でした。
本地震により、津波も引き起こされました。この津波は、震源に近い石川県を中心に、富山県、新潟県、福井県をはじめとした北海道から九州地方にかけての日本海沿岸で観測されました。現地調査での推定によると、石川県能登町(のとちょう)や珠洲(すず)市で4m以上の津波の浸水高が、新潟県上越(じょうえつ)市で5m以上の遡上高*2が見られました。また、本地震により、地盤隆起も、能登半島の外浦(そとうら)地域の海岸等において生じました。国土地理院による測地観測データの解析によれば、最大4m程度の地盤隆起が報告されており、漁港内の海底でも隆起が見られ、漁港の利用や漁業の操業に支障が生じているところです。
本地震による死者は244人を超え(令和6(2024)年3月29日時点。災害関連死を含む。)、多くの人命が失われました。建造物の被害は、全壊約9千戸、半壊約1万9千戸、一部損壊約8万4千戸(同月26日時点)となっており、多くの方々が家や家財道具を失いました。いまだに約8千人の被災者が避難生活を余儀なくされています(同月29日時点)。また、石川県では、最大で約4万戸が停電し、電力、水道、ガス等のインフラに多大な被害がありました。電力、ガスについては、ほぼ復旧しましたが、水道については、最大で約5万6千戸が断水し、石川県輪島市、珠洲市、能登町などで、約8千戸について、給水が再開されていません(同月29日時点)。
- 気象庁が定めた名称で、令和6(2024)年1月1日に石川県能登地方で発生したM7.6の地震及び令和2(2020)年12月以降の一連の地震活動のことを指す。
- 津波が海岸に到達後、陸地をはい上がり、最も高くなった地点の高さを、平常潮位面から計測した高さ。
本地震の震源に近い石川県は、遠浅の砂浜が広がる加賀(かが)海域、岩礁域が広がる能登外浦海域、急深な能登内浦(うちうら)海域、一年を通じて平穏な七尾湾など変化に富んだ海岸線を有し、各海域でそれぞれの環境に応じた多種多様な漁業が営まれています。加賀海域には、ズワイガニ、ホッコクアカエビ(アマエビ)、カレイ類などが生息する砂泥域が広がり、底びき網漁業が発達しています。能登外浦海域は、岩礁や離島が点在する複雑な海底地形が特徴であり、底びき網漁業、刺網漁業、釣り漁業、定置漁業、まき網漁業、海女(あま)漁など、多種多様な漁法が発達しています。能登内浦海域は、急深であり、ブリなどの回遊魚が岸近くまで来遊するため、定置漁業が発達しているほか、小木(おぎ)港は、沖合でのいか釣り漁業の基地となっています。七尾湾は、波静かで、小河川が多く流れ込み、栄養塩類が豊富なため、カキやトリガイの垂下式養殖業が行われているほか、内湾に生息するナマコなどを漁獲する底びき網漁業も発達しています。石川県では、底びき網漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、定置漁業が、基幹となる漁業であり、令和4(2022)年には、この四つの漁法で、県全体の生産量の75%*1を占めています。このほか、小規模な個人経営体が主体である刺網漁業、釣り漁業、海女漁などが営まれており、これらの漁法は、平成30(2018)年の経営体数としては、県内の全経営体数の61%*2を占めています。
富山県では、海岸線がゆるやかな弓状をなし、総延長約100kmに及んでいます。富山湾は急峻で、最深部は1,100~1,200mとされ、沿岸部には海底谷が複雑に発達しています。沿岸では、古くから定置漁業が盛んで、ブリ、マイワシ、アジ、ホタルイカなどの浮魚類が主な漁獲対象となっているほか、シロエビやアマエビを漁獲対象とする小型底びき網漁業、ヒラメ等の底魚類を漁獲対象とする刺網漁業が行われています。令和4(2022)年には、この三つの漁法で、県全体の生産量の75%*3を占めています。このほか、沿岸部ではワカメ等の養殖業が行われています。また、沖合では、ベニズワイガニやバイ類を漁獲対象とするかごなわ漁業が富山湾近辺で行われています。
新潟県は佐渡島(さどしま)と粟島(あわしま)の2島を有し、海岸線は、総延長630kmに及んでいます。中越(ちゅうえつ)及び下越(かえつ)地区では広い大陸棚を有し、上越(じょうえつ)地区は、沿岸から急峻となる異なった地形となっています。佐渡(さど)地区は、岩礁域の海岸線が長く、沖合には、天然礁が点在し、複雑な漁場が形成されています。県内では、漁船漁業中心であり、定置、小型底びき網、刺網、かご漁業の割合が大きくなっています。
本地震の発生により、水産業関係では、漁船、漁具、漁港施設(岸壁、護岸等)、荷さばき所、給油施設、製氷・貯氷施設、冷凍庫・冷蔵庫、漁具倉庫、水産加工場、カキ、トリガイ等の養殖施設、サケふ化場、造船所など、水産業を支えるあらゆる生産基盤に甚大な被害がもたらされました。本地震による地盤隆起により、漁港内の海底が露出したり、泊地等の水深が浅くなることで、漁船が出港できなくなる、岸壁に接岸しての陸揚作業が難しくなる、津波により、大量のがれきや泥が漁港内や港につながる航路、漁場等に堆積する、漁船が漁港内外に打ち上げられるといった被害も生じています。海上保安庁の調査では、富山湾の海底において、谷の斜面が本地震により崩壊していることが明らかになり、津波の発生源である可能性が指摘されています。本斜面の崩壊により、漁場が荒廃し、漁業への影響が生じることが懸念されているところです。
さらに、漁港の後背地の漁村集落においても、本地震により、多数の漁業者の住居が損壊しました。被害が甚大だった能登地域は、三方を海に囲まれる半島であり、山がちで道路網の整備が難しく、また、幹線交通体系から離れているなどの交通アクセスの面で不利な条件を抱えていました。このため、陸路でのアクセスが困難な被災地が多数あったことから、本地震の発生を受け、一部地域では、道路、水道、電気等の復旧に時間を要し、生活再建の動きを始められない状況や外部からのアクセスが途絶する孤立集落が発生する状況が見られました。このような状況の下、水産関係の被害状況の全容把握には、時間を要しています(図表5-16)。
- 農林水産省「漁業・養殖業生産統計」
- 農林水産省「2018年漁業センサス」。経営体における販売金額1位の漁業種類が、刺網漁業、釣漁業、潜水器漁業及び採貝・採藻漁業の割合。
- 農林水産省「漁業・養殖業生産統計」
図表5-16 令和6年能登半島地震による水産関係の被害状況
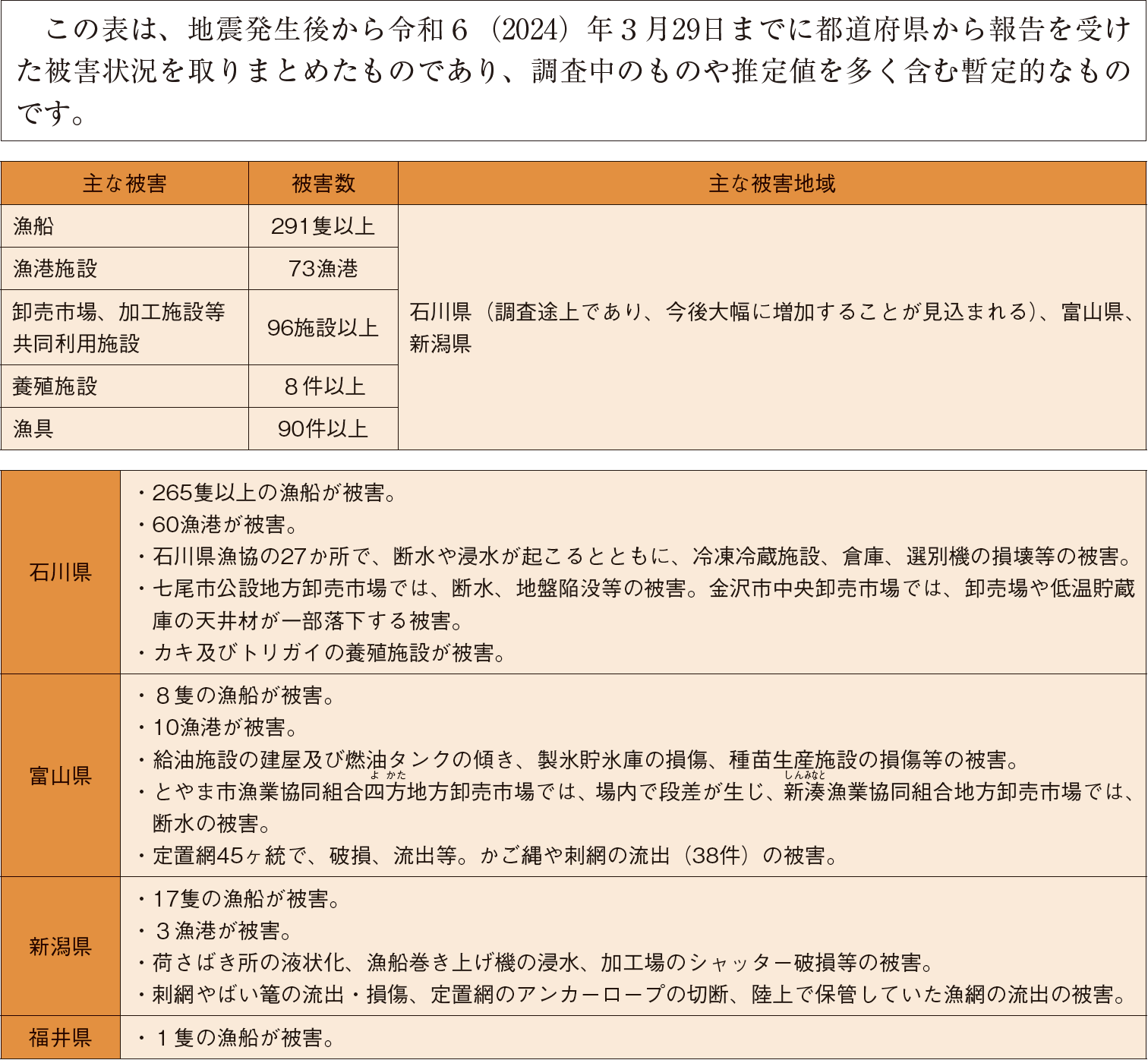
〈政府及び農林水産省の対応〉
政府においては、本地震の発生を受けて、令和6(2024)年1月1日、内閣府特命担当大臣(防災担当)を本部長とする「特定災害対策本部」が設置され、その後、同日、内閣総理大臣を本部長とする「非常災害対策本部」に移行されました。また、非常災害現地対策本部を設置し、各府省から多数の職員が、地方公共団体の復旧、復興の取組を支援するために派遣されました。さらに、本地震を対象とし、同月11日に「特定非常災害」及び「激甚災害」、19日に「非常災害」の指定が行われるとともに、25日に「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ」を政府として取りまとめ、被災地支援を行っていくこととしています(図表5-17)。
また、政府では、本地震からの復旧・復興を、関係府省の連携の下、政府一体となって迅速かつ強力に進めるため、同月31日に、閣僚全員を構成員とする「令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部」を設置しました。同本部を司令塔として、被災地方公共団体と緊密に連携し、被災者の方々の帰還と被災地の再生まで責任を持って取り組むこととしています。農林水産省としても、漁港、農地、林地等の早期復旧や事業再開に向けた支援など、被災した農林漁業者の一日でも早い生業再建に向け、全力で取り組んでいくこととしています。
図表5-17 被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッケージ
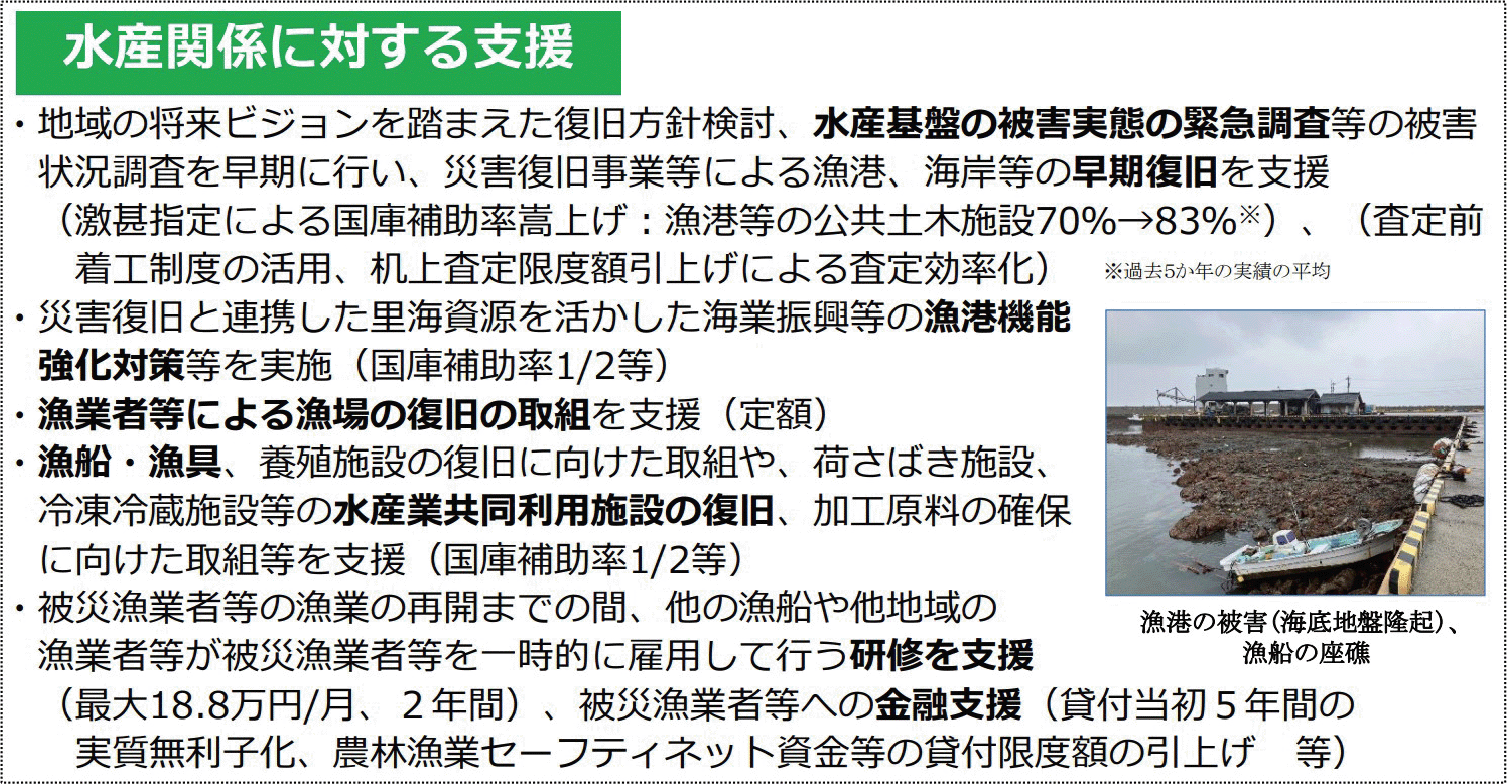
農林水産省においても、同月1日、農林水産大臣を本部長とする「農林水産省緊急自然災害対策本部」を設置しました。水産庁においても、同本部からの情報等を踏まえ、随時、庁内関係者による打合せを開催するなどにより、情報共有を図り、水産関係の被害状況を把握し、復旧・復興のための地域ニーズへの対応を迅速に図ってきています。
水産庁では、同月6日から14日にかけて、水産関係団体等から無償で提供を受けた支援物資(飲料水、缶詰、カイロ等)及び北陸農政局から提供された備蓄食料(アルファ化米等)を積み込んだ水産庁の漁業取締船「はやと」(499トン)、「おおくに」(1,282トン)、「白萩丸(しらはぎまる)」(916トン)、「白嶺丸(はくれいまる)」(913トン)が、石川県珠洲市の蛸島漁港へ支援物資を輸送(石川県や石川県漁協と調整の上、地元の漁業者と連携)しました。「はやと」は、蛸島漁港及び同市の狼煙(のろし)漁港の被災状況の調査も行いました。同月31日から2月7日には、石川県の要請を受け、水産庁は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に緊急調査を依頼し、同機構は漁業調査船「北光丸(ほっこうまる)」(902トン)を能登半島及び舳倉島(へぐらじま)周辺に派遣して、ドローンによる漁港・漁場の調査並びに海洋環境及び魚礁の緊急調査を実施しました。
金融関係においても、水産庁は、関係金融機関等に、本地震による被害を受けた漁業者等に対する資金の円滑な融通や既住債務の償還猶予等が適切に講じられるよう要請しました。また、漁業共済団体及び漁船保険団体に対しても、被害の早期把握、迅速な損害評価の実施及び共済金・保険金の早期支払を依頼しました。これを受け、漁業共済団体及び漁船保険団体は、被災漁業者の現地調査を行い、被害を早期に把握し、迅速に損害を評価し、共済金・保険金の早期支払の実施に努めているところです。
さらに、水産庁は、MAFF-SAT*1として、職員を現地に派遣し(123人日。同年3月末時点。)、水産関係被害の把握、技術支援等を行いました。また、22都道県*2から、職員を派遣いただき(781人日。同年3月末時点。水産庁調べ。)、水産庁からの派遣職員と連携し、被災地の漁港施設の被災状況の把握調査、災害査定などを支援しました。
- 農林水産省・サポート・アドバイス・チームの略称で、災害発生時に、農林水産省から被災した地方公共団体に職員を派遣し、迅速な被害の把握や被災地の早期復旧を支援。
- 北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県及び鹿児島県。
〈水産関係団体の被災地支援の取組〉
全国の水産関係団体も迅速に被災地支援に取り組みました。JF全漁連と一般社団法人大日本水産会は、地震発生直後に対策本部を設置し、被害状況の把握や現地への支援の取組を開始しました。
JF全漁連では、被災地に向けて、水産庁の漁業取締船を通じて、支援物資の提供を行ったほか、会員中心に支援募金を呼びかけるなどの取組を行いました。一般社団法人大日本水産会も、同様に、支援物資の提供や会員などからの義援金の募集を行いました。同会は、令和6(2024)年2月21日及び22日に開催された第21回シーフードショー大阪において、「能登半島地震支援ブース」を設け、石川県の水産業に係る被害状況や操業再開についての情報提供などを行いました。
また、一般社団法人水産土木建設技術センターは、職員を派遣し、水産庁からの派遣職員と連携し、被災地の漁港施設の被災状況の把握調査を支援しました。一般財団法人漁港漁場漁村総合研究所は、被災地の漁港及び漁業集落排水施設の被災状況調査を行いました。公益社団法人全国漁港漁場協会も、漁港の災害復旧のため、同協会のボランティア派遣制度を活用して、石川県に漁港の災害復旧支援のためボランティアを派遣しました。
〈漁港の復旧事業への着手及び被災地域の水産業の再開状況〉
本地震では、主に石川県の漁港で、地盤隆起や津波により、甚大な被害が生じました。水産庁では、被災した漁港、海岸等の被害実態の緊急調査を実施するとともに、災害復旧事業等による早期復旧を支援しています(図表5-18)。また、今回の被災状況の甚大さ及び複雑さに鑑み、大規模災害からの復興に関する法律*1に基づき、国の代行による漁港及び漁港海岸の復旧工事を実施することとしました。具体的には、石川県管理の狼煙漁港及び珠洲市管理の鵜飼漁港海岸について、石川県知事及び珠洲市長からの要請を受け、水産庁が代行工事を実施することとしています。さらに、地震で被災した輪島港等において、水産庁及び国土交通省は、石川県と連携して、座礁や損傷によって身動きが取れない漁船の移動に向けた対応を行っています。国土交通省は、漁船の航行に必要な水深を確保するため、漁船だまりの啓開作業及び港湾内の浚渫(しゅんせつ)作業を実施するとともに、水産庁は、サルベージ船による漁船の移動に対する支援を行うこととしています。
- 平成25年法律第55号
図表5-18 能登半島の漁港の被災調査状況
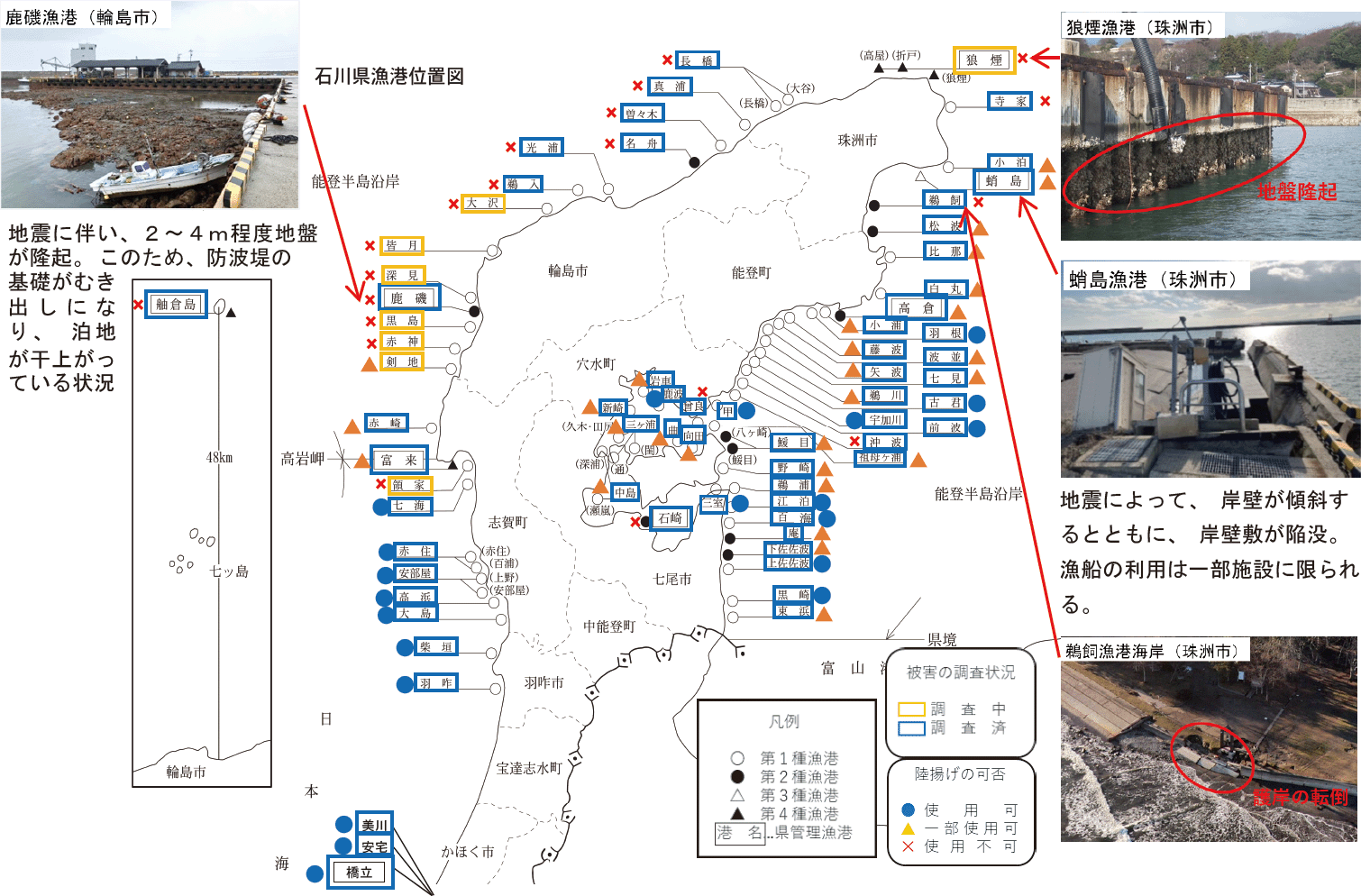
石川県や富山県内の漁業については、地震により操業が休止した地域が多数ありました。被災者の生活も完全に平常に復帰したとはいえず、漁業関係施設が損傷している中、岸壁、物揚場などの漁港設備の応急復旧工事を進め、断水したり、燃油タンクが損傷している状況下、操業に必要な氷や燃油を、金沢市、七尾(ななお)市などから輸送するといった対応を進め、一部では順次操業の再開が見られるようになりました。能登半島の外浦地域においては、志賀町の富来(とぎ)漁港で、令和6(2024)年1月中旬から月末にかけて、定置漁業、底びき網漁業などが再開しました。内浦地域の七尾市や能登島(のとじま)周辺でも、1月上旬に定置漁業が、1月中旬から一部のかき養殖事業者の出荷が、3月24日から底びき網漁業が再開しました。特に被害が大きかった珠洲市においても、蛸島漁港で、1月下旬に定置漁業が、3月下旬には底びき網漁業が再開しました。
さらに、卸売市場についても、七尾市公設地方卸売市場が、地震による断水、敷地内の一部での陥没等により、1月中の営業(競り)停止となりましたが、2月1日から、営業を再開しました。
水産加工業においても、多数の事業者が被災しましたが、徐々に製造を再開しているところも見られます。
〈被災地域の水産業の復旧・復興に向けて〉
被災地域の水産業の早期の復興を図ることは、地域経済や生活基盤の復興に直結するだけでなく、国民に対する豊かな水産物の供給を確保する上でも、極めて重要な課題です。
被災した水産関係者の方々が、困難を乗り越え、将来への希望と展望をもって水産業を再開できるよう、政府としても、漁業・加工流通業の再建や、漁港、漁場、漁船、養殖施設、さらには、漁村全体の復旧・復興に取り組むこととしています。
漁業・漁村の復旧・復興に際しては、生業の場としての漁場と漁港は、生活の場としての漁村集落と一体性があるため、生業と生活のあり方をまとめて考えていく必要があります。こうしたあり方を踏まえると、漁業やそれを支える漁村集落の将来像を描いていくためには、漁場や漁港、製氷施設等の共同利用施設など漁業に必要となる施設と、漁村集落のインフラをどうしていくのかについては、漁業者、漁協などの漁業関係者だけでなく、漁村集落に居住する地域住民も含めた関係者全体で議論していくことが必要となります。
令和6(2024)年2月22日には、内閣府と内閣官房が、「復興まちづくりに当たっての参考資料」を作成し、被災した地方公共団体に、情報提供を行い、関係府省が連携の上、被災した地方公共団体の復興まちづくりを継続的に支援することとしています。農林水産省としても、被災した地方公共団体が、これを参考にして地域の実情に応じた創意工夫が施された復興まちづくりを進められるよう、地域の計画の策定、事業の実施について、丁寧に相談に応じていくこととしています。また、被災地域の漁業関係者をはじめとした地域住民の方々が、各地域で、議論して描いた姿を実現するための支援を、各地域の実情を見据えつつ、行っていくこととしています。
当面の復旧対策として、令和5(2023)年度の予備費により、漁港の災害復旧等、災害復旧と連携した漁港機能回復・強化対策、漁船、市場、加工施設、関連施設等の回復(被災した漁船・定置網等の漁具の復旧のため、漁協等が行う漁船・定置網等の漁具の導入、被害を受けた養殖施設の復旧支援等)、漁業活動再開・継続への支援(被災した漁場の機能や生産力の再生・回復を図るため、漁業者等が行う漁場の状況を把握するための調査、漂流・堆積物の除去、漁場環境の改善等の取組支援等)を行うこととしています。
また、石川県、富山県、新潟県で、令和6(2024)年3月末時点では、合わせて20漁港と一部の共同利用施設について、応急工事を進めているところです。具体的には、2月20日に、石川県珠洲市の蛸島漁港で、地震により大きな段差が生じた岸壁の段差の解消工事を行い、岸壁の利用を再開しました。同県七尾市の鰀目(えのめ)漁港では、同様に、段差が生じた物揚場の段差を解消する工事を、1月26日から2月9日まで行い、物揚場の利用を再開しました。他の漁港でも、順次、応急工事を進めているところです。さらに、石川県における地盤隆起等甚大な被害を受けた漁港等について、県全体の復旧方針を検討するため、国も協力しつつ、漁業者・漁業関係団体、市町等の行政機関、研究機関などで構成する協議会を、3月25日に設置し、議論を開始しています。
そのほか、水産関係の支援策を漁業者等にきめ細かく周知するなど、現地対応力を強化するため、3月22日、石川県金沢市に水産庁の職員が常駐する事務所を開設し、4月12日、同事務所を奥能登地域(穴水町(あなみずまち))に移転しました。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344