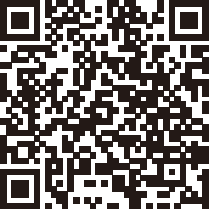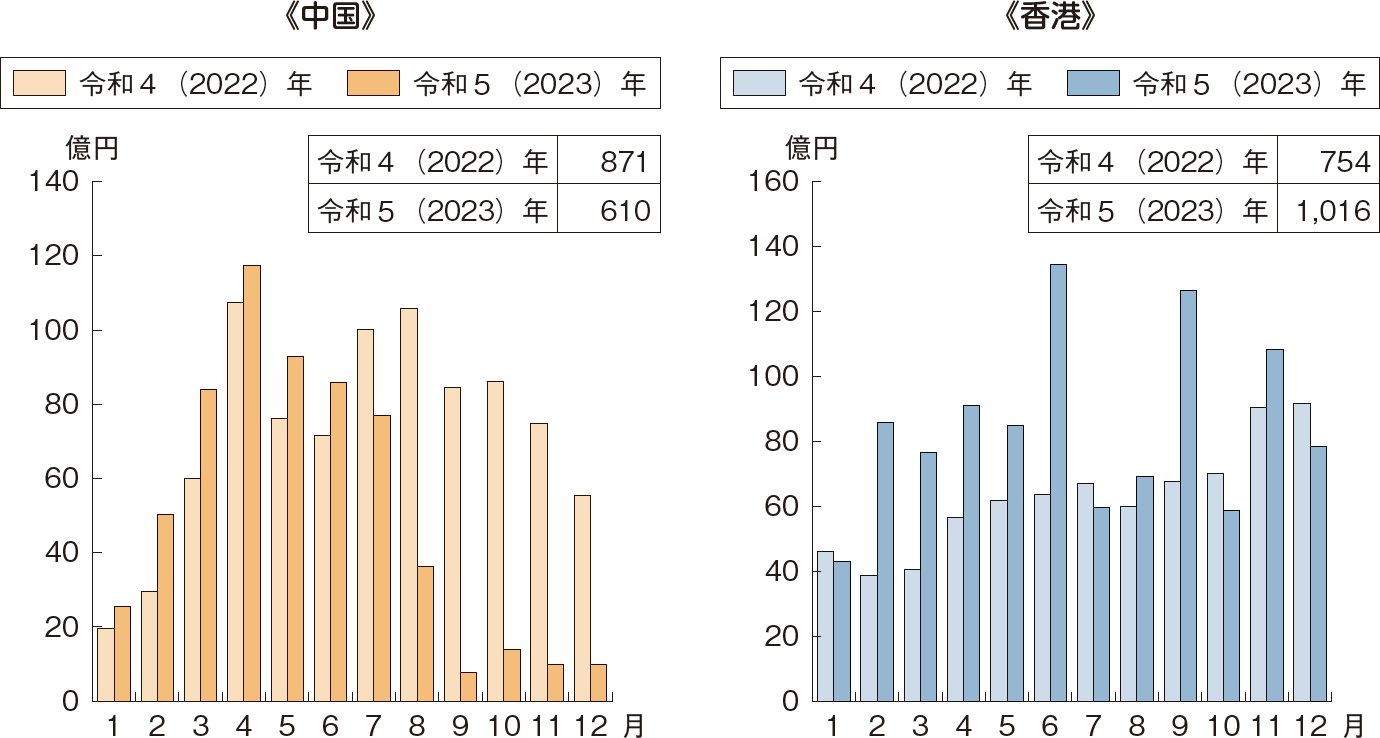(3)ALPS処理水の海洋放出をめぐる動き
ALPS処理水の海洋放出をめぐる主な動きは以下のとおりです(図表5-10)。
図表5-10 ALPS処理水の海洋放出をめぐる主な動き
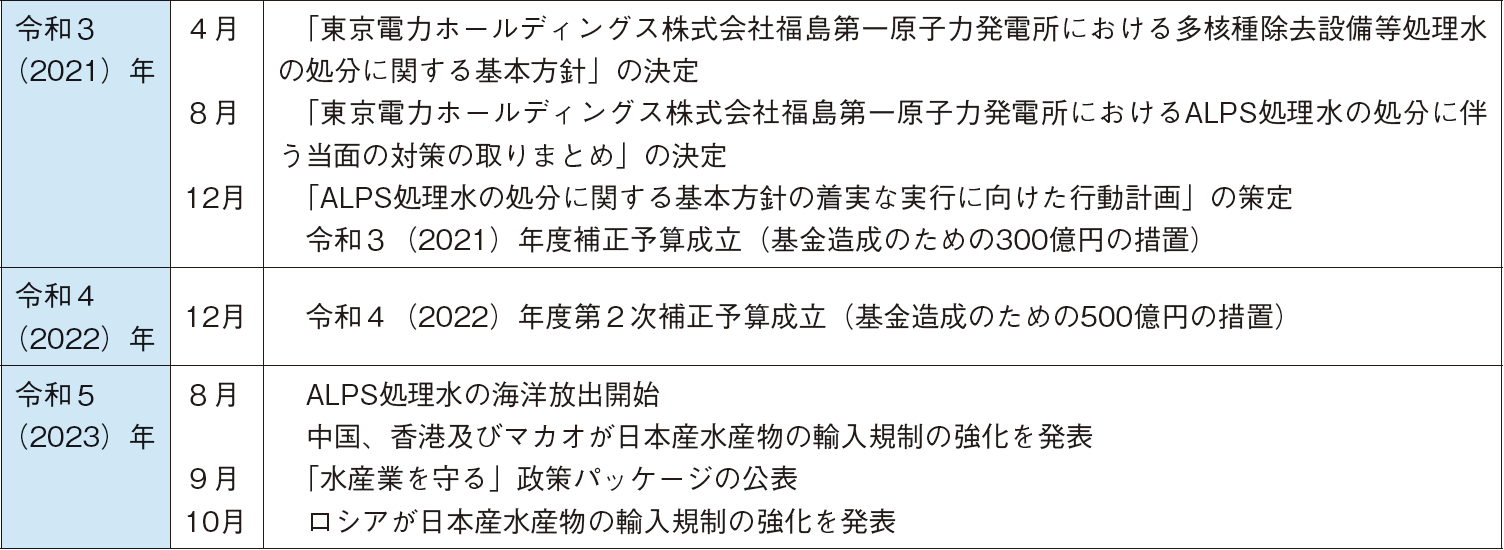
ア ALPS処理水の海洋放出前の取組
〈ALPS処理水の処分に関する基本方針等を策定〉
ALPS処理水の取扱いについて、令和2(2020)年2月に「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」が報告書を取りまとめたことを踏まえて、政府としてALPS処理水の取扱方針を決定するため、福島県の農林水産関係者をはじめ、幅広い関係者からの意見を伺いながら、議論を積み上げてきました。そして、令和3(2021)年4月に開催した「第5回廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議」において、安全性を確保し、政府を挙げて風評対策を徹底することを前提に、「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」を決定しました。
このことを踏まえ、将来生じ得る風評について、現時点で想定し得ない不測の影響が生じ得ることも考えられることから、必要な対策を検討するための枠組みとして、同年4月に「ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議」を開催し、同会議の下に、風評影響を受け得る方々の状況や課題を随時把握していく目的で、経済産業副大臣を座長とする関係省庁によるワーキンググループが新設されました。このワーキンググループは、同年5月から7月まで計6回開催され、地方公共団体・関係団体との意見交換を実施しました。この意見交換を踏まえ、同年8月に開催された同会議において、「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所におけるALPS処理水の処分に伴う当面の対策の取りまとめ」(以下「当面の対策の取りまとめ」といいます。)が決定され、水産関係では、新たにトリチウム(三重水素)を対象とした水産物のモニタリング検査の実施、生産・流通・加工・消費の各段階における徹底した対策等が盛り込まれました。
また、同年12月には、当面の対策の取りまとめに盛り込まれた対策ごとに今後1年間の取組や中長期的な方向性を整理した「ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた行動計画」(以下「行動計画」といいます。)を策定しました。令和5(2023)年1月には、行動計画が更新・改定され、次世代の担い手となる新規就業者の確保・育成の強化の対象を福島県に加えて近隣県にも拡大する等の取組が追加されたところです。今後も、対策の進捗や地方公共団体・関係団体等の意見も踏まえつつ、随時、対策の追加・見直しを行っていくこととしています。
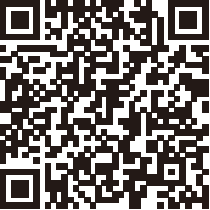
〈ALPS処理水の海洋放出に伴う風評被害の抑制等のため300億円及び500億円の基金を措置〉
当面の対策の取りまとめには、ALPS処理水の海洋放出に伴う風評影響を最大限抑制しつつ、仮に風評影響が生じた場合にも、水産物の需要減少への対応を機動的・効率的に実施することにより、漁業者の方々が安心して漁業を続けていくことができるよう、基金等により、全国的に弾力的な執行が可能となる仕組みを構築することを盛り込んでおり、ALPS処理水の海洋放出に伴う需要対策として「多核種除去設備等処理水風評影響対策事業」を行うため、経済産業省において令和3(2021)年度補正予算により基金造成のために300億円が措置されました。
また、「ALPS処理水の海洋放出に伴う影響を乗り越えるための漁業者支援事業」を行うため、経済産業省において令和4(2022)年度第2次補正予算により基金造成のために500億円が措置されました。
〈令和4(2022)年6月からトリチウムを対象とする水産物のモニタリングを実施〉
水産庁は、ALPS処理水の海洋放出に当たり、消費者等の安心の回復と信頼の確保につなげるため、令和4(2022)年6月から新たにトリチウムを対象とする水産物のモニタリング分析を開始しました。ALPS処理水に係るトリチウム等の分析も放射性セシウムの分析と同様の手法により、IAEAとの共同事業の一環として試料採取、分析、比較評価が実施されています。
〈ALPS処理水の海洋放出の決定〉
ALPS処理水の海洋放出に先立ち、令和5(2023)年8月22日、「第6回廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議」及び「第6回ALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等会議」の合同会議において行動計画が更新・改定され、科学的根拠のない輸入規制措置等への対策が追加されるとともに、「『東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針』の実行と今後の取組について」が決定され、さらにALPS処理水の具体的な海洋放出時期を同月24日とする見込みが示されました。
コラムトリチウムについて
〈トリチウムとは〉
トリチウムは水素の一種で、非常に弱い放射線を放出します。トリチウムは原子力発電所の稼働や核実験で生成されるほか、宇宙線の影響によって自然条件下でも生成されます。酸素とトリチウムが結びついた「トリチウム水」は、地球上のあらゆる水の中に普通に存在し、私たちのからだを構成する水分にも数十Bqのトリチウムが存在しています。
〈人体への影響について〉
放射線には、「α(アルファ)線」、「β(ベータ)線」、「γ(ガンマ)線」、「中性子線」などの種類があります。このうち「トリチウム」が放出するβ線が持つエネルギーは極めて弱く、紙1枚や皮膚で遮られるため、人体への影響は体内に取り込んだ場合に限られます。
水や食物を通じてトリチウムを体内に取り込んだ場合でも、人体や魚介類に与える影響は極めて小さく、濃縮もされず最終的に体外に排出されます。
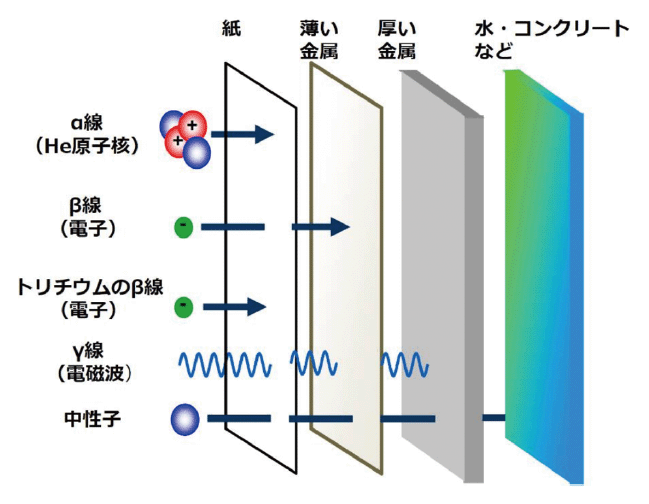
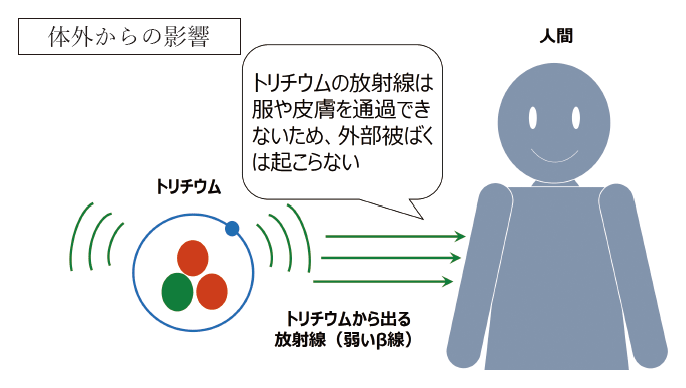
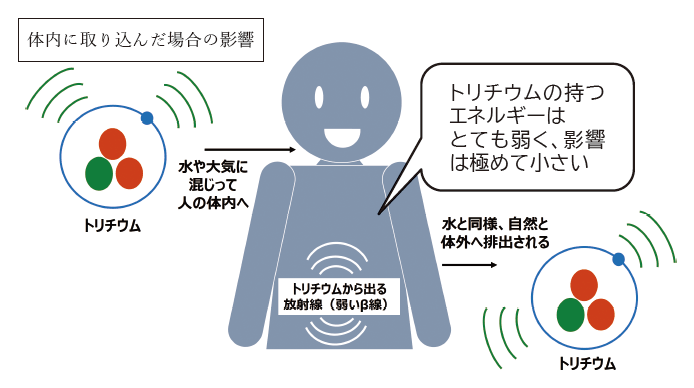
〈放出されるALPS処理水の安全性について〉
ALPS処理水は、トリチウム濃度を1L当たり1500Bq未満になるまで海水で薄めてから放出されます。これは、世界保健機構(WHO)の飲料水水質ガイドラインの約7分の1です。また、トリチウムの年間放出量をできるだけ小さくするように、毎年計画を見直すこととしています。
トリチウムは海外の原子力発電所などでも生成され、海洋や河川などへ放出されています。
ALPS処理水によって放出されるトリチウムの年間総量は、海外の多くの原子力発電所等からの放出量と比べても、非常に低い水準となっています。
イ ALPS処理水の海洋放出とその影響
〈中国等が日本産水産物の輸入を停止〉
令和5(2023)年8月24日のALPS処理水の海洋放出開始を受け、米国は、日本の安全で透明性のある科学に基づいたALPS処理水の海洋放出のプロセスに満足しているとの声明を、EUは、ALPS処理水の海洋放出に対する日本のアプローチが国際的な原子力安全基準及び放射性物質に関する基準の最高水準に合致していると評価したIAEAが令和5(2023)年7月4日に発表した包括的な報告書を歓迎するとの声明を発出しました。
一方、従来の原発事故に伴う輸入規制に加えて、中国及びロシアは全都道府県の水産物を輸入停止としたほか、香港及びマカオは10都県*1の水産物等を輸入停止としました(図表5-11)。
我が国では、政府一丸となって、日中首脳会談等の二国間での会議の場や、ASEAN+3農林水産大臣会合や世界貿易機関(WTO)等の国際的な議論の場において、科学的根拠に基づかない規制の即時撤廃に向けた働きかけを行っています。
- 福島県、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県及び長野県。
図表5-11 ALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国・地域の食品等の輸入停止の概要(令和6(2024)年1月時点)
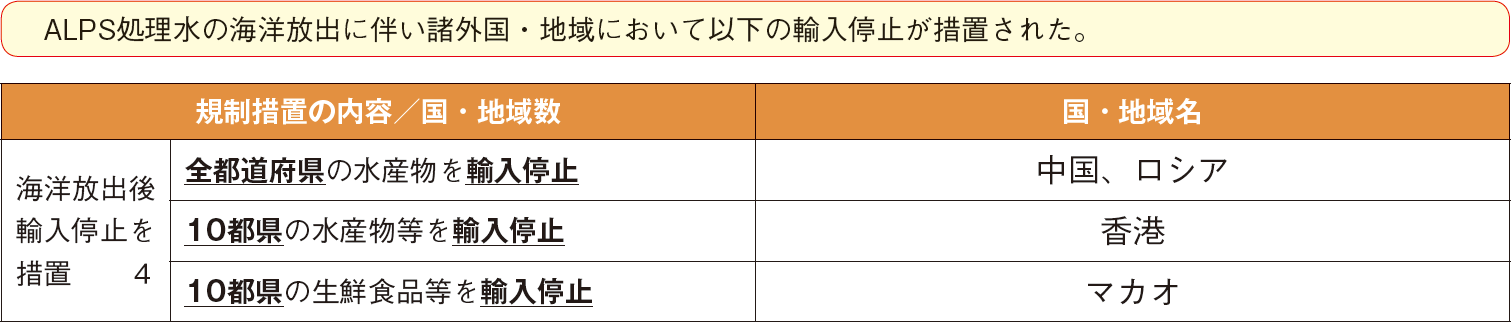
- この他、タイにおいて日本産水産物に対する輸入時の検査が強化されている。
〈トリチウムの迅速分析により分析結果を迅速に公表〉
ALPS処理水の海洋放出に当たり、水産庁は、令和4(2022)年6月から行っているトリチウムを対象とする水産物のモニタリング分析(精密分析)に加え、令和5(2023)年8月から、短時間でトリチウムの分析が行える手法(迅速分析)を導入し、ALPS処理水の放出口の北北東約4km及び放出口の南南東約5kmで採取した魚類について、採取日から翌々日までに分析結果を公表しています(図表5-12)。
精密分析は、令和4(2022)年6月から令和6(2024)年3月末までの間、420検体の水産物の分析を実施し、その分析結果は検出限界値(最大で0.408Bq/kg)未満で、放出前後で変化はありませんでした。
また、迅速分析については、令和5(2023)年8月から令和6(2024)年3月末までの間、174検体の水産物の分析を実施し、その分析結果は検出限界値未満となっており、精密分析と同様に放出前後で変化はなく、海洋放出が問題なく行われていることが裏付けられています。
図表5-12 水産物の放射性物質モニタリングの検体採取地点(トリチウム)
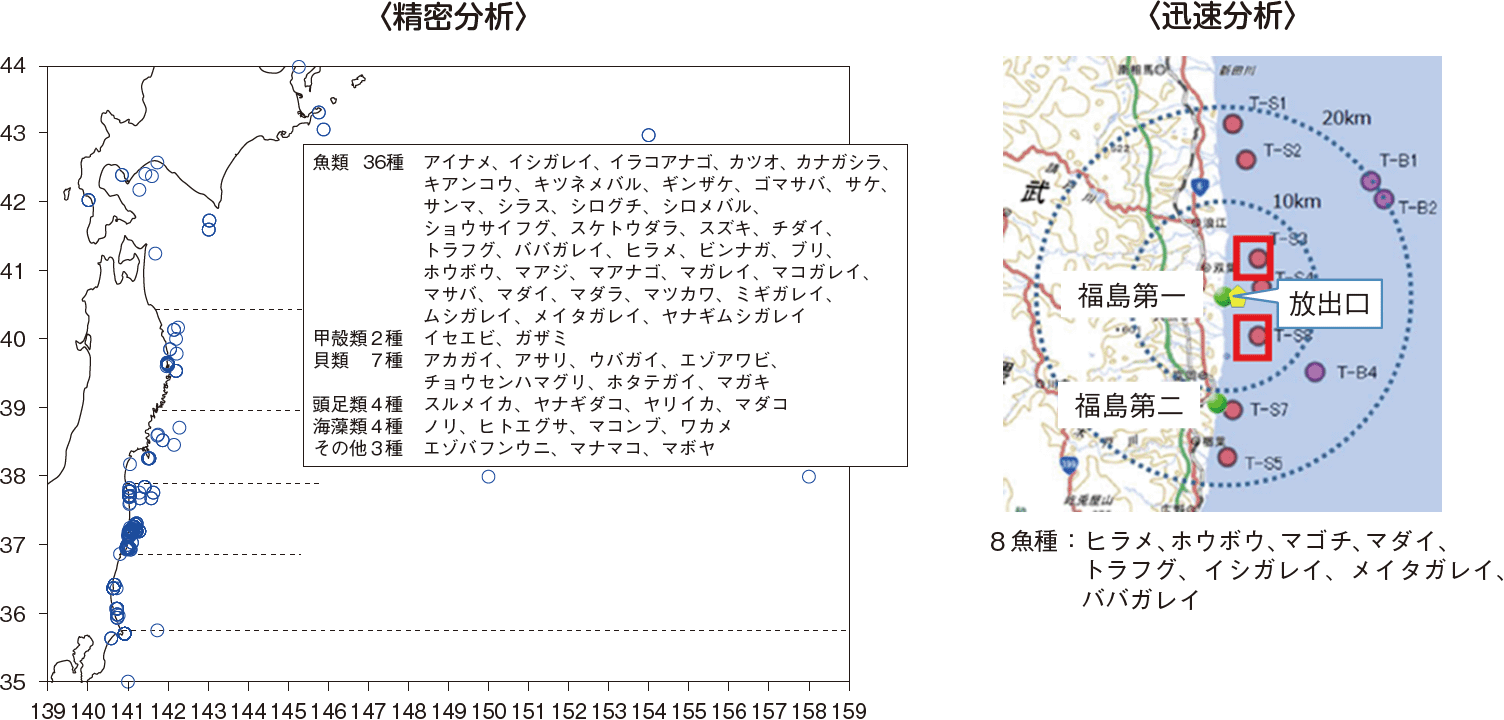
〈中国への水産物輸出が減少〉
令和4(2022)年の我が国の水産物輸出額の割合を国別に見ると、中国が22.5%と最も高く、次いで香港が19.5%となっています。また、マカオは0.5%、ロシアは0.1%であり、ALPS処理水の海洋放出開始に伴い我が国水産物の輸入規制を行った4か国・地域の水産物輸出額総額に占める割合は4割を超えています。
品目別に見ると、ホタテガイ、ナマコ調整品及びホタテガイ調整品においてはこれらの国・地域の占める割合は5割を超え、カツオ・マグロ類においては35%を超えています(図表5-13)。
このような中、令和5(2023)年7月の中国による輸入審査の厳格化を受け、同月から我が国から中国への水産物輸出に際し通関手続の所要日数の大幅な延長が一部発生し、同月の中国向け水産物の輸出額は対前年同月比で約23%減少しました。
その後、同年8月の中国による輸入規制の強化により、8月以降中国への輸出額が大幅に減少し、令和5(2023)年の中国への水産物輸出額は対前年で約30%減少しました。一方、香港への水産物輸出額は、真珠等の輸出の増加により約35%増加しました(図表5-14)。
図表5-13 令和4(2022)年の我が国の水産物の輸出先国・地域、主な輸出水産物の輸出先国・地域
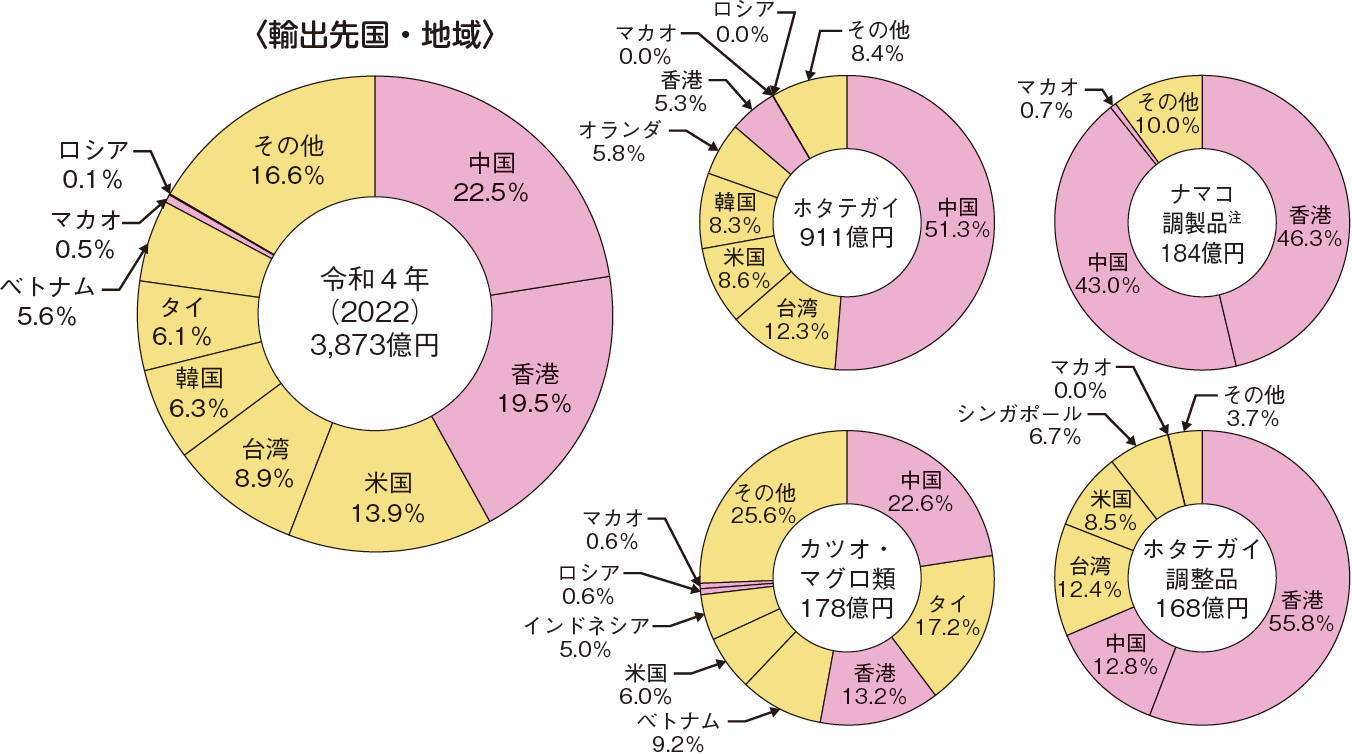
図表5-14 中国及び香港への水産物の輸出額の推移
〈国内における水産物等の動向〉
ALPS処理水の海洋放出以降、東京都中央卸売市場等の大規模消費地市場では国内の水産物価格は全体の傾向として大幅な下落は見受けられていません。一方、中国への輸出に依存していた一部の魚介類については、産地では価格の下落が見られており、特に中国での殻剥き加工等用に輸出していた北海道のホタテガイについては、加工業者等の在庫が滞留し、一部の産地で価格の下落が継続しているとの声もあります。このように、国内における全体的な風評影響は見受けられないものの、中国等の輸入規制による影響が見られています。
こうした状況の中、引き続き、影響を受ける水産物について、一層の消費拡大や輸出先の転換・多角化が必要となっています。
ウ 「水産業を守る」政策パッケージの実施等
〈「水産業を守る」政策パッケージの策定〉
令和5(2023)年9月4日、政府は、ALPS処理水の海洋放出開始以降の中国等の輸入規制強化を踏まえ、科学的根拠に基づかない措置の即時撤廃を求めていくとともに、全国の水産業支援に万全を期するため、既に措置された300億円及び500億円の基金による支援、東京電力による賠償等に加え、特定の国・地域への依存を分散するための207億円の緊急支援事業を創設し、1)国内消費拡大・生産持続対策、2)風評影響に対する内外での対応、3)輸出先の転換対策、4)国内加工体制の強化対策及び5)迅速かつ丁寧な賠償の5本柱からなる「水産業を守る」政策パッケージを示しました(図表5-15)。
また、令和5(2023)年11月には、補正予算により輸出拡大に必要なHACCP*1等対応の施設・機器整備、加工原材料の買取・一時保管、「地域の加工拠点」施設等を整備する事業等の支援が措置されました。
- Hazard Analysis and Critical Control Point:危害要因分析・重要管理点。原材料の受入れから最終製品に至るまでの工程ごとに、微生物による汚染や金属の混入等の食品の製造工程で発生するおそれのある危害要因をあらかじめ分析(HA)し、危害の防止につながる特に重要な工程を重要管理点(CCP)として継続的に監視・記録する工程管理システム。国際連合食糧農業機関(FAO)とWHOの合同機関である食品規格(コーデックス)委員会がガイドラインを策定して各国にその採用を推奨している。
図表5-15 「水産業を守る」政策パッケージの概要

〈国内消費拡大に向けた取組〉
中国等の輸入規制措置により影響を受ける水産物の国内の消費拡大に向けた対策として、学校給食・子ども食堂等への水産物の提供や、創意工夫による多様な販路拡大の取組への支援を行っています。また、補正予算においては、特に影響の大きいホタテガイやナマコについて、当該支援を積み増して支援しています。
また、消費者に向けた多様な媒体・方法によるALPS処理水に関する広報活動の実施や、公正な取引が行われるよう、流通事業者等に対する説明会等の実施への支援を行っており、例えば量販店等において、三陸・常磐産の水産物の魅力や安全性について発信するイベント等が行われました。農林水産省においても、SNS*1等を活用した消費拡大に向けた発信を行っており、例えば農林水産省公式X(旧Twitter)による「#食べるぜニッポン」の投稿は令和6(2024)年3月末時点で3,022万回以上の閲覧がありました。
くわえて、輸入停止等により影響を受ける産地水産物を返礼品とするふるさと納税への寄付の増加が見られていることや、駐日米国大使が在日駐留米軍向けに日本産水産物を購入する意向を明らかにするなど、輸入停止等により影響を受ける産地を応援する取組が見られています。また、北海道森町(もりまち)等の産地自治体が、全国の小中学校に対し影響を受けた北海道産のホタテガイを学校給食の食材として無償提供する取組を行うなど、各地で消費拡大の取組が行われています。
- Social Networking Service:登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービス。
〈国内生産持続に向けた取組〉
輸入規制措置等により影響を受ける水産物の需要減少への対応として、漁業者団体等が行う販路拡大等の取組や水産物の一時的買取り・保管への支援を行うとともに、出荷が困難となった養殖水産物を養殖場に留め置くために追加的に必要な飼餌料費等の支援も措置しています。
また、ALPS処理水海洋放出の影響のある漁業者に対し、売上高向上や基本コスト削減により持続可能な漁業継続を実現するため、当該漁業者が創意工夫を凝らして取り組む新たな魚種・漁場の開拓等に係る漁具等の必要経費、燃油コスト削減や魚箱等コストの削減に向けた取組、省エネルギー性能に優れた機器の導入に要する費用に対して支援を行っています。
さらに、水産関係事業者への資金繰り支援として、株式会社日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金等について、対象要件の緩和や特別相談窓口の設置等を行うとともに、漁業信用基金協会の保証付き融資について、実質無担保・無保証人化措置を講じました。
〈輸出先転換に向けた取組〉
中国等の輸入規制措置を踏まえ、安定的な輸出を継続できるサプライチェーンを構築することが必要です。このため、輸入規制措置等により影響を受ける水産物の輸出先の転換に向けた対策として、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)においては、令和5(2023)年8月に特別相談窓口を設置し、輸入規制等に影響を受けた企業からの相談に対応しているほか、同年9月に「水産品等食品輸出支援にかかる緊急対策本部」を設置し、「水産業を守る」政策パッケージに基づき、海外見本市への出展やバイヤー招へい等による商談機会の組成、また、日本食品海外プロモーションセンターでは、海外の要人が参加する国際会議等での水産物のプロモーションイベント、海外の飲食・小売店等と連携した水産物フェア等に取り組んでいます。
また、中国へ冷凍両貝で輸出されたホタテガイの一部は、中国でむき身に加工された後に米国向けに輸出されていることから、農林水産省は、JETRO等と連携しベトナム、メキシコ等で殻剥き加工を行い米国等へ輸出するルートの構築等を進めて、輸出先の多角化に取り組んでいます。
〈国内加工体制の強化に向けた取組〉
中国等による輸入規制強化を踏まえ、特定国・地域依存を分散し、国内外の販路拡大を行うため、例えば中国に殻剥き依存していたホタテガイについては、輸出先のニーズに合わせ、国内で殻を剥くことが重要です。このため、予備費において、加工作業員確保のための人件費の支援や加工能力強化に係る機器導入への支援に加え、補正予算においても、広く地域のホタテガイ加工に貢献し、欧米等海外への輸出拠点となる「地域の加工拠点」の整備費用を支援しています。
また、EUや米国等へ水産物を輸出するためには、水産加工施設等が輸出先国・地域から求められているHACCPの実施、施設基準の適合が必要であることから、HACCP等の要件に適合する施設や機器の整備や認定手続きを支援しています。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344