(2)東京電力福島第一原子力発電所事故の影響への対応
ア 水産物の放射性物質モニタリング
〈水産物の安全性確保のために放射性物質モニタリングを着実に実施〉
東日本大震災に伴って起きた東京電力福島第一原子力発電所(以下「東電福島第一原発」といいます。)の事故の後、消費者に届く水産物の安全性を確保するため、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、国、関係都道県、漁業関係団体が連携して水産物の計画的な放射性物質モニタリングを行っています。水産物のモニタリングは、区域ごとの主要魚種や、前年度に50Bq(ベクレル)/kgを超過した放射性セシウムが検出された魚種、出荷規制対象種を主な対象としており、生息域や漁期、近隣県におけるモニタリング結果等も考慮されています。モニタリング結果は公表され、基準値(100Bq/kg)を超過した種は、出荷自粛要請や出荷制限指示の対象となります(図表5-4)。
図表5-4 水産物の放射性物質モニタリングの枠組み
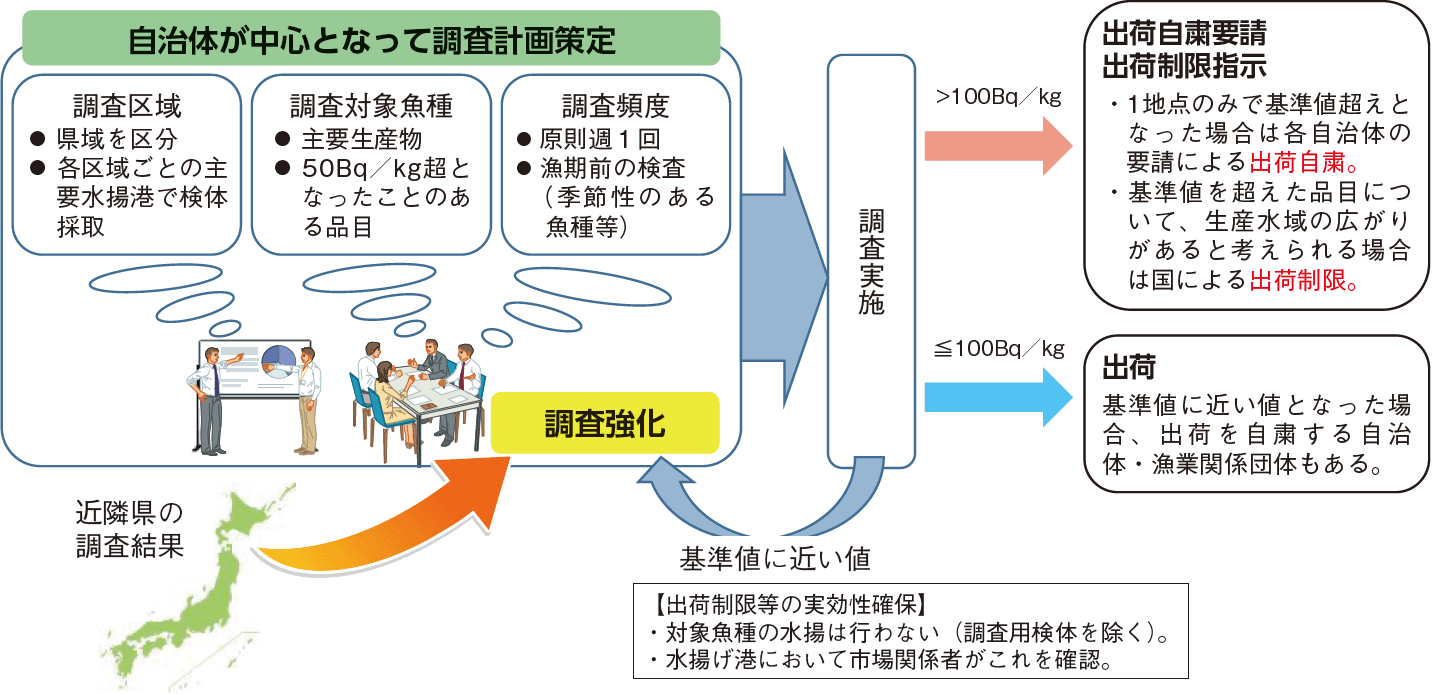
東電福島第一原発の事故以降、令和6(2024)年3月末までに、福島県及びその近隣県において、合計20万2,715検体の検査が行われてきました。基準値超の放射性セシウムが検出された検体(以下「基準値超過検体」といいます。)の数は、時間の経過とともに減少する傾向にあります。福島県における令和5(2023)年度の基準値超過検体は、ありませんでした。また、福島県以外においては、海産種では平成26(2014)年9月以降、淡水種では令和3(2021)年度以降、基準値超過検体はありませんでした(図表5-5)。
さらに、令和5(2023)年度に検査を行った水産物の検体は、全て検出限界値*1未満となりました。
- 分析機器が検知できる最低濃度であり、検体の重量や測定時間によって変化する。厚生労働省のマニュアル等に従い、基準値から十分低い数値になるよう設定。
図表5-5 水産物の放射性物質モニタリング結果(放射性セシウム)
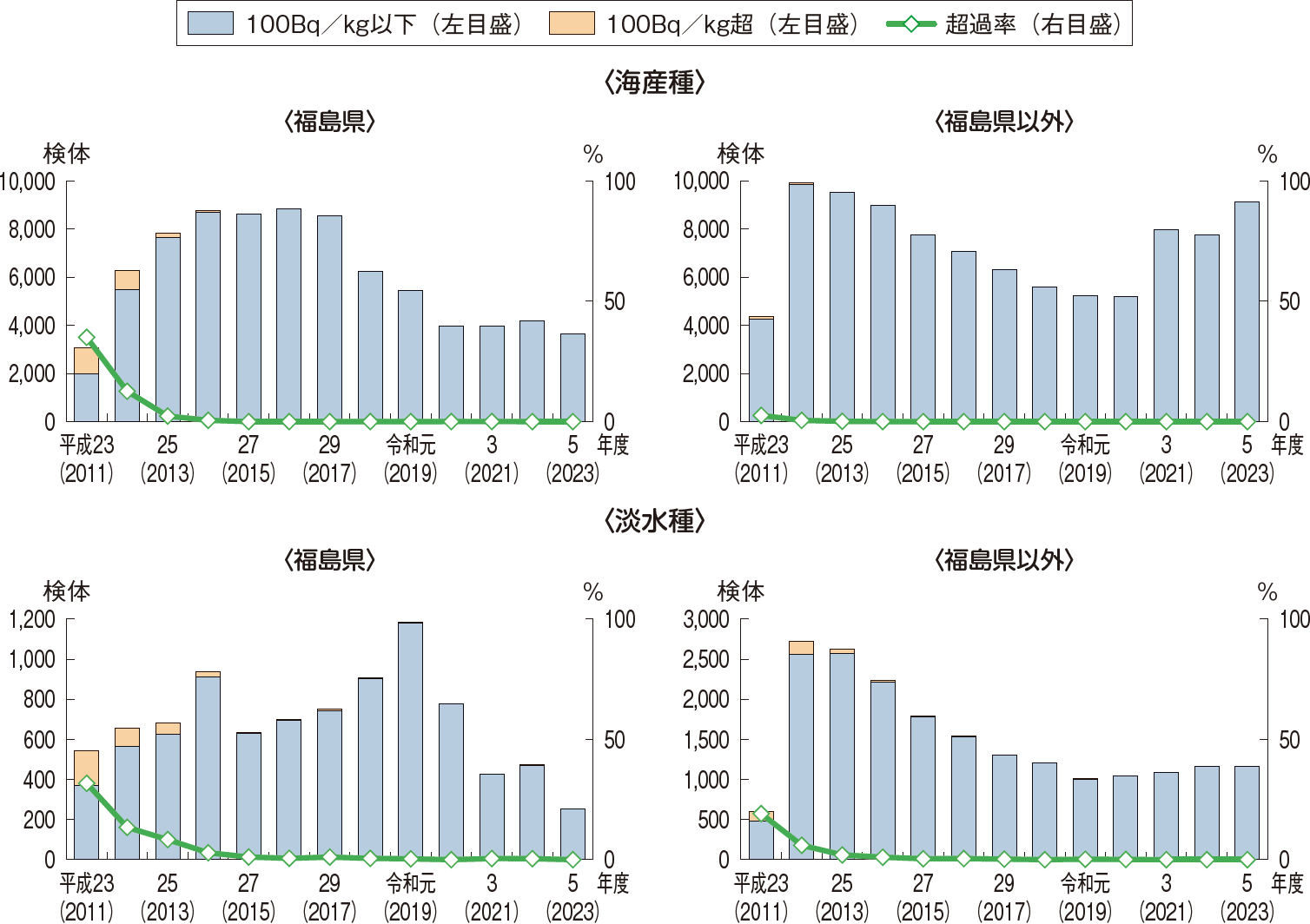

〈国際原子力機関と共同で実施した海洋モニタリングの報告書を公表〉
我が国は、国際原子力機関(IAEA)の支援により、平成26(2014)年度から海洋モニタリングデータの信頼性及び透明性の向上に取り組んでいます*1。令和4(2022)年11月に実施した共同での海洋モニタリングの報告書が令和5(2023)年12月にIAEAから公表され、「海域モニタリング計画に参加している日本の分析機関が引き続き高い正確性と能力を有している。」と評価されました。
また、IAEAでは、令和4(2022)年度から、東電福島第一原発におけるALPS処理水*2の取扱いに関する安全性レビューの一環として、日本の海域における水産物や海水のモニタリング結果の信頼性を裏付けるための取組を実施しています。令和4(2022)年11月に採取した試料の分析結果に関する報告書が令和6(2024)年1月にIAEAから公表され、「ALPS処理水に係るトリチウム分析などについて、日本の分析機関の試料採取方法は適切であり、かつ、海洋モニタリングの結果から、参加した日本の分析機関が高い正確性と能力を有している。」と評価されました。
令和5(2023)年度の共同海洋モニタリングでは、IAEA海洋環境研究所に加え、カナダ、中国及び韓国の分析機関が参加し、試料採取から前処理までの状況及び分析手順の確認が⾏われ、現在各機関で分析が行われているところです。
- 水産物については、平成27(2015)年度から実施
- 多核種除去設備(ALPS:Advanced Liquid Processing System)等によりトリチウム以外の核種について、環境放出の際の規制基準を満たすまで浄化処理した水。
イ 市場流通する水産物の安全性の確保
〈出荷制限等の状況〉
放射性物質モニタリングにおいて、基準値を超える放射性セシウムが検出された水産物については、国、関係都道県、漁業関係団体等の連携により流通を防止する措置が講じられているため、市場を流通する水産物の安全性は確保されています(図表5-6)
その上で、時間の経過による放射性物質濃度の低下により、検査結果が基準値を下回るようになった種については、順次出荷制限の解除が行われ、令和3(2021)年12月には、全ての海産種で出荷制限が解除されました。しかしながら、令和4(2022)年1月、福島県沖のクロソイ1検体で基準値超の放射性セシウムが検出され、同年2月に出荷制限が指示されました。
また、淡水種については、令和6(2024)年3月末時点で、5県(宮城県、福島県、栃木県、群馬県及び千葉県)の河川や湖沼の一部において、合計12種が出荷制限又は地方公共団体による出荷・採捕自粛措置の対象となっています。
図表5-6 出荷制限又は自主規制措置の実施・解除に至る一般的な流れ
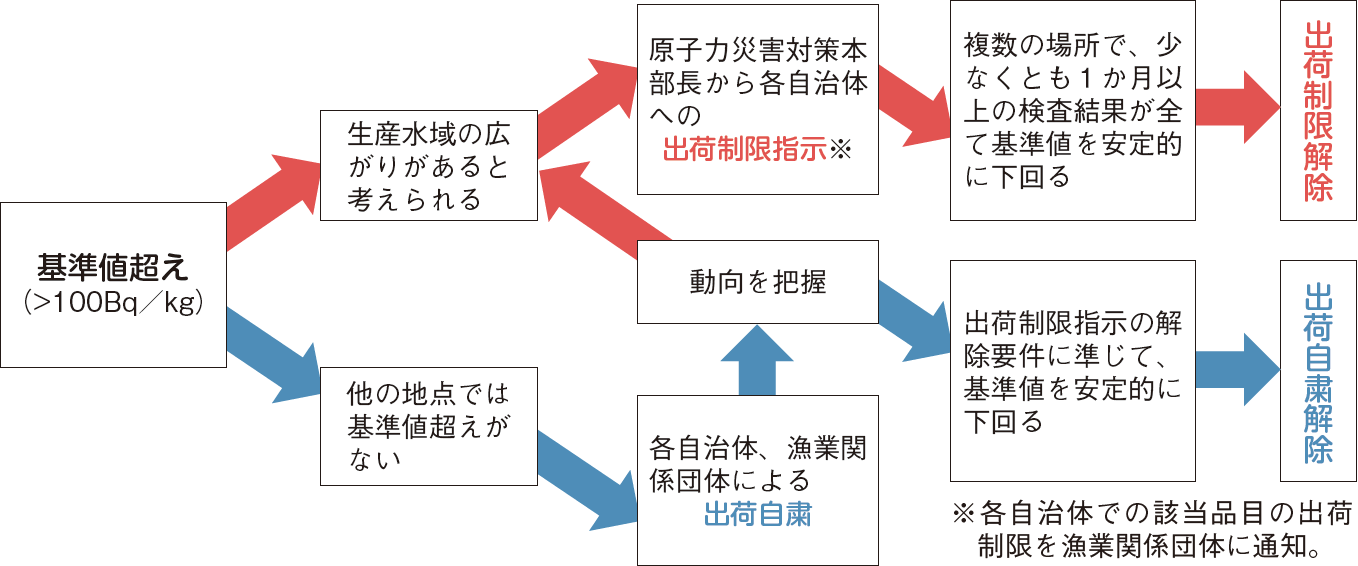
ウ 福島県沖での本格操業に向けた取組
〈試験操業から本格操業に向けた移行期間として水揚げの拡大に取り組む〉
福島県沖では、東電福島第一原発の事故の後、沿岸漁業及び底びき網漁業の操業が自粛され、漁業の本格再開に向けた基礎情報を得るため、平成24(2012)年から令和3(2021)年3月末まで、試験操業・販売(以下「試験操業」といいます。)が実施されました。
試験操業の対象魚種は、放射性物質モニタリングの結果等を踏まえ、漁業関係者、研究機関、行政機関等で構成される福島県地域漁業復興協議会での協議に基づき決定されてきたほか、試験操業の取組で漁獲される魚種及び加工品共に放射性物質の自主検査が行われるなど、市場に流通する福島県産水産物の安全性を確保するための慎重な取組が行われました。
試験操業の対象海域は、東電福島第一原発から半径10km圏内を除く福島県沖全域であり、試験操業への参加漁船数は、当初の6隻から試験操業が終了した令和3(2021)年3月末には延べ2,183隻となりました。水揚量については、令和2(2020)年から更なる水揚量の回復を目指し、 相馬(そうま)地区の沖合底びき網漁業で計画的に水揚量を増加させる取組等を行ってきました。平成24(2012)年に122tだった水揚量は、令和5(2023)年には6,530t(速報値)まで回復しています(図表5-7)。
この試験操業は、生産・流通体制の再構築や放射性物質検査の徹底等、福島県産水産物の安全・安心の確保に向けた県内漁業者をはじめとする関係者の取組の結果、令和3(2021)年3月末で終了し、同年4月からは操業の自主的制限を段階的に緩和し、地区や漁業種類ごとの課題を解決しつつ、震災前の水揚量や流通量へと回復することを目指しています。
福島県産水産物の販路を拡大するため、多くの取組やイベントが実施されています。福島県漁業協同組合連合会では、全国各地でイベントや福島県内で魚料理講習会を開催しています。このような取組を着実に行っていくことにより、福島県の本格的な漁業の再開につながっていくことが期待されます。
図表5-7 福島県の水揚量(沿岸漁業及び底びき網漁業)
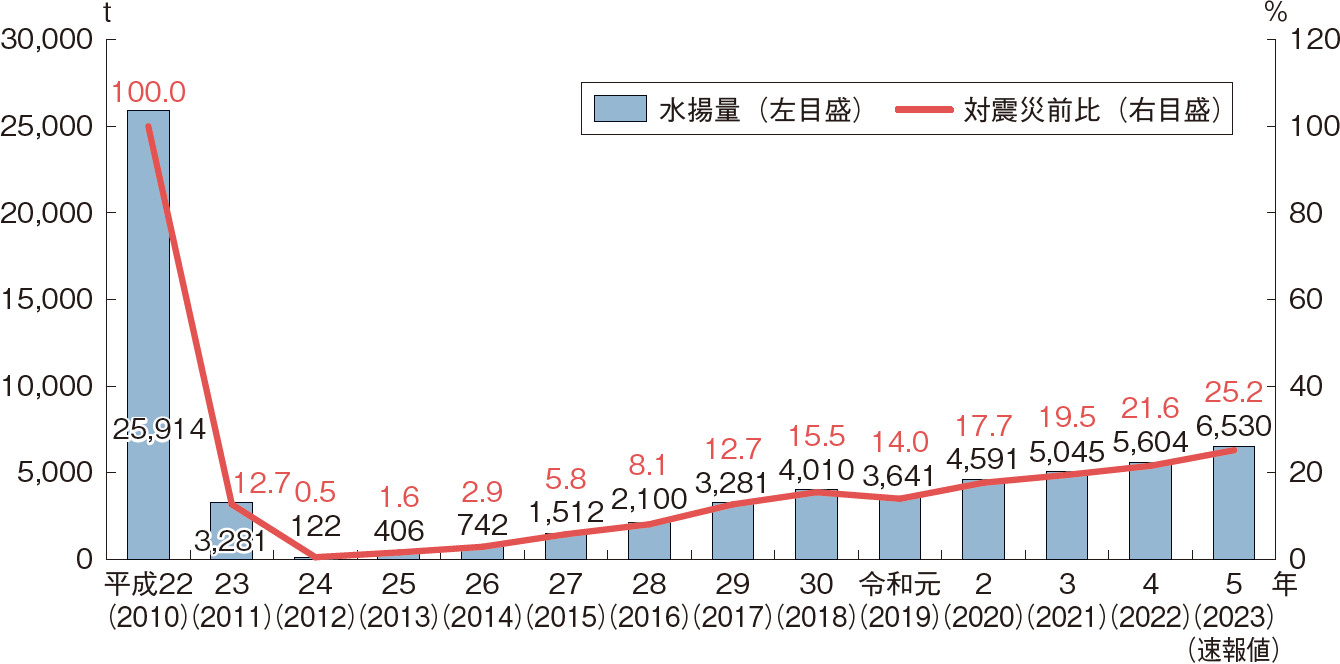
エ 東京電力福島第一原子力発電所事故による風評の払拭
〈最新の放射性物質モニタリングの結果や福島県産水産物の魅力等の情報発信〉
消費者庁が平成25(2013)年2月から実施している「風評に関する消費者意識の実態調査」によれば、「放射性物質を理由に福島県の食品の購入をためらう」と回答した消費者の割合は減少傾向にあり、令和6(2024)年2月の調査では、4.9%とこれまでの調査で最小となりました(図表5-8)。
図表5-8 「放射性物質を理由に福島県の食品の購入をためらう」と回答した消費者の割合
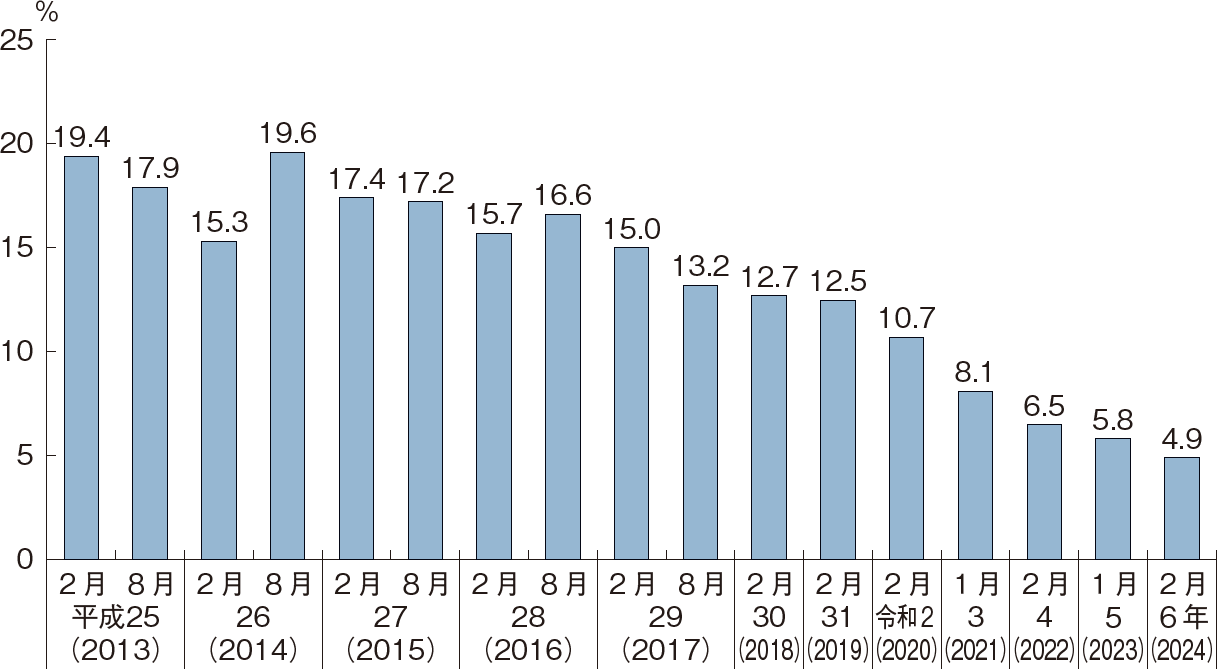
しかしながら、これまでも風評被害が発生してきていることに鑑み、対応していく必要があります。
風評被害を防ぎ、一日も早く復興を目指すため、水産庁は、最新の放射性物質モニタリングの結果や水産物と放射性物質に関するQ&A等をWebサイトで公表し、消費者、流通業者、国内外の報道機関等への説明会を行うなど、正確で分かりやすい情報提供に努めています。
また、被災地県産水産物の販路回復・風評払拭のため、大型量販店において福島県産水産物を「福島鮮魚便」として常設で販売し、専門の販売スタッフが安全・安心とおいしさをPRするとともに、水産物が確実に流通されるよう共同出荷による消費地市場への流通拡大の実証を支援しました。さらに、海外向けに我が国の情報を発信するWebサイトでの福島県を含む被災県産水産物の安全性と魅力をPRする活動等を行いました。これらの取組を通じ、消費者だけでなく、漁業関係者や流通関係者にも正確な情報や福島県産水産物の魅力等の発信を行い、風評の払拭に努めていきます。

〈令和5(2023)年に5か国・地域で輸入規制措置が撤廃〉
東電福島第一原発事故に伴い、55か国・地域において、⽇本産農林水産物・食品の輸入停止や放射性物質の検査証明書等の要求、検査の強化といった輸入規制措置が講じられました。これらの国・地域に対し、政府一体となってあらゆる機会を捉えて規制の撤廃に向けた粘り強い働き掛けを行ってきた結果、令和5(2023)年度にEU等で輸入規制措置が撤廃される等、規制を維持する国・地域は7にまで減少しました(図表5-9)。
図表5-9 原発事故に伴う諸外国・地域の食品等の輸入規制の概要(令和6(2024)年1月時点)
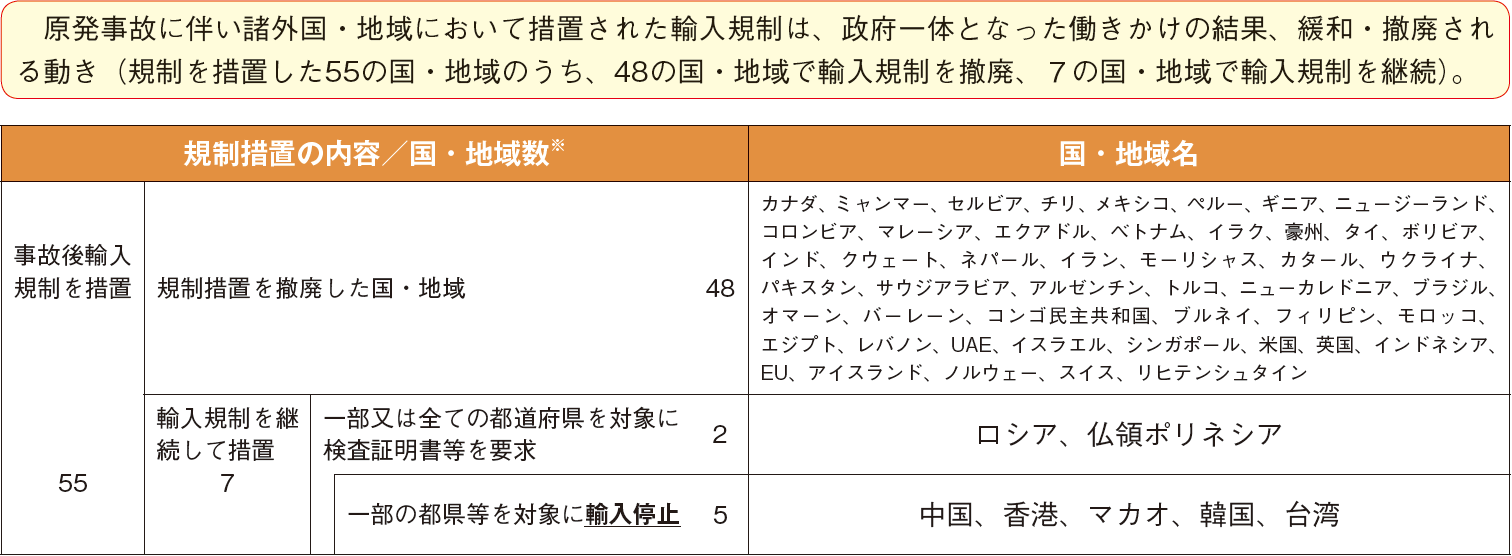
- 規制措置の内容に応じて分類。規制措置の対象となる都道府県や品目は国・地域によって異なる。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344







