(2)海業の推進のための今後の取組
〈海業の推進に向けて〉
漁村は、漁業をはじめとする水産業の拠点として重要な役割を果たしているとともに、自然環境の保全や国民の生命・財産の保全等の多面的機能を果たしています。しかしながら、人口減少や高齢化、漁獲量の低迷に伴う漁業所得の減少等による地域の活力の低下等厳しい状況に直面しています。
一方で、漁村は、食、体験、交流、自然環境等多くの魅力的な地域資源を有しており、このような地域資源に対しては都市住民やインバウンド等による高いニーズがあります。
これまで見てきた先行事例のように、各漁村の課題の解決に向け、既に地域が持つ地域資源等を活かして取り組まれている多くの事例があり、このような取組により、地域の所得向上と雇用機会の確保が期待されます。
今後、漁港漁場整備長期計画に成果目標として設定された、令和8(2026)年度までに漁港における新たな海業等の取組のおおむね500件の展開に向けて、各地で漁業者や漁協など漁業関係者が海業の取組を始められるよう、地方公共団体や民間企業等との連携の枠組みづくりや、子どもたちが海とふれあう機会を通じて、魚のおいしさや水産業の仕組みを学び、体験する機会の創出、多くの人々に海業が浸透するよう世界にも通じる海業のコンセプトや魅力の国内外への発信、国や世代等によって異なる多様化した消費者ニーズへの対応など、海業の普及啓発の取組を推進していく必要があります。
〈海業の推進に向け漁港漁場整備法等を改正〉
水産基本計画等を踏まえ、漁業上の利用に支障を与えないことを前提に、漁港の有する価値や魅力を活かし、海業を推進し、水産物の消費増進や交流人口の拡大を図るとともに、漁港において陸上養殖の展開等の漁港機能の強化を図るため、令和5(2023)年5月に改正法が成立しました。
同法では、漁港漁場整備法*1の法目的に漁港の活用促進が追加され、法律名が「漁港漁場整備法」から「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に変更されたほか、漁業上の利用を確保した上で、漁港施設、水面等を活用した水産物の消費増進や交流促進に寄与する事業(漁港施設等活用事業)の推進に関する計画の策定や、当該計画が策定された漁港において、漁港管理者の認定を受けて漁港施設等活用事業を実施する者に対し、当該事業を安定的に実施するための新たな権利・地位として、1)行政財産である漁港施設の貸付け(最大30年)、2)漁港水面施設運営権(みなし物権、最大10年)の設定、3)水面等の長期占用(最大30年)が可能となりました。
また、同法の成立に併せ、同年12月には「漁港漁場整備事業の推進に関する基本方針」を改正し、漁港施設等活用事業についての記述の追加等を行いました。
今後は、漁港施設等活用事業を普及するなど、漁港を十分に活かした海業の取組を推進することとしています。
- 昭和25年法律第137号


〈遊漁者の安全確保等に向け遊漁船業の適正化に関する法律を改正〉
釣りによる海業の推進に当たり、遊漁船業の役割も重要です。特に遊漁船業は漁業との兼業割合が多く、漁業者にとって重要な兼業業種の一つとなっています。一方、遊漁船業において近年死傷事故が増加傾向にあることから、利用者の安全性の確保が課題となっています(図表特-3-1)。
このような中、これまでより更に安全に遊漁船で魚釣りができるよう、令和5(2023)年5月に、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律*1が成立*2し、遊漁船業の登録・更新制度の厳格化、遊漁船業者の安全管理体制の強化等により遊漁船業における安全性の向上を図ることとされました。
また、漁場や水産資源をめぐり遊漁と漁業との間の競合等によるトラブルがある中、遊漁が地域の水産業と調和のとれたものにしていくため、同法により、都道府県知事が地域の遊漁船業者や漁協等を構成員とする協議会を組織できる制度を創設し、この仕組みを活用して漁場の安定利用のためのルール作り等を推進していくこととしています。
- 令和5年法律第39号
- 令和6(2024)年4月施行
図表特-3-1 遊漁船業における死傷者数の推移
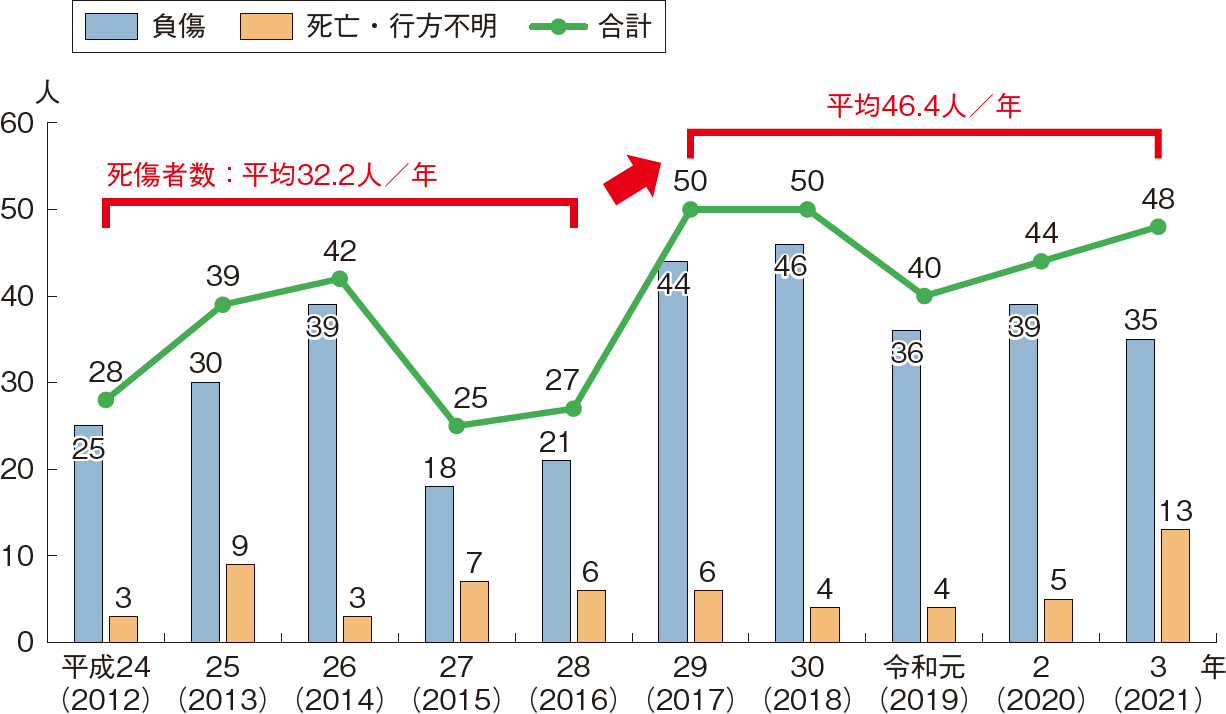
〈海業の推進に取り組む地区〉
海業を普及・推進するため、水産庁では、「海業の推進に取り組む地区」を募集し、応募のあった地区のうち、「『海業の推進に取り組む地区』公募要領」記載の内容に該当する54地区を、令和6(2024)年3月に「海業の推進に取り組む地区」として決定しました。
今後、必要に応じて、個別に助言や海業の推進に関する情報提供等を行うとともに、横展開を図る必要がある取組を中心に、各地区と連携して、実証的に新たな海業の取組計画策定に取り組んでいきます。
同地区のうち、同公募要領に記載の事例等、海業を普及・推進するに当たっての新たな知見として横展開を図る必要がある取組を中心に、「実証的に海業の計画策定に取り組む地区」を抽出し、水産庁において、同地区と連携し、現地調査や関係者による協議会の設置、運営等を通じて、実証的に新たな海業の取組計画策定を推進することとしています。

〈海業推進全国協議会の開催〉
水産庁は、令和5(2023)年12月、地方公共団体、漁協・漁業関係者、民間企業、民間団体等の海業に関心を持つ幅広い関係者の皆様を対象に、情報共有を図るとともに、優良な取組事例の発表等により海業への理解の促進と取組の普及、全国展開を推進するため、「海業推進全国協議会」を開催しました。同協議会では、地方公共団体、漁協、NPO*1法人及び民間企業の6名の講演者から取組事例の紹介等があり、465人が参加するなど関係者の関心の高さがうかがえました。
- NPO(Non Profit Organization):非営利団体
〈漁村における海業推進に向けた環境整備〉
海業の推進に当たり、漁村への来訪者にも安心して漁港を利用してもらえるよう、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等の大規模地震・津波や激甚化・頻発化する自然災害による甚大な被害に備えて、引き続き、漁港・漁村における事前の防災・減災対策や災害発生後の円滑な初動対応等を推進していく必要があります。このため、政府は、東日本大震災の被害状況等を踏まえ、防波堤と防潮堤による多重防護、粘り強い構造を持った防波堤や漁港から高台への避難経路の整備とともに、避難・安全情報伝達体制の構築等の避難対策を推進しています。
また、漁港施設、漁場の施設や漁業集落環境施設等のインフラは、老朽化が進行して修繕・更新すべき時期を迎えているものが多いことから、中長期的な視点から戦略的な維持管理・更新に取り組むため、予防保全型の老朽化対策等に転換し、ライフサイクルコストの縮減及び財政負担の平準化を実現していくことが必要となっています。
これらのことから、令和2(2020)年12月に閣議決定された「防災・減災、国土強靱(きょうじん)化のための5か年加速化対策」に基づき、甚大な被害が予測される地域等の漁港施設の耐震化・耐津波化・耐浪化等の対策や漁港施設の長寿命化対策、海岸保全施設の津波・高潮対策等を推進しています。
なお、漁村では、その多くは伝統文化を受け継ぎ、良好な自然環境を有していることから、地域特有の自然条件、社会条件等を活かしつつ、生活様式等に配慮した施設、良好な漁村の景観形成に資する施設等の整備を推進していくことが求められます。
また、狭い土地に家屋が密集している漁村では、自動車が通れないような狭い道路もあり、汚水処理人口普及率も低く、生活基盤の整備が立ち後れています。生活環境の改善は、若者や女性の地域への定着を図るだけでなく、漁村への来訪者向けにも重要です。このような状況を踏まえ、農林水産省は、漁業の生産性向上や漁村生活を支える集落道の整備、漁業集落排水施設の整備や広域化・共同化等を推進しています。
さらには、漁港施設や用地の再編・整除や、地域水産物普及施設、漁業体験施設のほか、漁船以外の船舶の簡易な係留施設、陸上保管施設等の整備を推進することで、漁村・漁港において、海業に取り組みやすくするための環境づくりを行っています。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344




