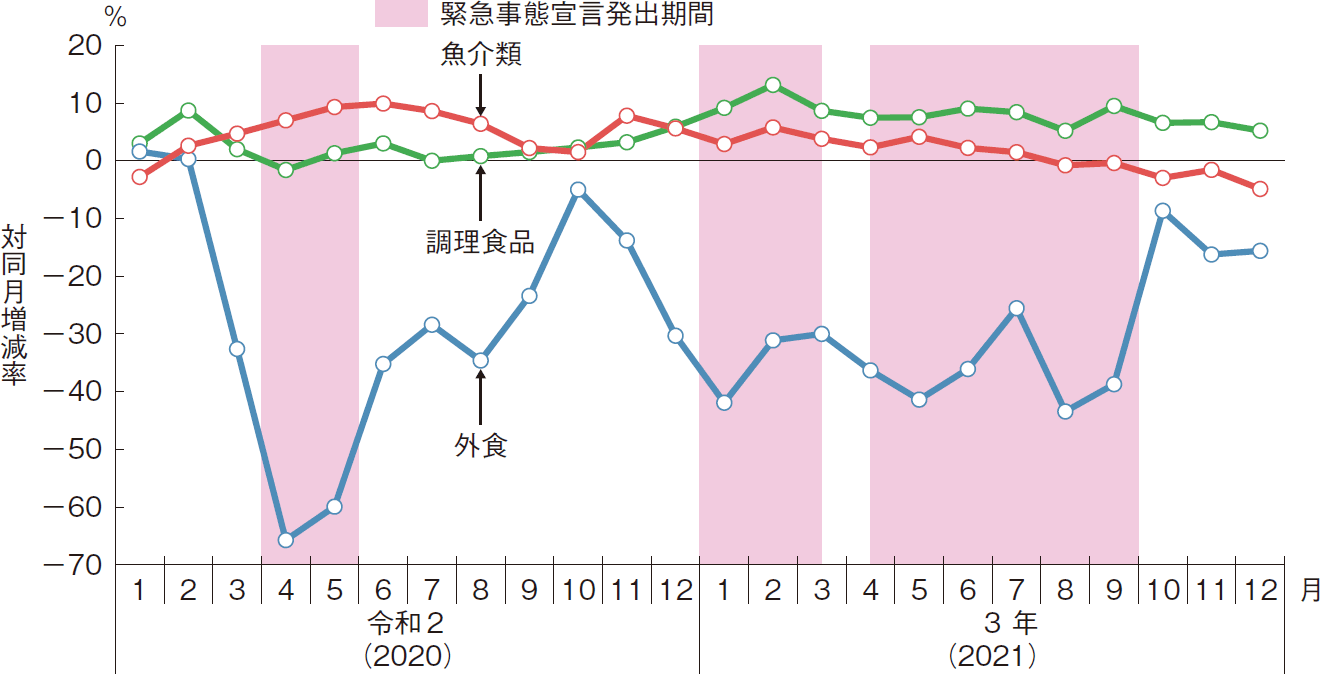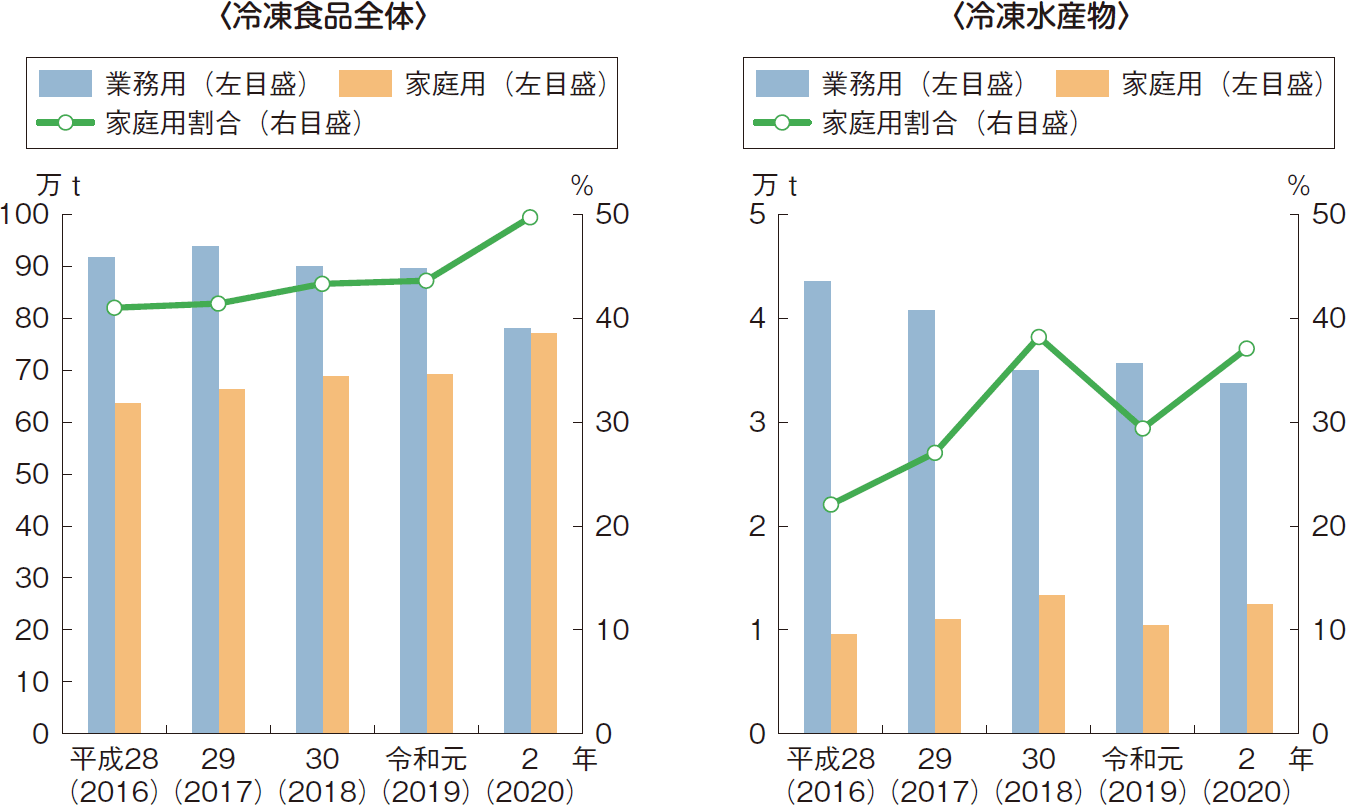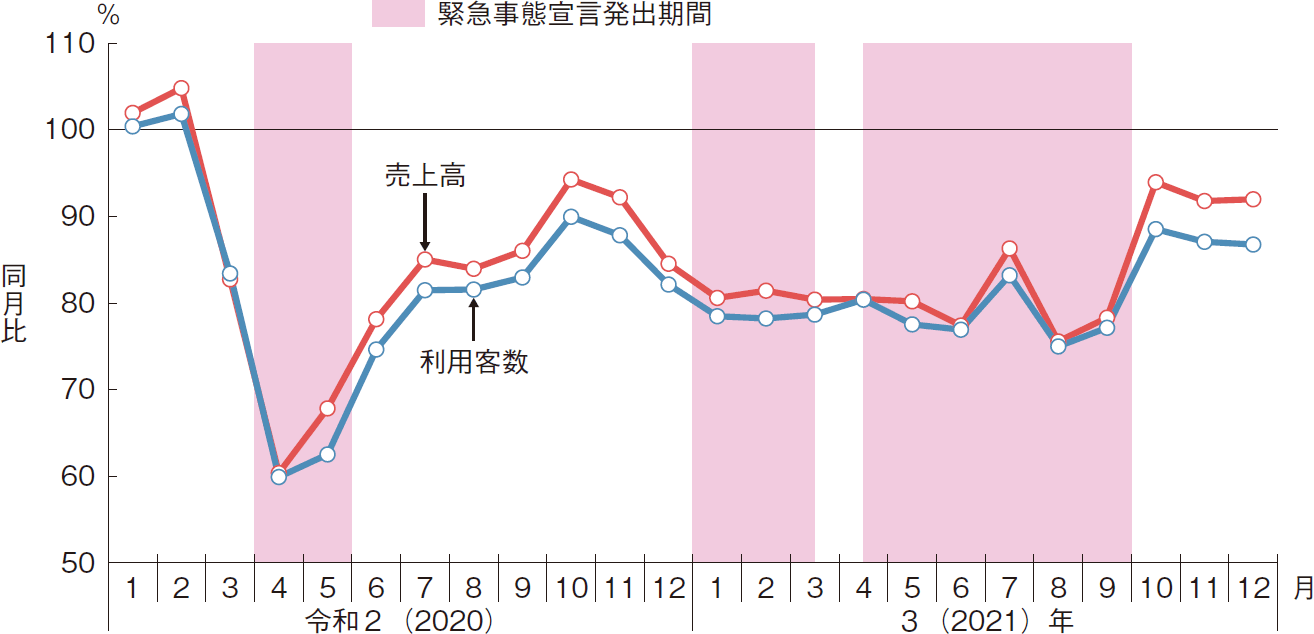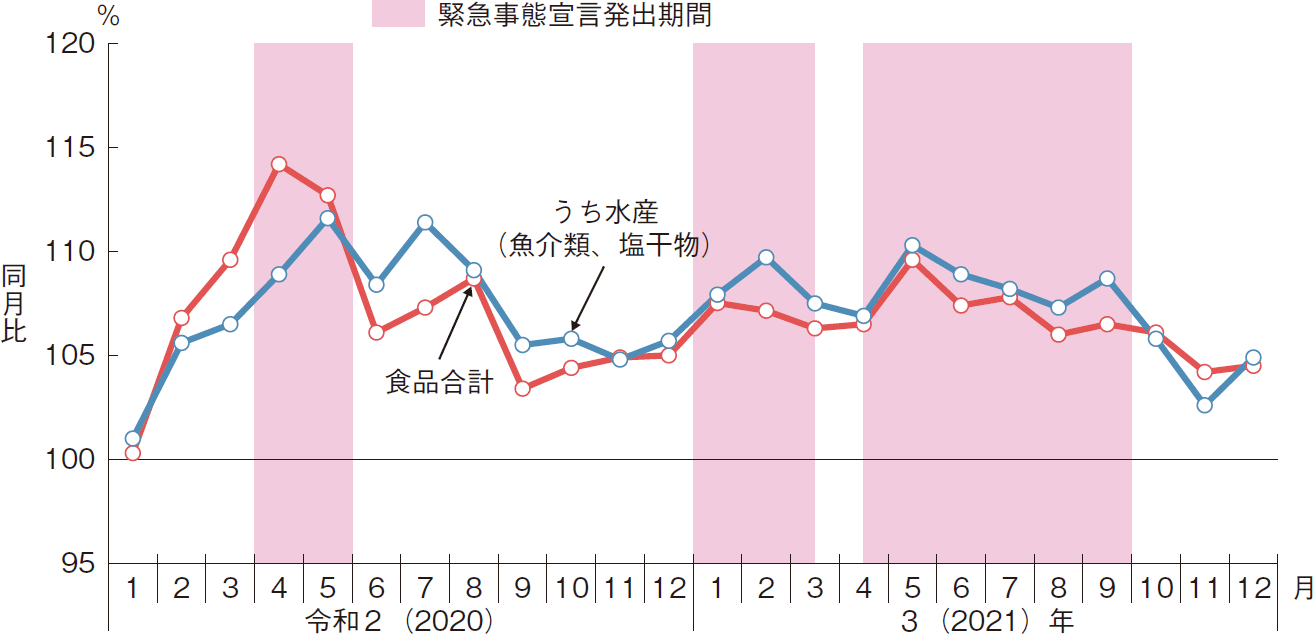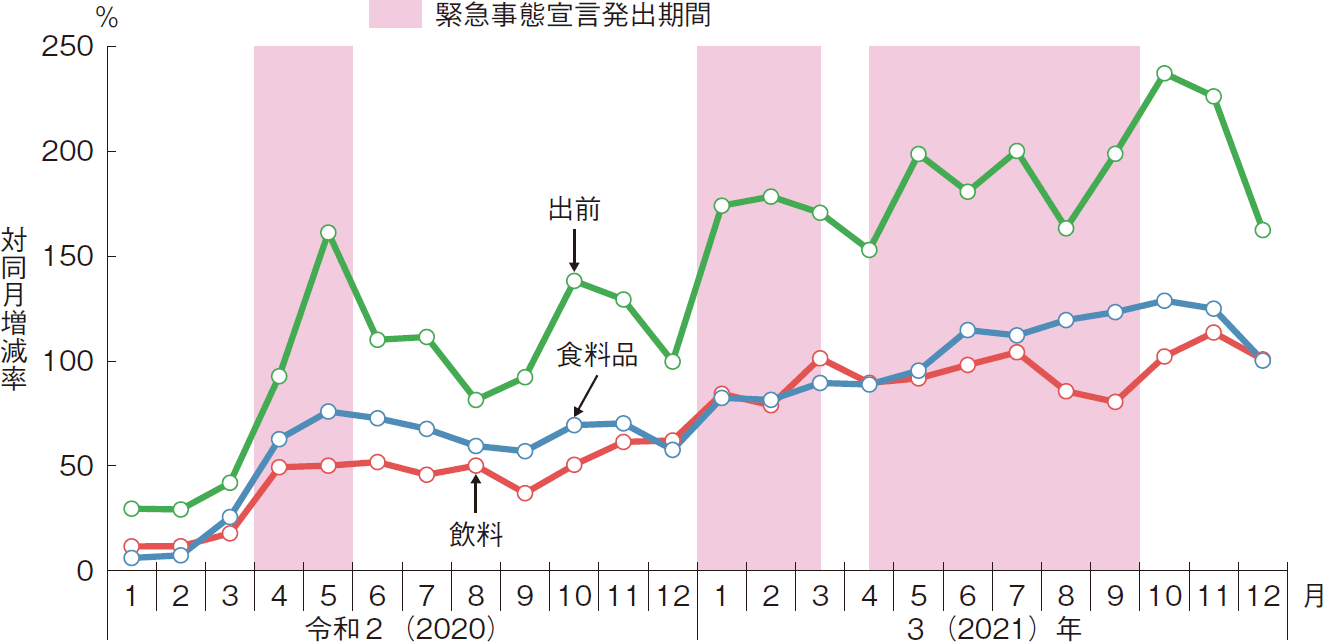(1)水産物需要における影響と新たな動き
〈自宅での食事・料理機会が増加し、家計の消費支出額は外食で大きく減少〉
令和2(2020)年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、3月以降、外食の利用が大きく減少し、その後緊急事態宣言*1等の状況により、大きく増減しました。他方、家での食事(内食)が増加し、1世帯当たりの魚介類の購入額が増加しました(図表特-2-1)。令和3(2021)年にも同様の傾向が見られましたが、同年8月以降は魚介類の購入額が令和元(2019)年を下回った一方、調理食品は令和元(2019)年を上回って推移しました。
農林水産省が令和2(2020)年12月に実施した調査では、自宅で食事する回数が増えたと回答した人は4割弱、料理する回数が増えたと回答した人は3割弱となり、自宅内での食事や料理機会が増加したことがうかがえます(図表特-2-2)。
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24(2012)年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言
図表特-2-1 外食、調理食品及び魚介類の1世帯当たり月別支出金額の対令和元(2019)年同月増減率
図表特-2-2 自宅における食事及び料理の頻度
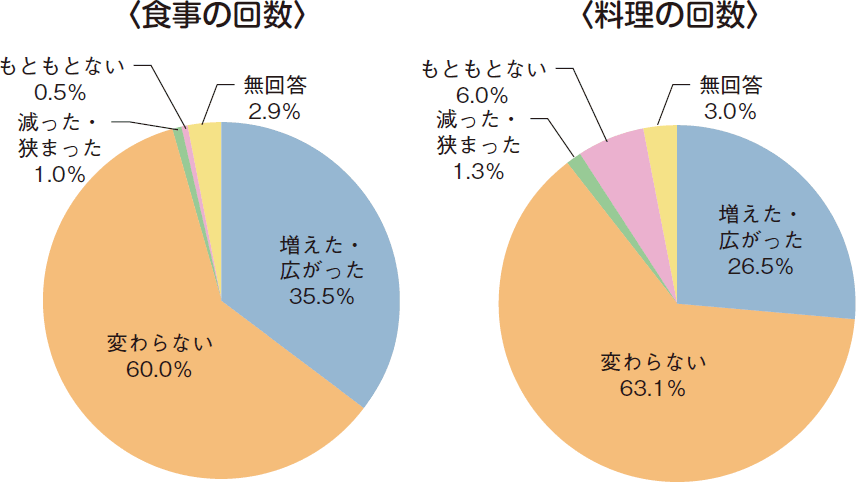
〈買い置きができ、調理が手軽で便利な家庭用冷凍食品の需要が増加〉
一般社団法人日本冷凍食品協会が令和3(2021)年2月に実施した「“冷凍食品の利用状況”実態調査」によると、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、買い物に行く回数が減ったと回答する女性が約4割を占め、男女共に1回の買い物の購入量が増えたと回答した割合及び買い置きができる食品の購入が増えたと回答した割合が大きくなっています(図表特-2-3)。
また、在宅勤務時の食事に最も求めるものとしては、男女共に「手軽・便利」が約4割を占め、次いで「おいしさ」となっています(図表特-2-4)。
図表特-2-3 食材の買い物方法や内容の変化
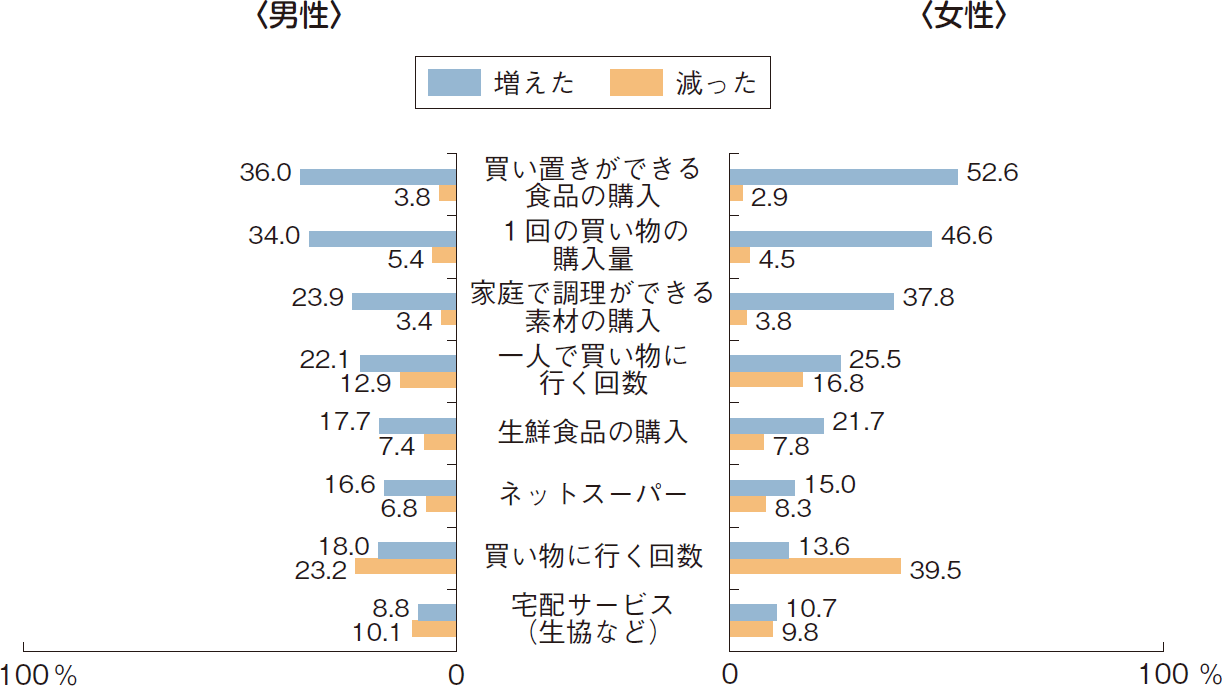
図表特-2-4 在宅勤務時の食事に最も求めること
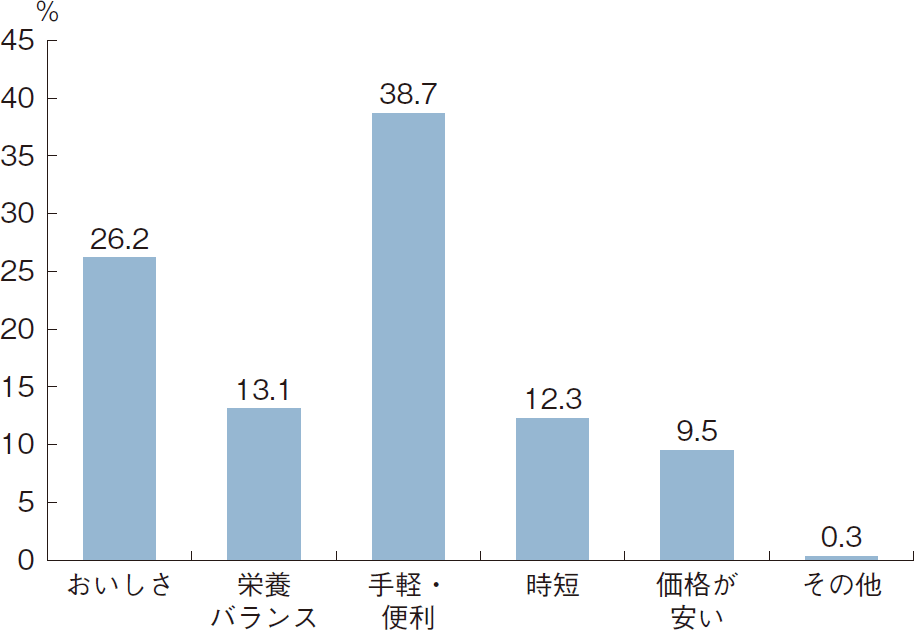
このようないわゆる巣ごもり需要の高まりから、家庭用冷凍食品の需要が増加し、令和2(2020)年の家庭用冷凍食品の生産量は前年から7.9万t(11.4%)増加しました。水産物の家庭用冷凍食品の生産量も令和元(2019)年から0.2万t(19.4%)増加しており、過去5年間でも高水準の生産量を示しています。他方、業務用冷凍食品の生産量は減少し、冷凍食品全体で11.6万t(13.0%)、水産物で0.2万t(5.4%)とそれぞれ減少しています(図表特-2-5)。
図表特-2-5 冷凍食品の生産量の推移
事例需要の高まるおいしい冷凍食品の製造をリキッドフリーザーで後押し(株式会社テクニカン)
(株)テクニカンは、水産物や畜産物、その他の食品を、液体を用いて凍結するリキッドフリーザー「凍眠(とうみん)」等を製造・販売するメーカーです。
凍眠は、食品を-30℃で急速に液体凍結することで、細胞を壊さず冷凍でき、解凍時にドリップが流れ出ることがほとんどなく、産地の鮮度のまま長期保管することを可能にしています。この凍眠は様々な食品加工業者や飲食店で使用されており、国内外で高い評価を得ています。
そのような中、同社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による巣ごもり需要の高まりに伴い、冷凍食品の需要が伸びていることを受け、飲食店で提供する料理や鮮度が求められる食品を家庭で気軽に味わえるよう、令和3(2021)年2月に冷凍食品専門店「TŌMIN FROZEN」(トーミン・フローズン)をオープンしました。地元の魚介類の刺身や有名店の魚料理等、凍眠を導入した食品加工業者や飲食店が製造した冷凍食品を取り扱い、売上げを伸ばしています。
そのほか、大手コンビニエンスストアチェーンが凍眠で凍結した刺身を同チェーン店舗で販売するなど、消費者の需要の変化に対応した冷凍水産加工品等を開発・販売する取組が広がっています。
〈外食産業の売上高が大きく減少〉
一般社団法人日本フードサービス協会の「外食産業市場動向調査」によると、令和2(2020)~3(2021)年の外食の売上高及び利用客数の令和元(2019)年同月比は、令和2(2020)年4月に最小の60%となり、その後も令和2(2020)~3(2021)年のいずれの月も令和元(2019)年の同月を下回って推移しました(図表特-2-6)。これは、国内の需要だけでなく、訪日外国人旅行者等のインバウンド需要が落ち込んだことも影響していると考えられます。
図表特-2-6 外食市場の全体の売上高及び利用客数の令和元(2019)年同月比
〈スーパーマーケットでの水産物の売上高が増加〉
内食の機会が増加したことにより、外食を代替するものとして、スーパーマーケット等の小売店やWebサイトでの購入のほか、宅配サービスや外食店からの持ち帰り(テイクアウト)の利用も拡大しました。一般社団法人全国スーパーマーケット協会等の「スーパーマーケット販売統計調査」によると、令和2(2020)~3(2021)年のスーパーマーケットの水産(魚介類、塩干物)の売上高の令和元(2019)年同月比は、令和2(2020)年5月に最大の112%となり、令和2(2020)~3(2021)年のいずれの月も令和元(2019)年の同月を上回って推移しました(図表特-2-7)。
図表特-2-7 スーパーマーケットの売上高(食品、水産)の令和元(2019)年同月比
〈インターネットを利用した販売での食料消費が増加〉
令和2(2020)年4月以降には、インターネットを利用した販売での食料支出額の大きな伸びが見られ、増加傾向で推移しました。特に出前への支出が増加し、同年5月には令和元(2019)年同月と比較して161%、令和3(2021)年10月には237%の増加が見られました。食料品や飲料への支出も同様に増加しており、令和2(2020)~3(2021)年のいずれの月も令和元(2019)年の同月を上回っています(図表特-2-8)。
図表特-2-8 インターネットを利用した販売での食料支出額の対令和元(2019)年同月増減率
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
FAX番号:03-3501-5097