(3)消費者への情報提供や知的財産保護のための取組
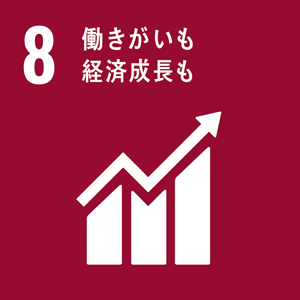
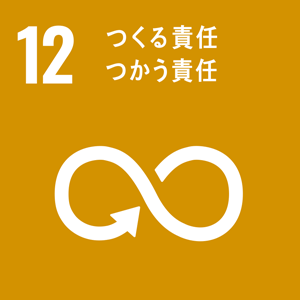

ア 水産物に関する食品表示
〈貝類の原産地表示を厳格化〉
消費者が店頭で食品を選択する際、安全・安心、品質等の判断材料の一つとなるのが、食品の名称、原産地、原材料、消費期限等の情報を提供する食品表示であり、食品の選択を確保する上で重要な役割を担っています。水産物を含む食品の表示は、平成27(2015)年より食品表示法*1の下で包括的・一元的に行われています。
食品表示のうち、加工食品の原料原産地表示については、平成29(2017)年9月に同法に基づく食品表示基準が改正され、輸入品以外の全ての加工食品について、製品に占める重量割合上位1位の原材料が原料原産地表示の対象となっています*2。さらに、国民食であるおにぎりのノリについては、重量割合としては低いものの、ノリの生産者の意向が強かったこと、消費者が商品を選ぶ上で重要な情報と考えられること、表示の実行可能性が認められたこと等から、表示義務の対象とされています。
また、水産物の原産地表示については、1)国産品にあっては水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名)、2)輸入品にあっては原産国名、3)2か所以上の養殖場で養殖した場合は主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所)が属する都道府県名*3となっています。このようなルールが適用されている中、農林水産省は、広域小売店におけるアサリの産地表示の実態に関する調査において、漁獲量を大幅に上回る量の熊本県産アサリが販売されていることが推測され、科学的分析により、買い上げた熊本県産アサリのほとんどが「外国産あさりが混入している可能性が高い」と判定された結果を令和4(2022)年2月に公表しました。
また、同調査結果の公表等を背景としたアサリの産地表示の現状を確認するための調査を行った結果、熊本県産と表示されたアサリの販売は確認されず、中国産と表示されたアサリの販売割合が全体の7割に達したこと及びアサリを販売する店舗の割合が低下していることを同年3月に公表しました。
このため、アサリの産地表示適正化のための対策として、消費者庁は、同年3月に食品表示基準Q&Aを改正し、出荷調整用その他の目的のため、貝類を短期間一定の場所に保存することを「蓄養」とした上で、蓄養が上記3)の期間の算定に含まれないことを明確化したほか、輸入したアサリの原産地は、蓄養の有無にかかわらず輸出国となること等のルールの適用の厳格化を行いました*4。
これらのアサリの産地表示適正化のための対策の効果を測るため、農林水産省は、アサリの産地表示の状況に関する調査を行い、国産アサリの原産地別出回り状況や輸入数量の動向に乖離(かいり) がない状況等を同年7月に公表しました。
- 平成25年法律第70号
- 消費者への啓発及び事業者の表示切替えの準備のための経過措置期間は、令和4(2022)年3月31日で終了。
- ただし、サケ・マス類やブリ類等、養殖を行った2か所の養殖場のうち、第2段階の育成期間が短いものの、重量が大きい場合には、当該養殖場における育成により水産物の品質が決定されることから、重量の増加が大きい養殖場が属する都道府県が原産地となる。
- 例外として、輸入した稚貝のあさりを区画漁業権に基づき1年半以上育成(養殖)し、育成等に関する根拠書類を保存している場合には、国内の育成地を原産地として表示することができる。
イ 機能性表示食品制度の動き
〈機能性表示食品として、7件の生鮮食品の水産物の届出が公表〉
機能性を表示することができる食品は、国が個別に許可した特定保健用食品(トクホ)と国の規格基準に適合した栄養機能食品のほか、機能性表示食品があります。
食品が含有する成分の機能性について、安全性と機能性に関する科学的根拠に基づき、食品関連事業者の責任で表示することができる機能性表示食品制度では、生鮮食品を含め全ての食品*1が対象となっており、令和5(2023)年3月末時点で、生鮮食品の水産物としては、カンパチ2件(「よかとと 薩摩カンパチどん」及び「生鮮プレミアム 活〆かんぱち」)、ブリ1件(「活〆黒瀬ぶりロイン200g」)、イワシ1件(「大トロいわしフィレ」)、マダイ1件(「伊勢黒潮まだい」)及びクジラ2件(「凍温熟成鯨赤肉」及び「鯨本皮」)の7件の届出が公表されています。
- 特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、並びに脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)及びナトリウムの過剰な摂取につながるものを除く。
ウ 水産エコラベルの動き
〈令和4(2022)年度は新たに111件が国際基準の水産エコラベルを取得〉
水産エコラベルは、水産資源の持続性や環境に配慮した方法で生産された水産物に対して、消費者が選択的に購入できるよう商品にラベルを表示する仕組みです。国内では、一般社団法人マリン・エコラベル・ジャパン協議会による漁業と養殖業を対象とした「MEL」(Marine Eco ‐ Label Japan)、英国に本部を置く海洋管理協議会による漁業を対象とした「MSC」(Marine Stewardship Council)、オランダに本部を置く水産養殖管理協議会による養殖業を対象とした「ASC」(Aquaculture Stewardship Council)等の水産エコラベル認証が主に活用されており、それぞれによる漁業と養殖業の認証実績があります(図表1-14)。
図表1-14 我が国で主に活用されている水産エコラベル認証
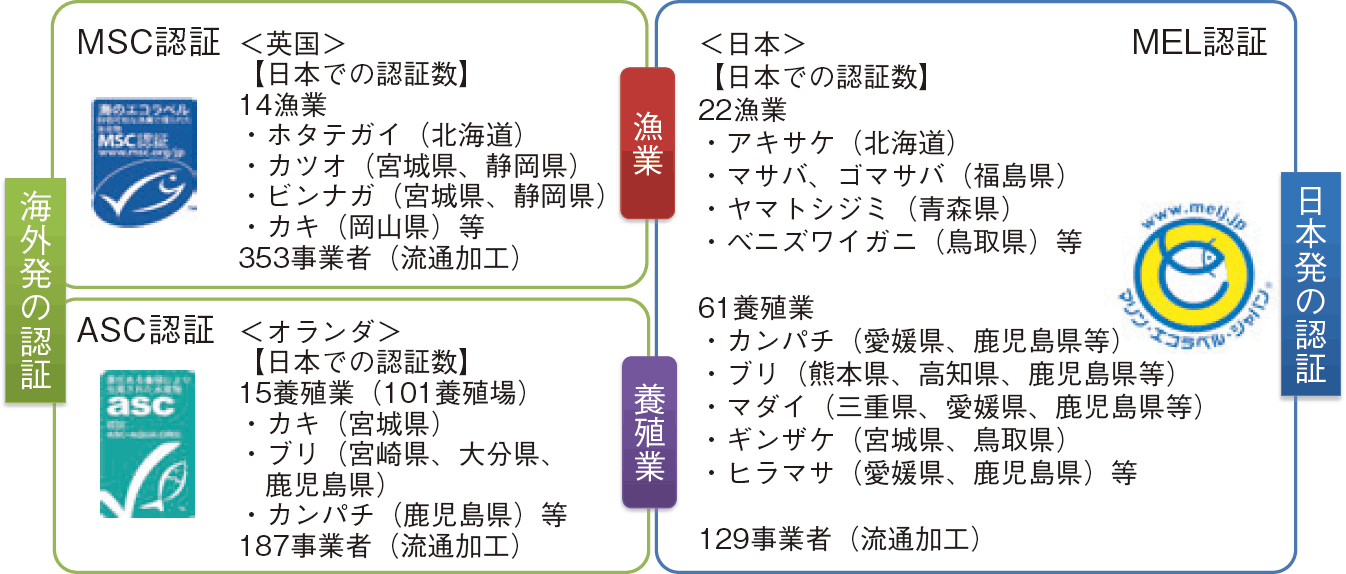
水産エコラベルは、国際連合食糧農業機関(FAO)水産委員会が採択した水産エコラベルガイドラインに沿った取組に対する認証を指すものとされています。しかし、世界には様々な水産エコラベルがあることから、水産エコラベルの信頼性確保と普及改善を図るため、「世界水産物持続可能性イニシアチブ(GSSI:Global Sustainable Seafood Initiative)」が平成25(2013)年に設立され、GSSIから承認を受けることが、国際的な水産エコラベル認証スキームとして通用するための潮流となっています。令和4(2022)年度末時点で、MSC、ASC、MEL等九つの水産エコラベル認証スキームがGSSIの承認を受けています*1。なお、国内では、令和4(2022)年度に、新たに国際基準の水産エコラベル111件(MSC42件、ASC24件、MEL45件)が認証されました。水産庁は、引き続き水産エコラベルの認証取得の促進や水産エコラベルの認知度向上のための周知活動を推進していくこととしています。
また、我が国の水産物が持続可能で環境に配慮されたものであることを消費者に情報提供し、消費者が水産物を購入する際の判断の参考とするための取組として、国立研究開発法人水産研究(すいさんけんきゅう)・教育機構(きょういくきこう)が「SH"U"N(Sustainable, Healthy and "Umai" Nippon seafood)プロジェクト」を行っており、令和4(2022)年度末時点で、44種の水産物について、魚種ごとに資源や漁獲の情報、健康と安全・安心といった食べ物としての価値に関する情報をWebサイトに公表しています。
- ASCは、サーモン、エビのみがGSSI承認の対象。
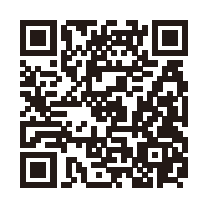
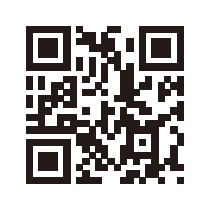
エ 地理的表示保護制度
〈輸出拡大や所得・地域の活力向上に向けてGI保護制度を見直し〉
地理的表示(GI)保護制度は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を地域の知的財産として保護する制度です。我が国では、農林水産物・食品等のGIの保護については、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律*1(地理的表示法)に基づいて、平成27(2015)年から開始されました。この制度により、生産者にとっては、模倣品排除とともに、産品の持つ品質、製法、評判、ものがたり等の潜在的な魅力や強みを見える化し、GIマーク*2とあいまって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールとして活用することができ、また、消費者にとっても、真正のGI産品を容易に選択できるという利点があります。
このようなGI保護制度の機能の活用を促し、産品の輸出拡大、所得・地域の活力向上に更に貢献できるよう、令和4(2022)年11月に審査基準等の見直しを行いました。さらに、国際約束による諸外国とのGIの相互保護に向けた取組、GIに対する侵害対策等、海外における知的財産侵害対策の強化を図ることで、農林水産物・食品等の更なる輸出促進が期待されます。
- 平成26年法律第84号
- 登録された産品の地理的表示と併せて付すことができるもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するもの。
〈海外でGI申請した我が国水産物が初めて登録〉
海外における我が国のブランド産品の模倣品排除とブランド保護のため、輸出品目について、海外でのGI登録も推奨されています。令和4(2022)年8月には、我が国のGI産品「みやぎサーモン」が、ベトナムにおいてGIとして登録されました。これは、海外において、直接申請により初めて登録された我が国のGI水産物です。このことにより、ベトナムにおいて「みやぎサーモン」の模倣品について、行政上の救済手段や輸出入における水際措置の活用が可能となり、現地でのブランドの保護に寄与することとなります。
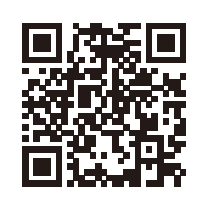
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344





