(3)水産物の食料安全保障の強化に向けた今後の取組
〈水産基本計画に基づく資源管理の徹底と水産業の成長産業化に向けた取組〉
水産基本法が掲げる基本理念の実現に向けて、10年先を見通し、水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために「水産基本計画」(以下「基本計画」といいます。)を定めています。
基本計画は、水産をめぐる情勢の変化や施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに変更することとしており、令和4(2022)年3月に新たな基本計画を策定しました。同計画では、「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」に従った水産資源回復へ向けた取組の着実な実施により漁獲量を444万tに回復させることや、「養殖業成長産業化総合戦略」、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づく生産性の向上、輸出拡大等の水産業の成長産業化等を通じ、令和14(2032)年度における自給率の目標を、食用魚介類で94%、魚介類全体で76%、海藻類で72%と設定しました(図表特-2-8)。自給率は、食料の安定供給がどの程度確保されているかを判断するための一つの指標となるものであることから、この自給率目標の達成に向けて、基本計画に基づく各般の施策を着実に推進していくことにより水産物の食料自給率の向上を図る考えです。
図表特-2-8 水産物の生産量、消費量、自給率の目安
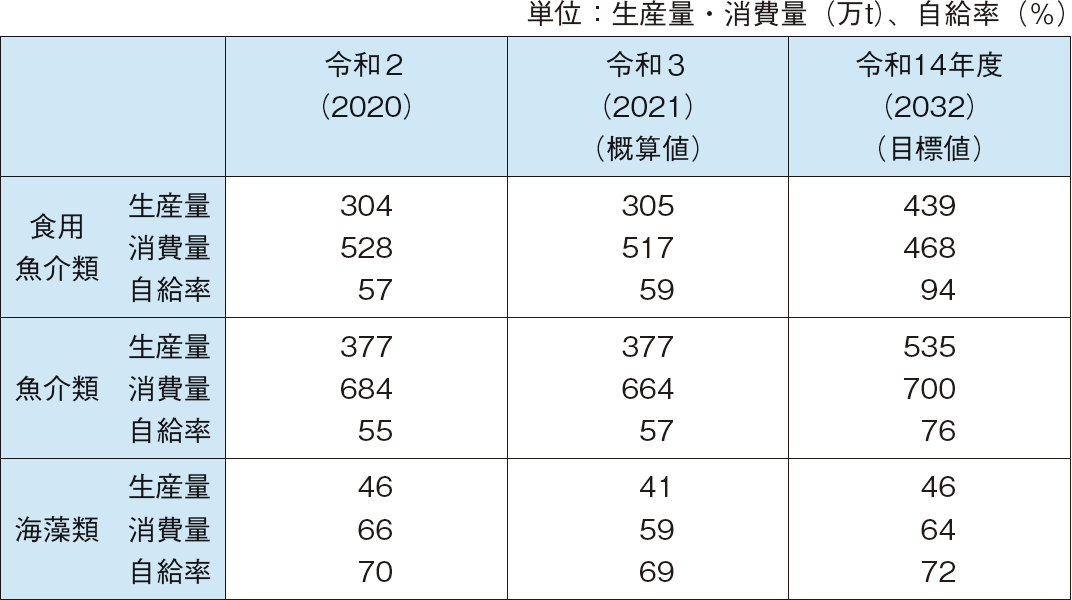
〈農林水産業・地域の活力創造プランの改訂等〉
平成25(2013)年、内閣総理大臣を本部長とする「農林水産業・地域の活力創造本部」は、我が国の農林水産業と地域の活力を創造する政策改革のグランドデザインとして「農林水産業・地域の活力創造プラン」(以下「活力創造プラン」といいます。)を策定しました。
令和4(2022)年6月には、ロシア・ウクライナ情勢による原油等の国際価格の高騰により我が国の食料安全保障の確保がますます重要となっている中、活力創造プランを改訂し食料安全保障の確立等の内容を追加しました。水産物に関する対応については、燃油等の価格高騰対策、資源管理の着実な実施に向けた水産業の振興等の対策について検討を行い、必要な施策を実施することとしています。
また、「農林水産業・地域の活力創造本部」から改組された「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」において、令和4(2022)年12月に継続的に講ずべき食料安全保障の強化のために必要な対策とその目標を明らかにする「食料安全保障強化政策大綱」が策定されました。水産物に関する対応については、養殖飼料(魚粉)の国産化の推進、省エネ技術の導入加速化、食品事業者における国産切替え等の原材料の調達安定化の推進、燃油高騰への対応等の対策が規定されており、引き続き関連施策を推進していくこととしております。

〈食料安全保障の強化に向けた構造転換対策等の実施〉
農林水産省は、令和4(2022)年12月に食料安全保障の強化に向けた構造転換対策等として、次のような取組への支援を措置しました。
・水産加工業者等における原材料の調達安定化
水産加工品の原材料調達の安定化のため、水産加工業者による国産原材料への切替えの取組及び切替えに伴って必要となる機器導入や新商品の開発・製造の支援。
・養殖業の体質強化
配合飼料の原材料の魚粉には価格高騰等の調達リスクがあるため、低魚粉養殖用配合飼料の開発及び原材料の国産化の取組への支援。
また、人工種苗の供給拠点の整備及び給餌効率の向上に資する機器の導入、協業化による養殖経営体の生産性の向上といった取組への支援。
・サケ増殖資材の緊急開発
サケふ化放流の効率化を図るための飼料効率の向上や新たな配合飼料の導入等、サケ稚魚の飼料の技術開発等の取組への支援。
・省エネ技術の導入
持続可能な収益性の高い操業体制への転換を図るため、省エネ化に資する漁業用機器の導入等への支援。
以上のような措置に引き続き、今後も食料安全保障の強化に向け必要な対策に取り組んでいく考えです。
〈今後の食料安全保障の強化に向けて〉
食料・農業・農村基本法の制定から約20年が経過する中で、食料安全保障の強化をはじめ将来に向けた課題に対応するためには、同法の検証・見直し検討が不可欠になっています。このため、令和4(2022)年9月に食料・農業・農村政策審議会に新設された基本法検証部会において、食料、農業及び農村に係る基本的な政策の検証及び評価並びにこれらの政策の必要な見直しに関する基本的事項に関することを調査審議するため、有識者をはじめ、消費者、生産者、経済界、メディア、農業団体等の代表による活発な議論が行われています。
また、先述のとおり、水産物の安定供給の確保を図るためには同法に規定されていない水産資源の管理を適正に行うことも重要です。基本計画に基づく資源管理の取組を推進することはもとより、近年、海洋環境の変化等を要因として、イカ、サンマ、サケや地域における主要な魚種の不漁が継続する一方、これまで漁獲されていなかった魚種の増加も見られるなど水産資源の変化が生じていることから、水産庁では、令和5(2023)年3月から「海洋環境の変化に対応した漁業の在り方に関する検討会」を開催し、漁獲される魚種の変化の状況や要因を把握・分析するとともに、漁業経営・操業の在り方や対応の方向性について検討しています。
同検討会においては、海面水温や底水温の上昇といった海洋環境の変化がサンマやサケ等の表層域の資源に加えて、マダラやズワイガニ等の中層から底層域の資源の減少の要因となっていると考えられること、減少する資源がある一方でマイワシやブリは資源が増加していること、タチウオやフグ等の分布域が北上していること等について、状況を整理・共有いたしました。
また、漁業者等から、海洋環境の変化の状況や漁業現場での取組等を聴取するとともに、有識者や漁業関係団体の関係者等を交え、対応の方向性について議論しています。今後、これらの議論を踏まえ、海洋環境の変化に対応するための対策について検討していく考えです。
食料供給において、自国で生産することは輸送障害や他国との競合等のリスクを下げ、より安定的な供給が期待できることから、水産物の自給率を向上させていくことは、食料安全保障の確立につながっていくものと期待されます。このため、今後とも自給率向上に向けて必要な対策を講じていくこととしています。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344




