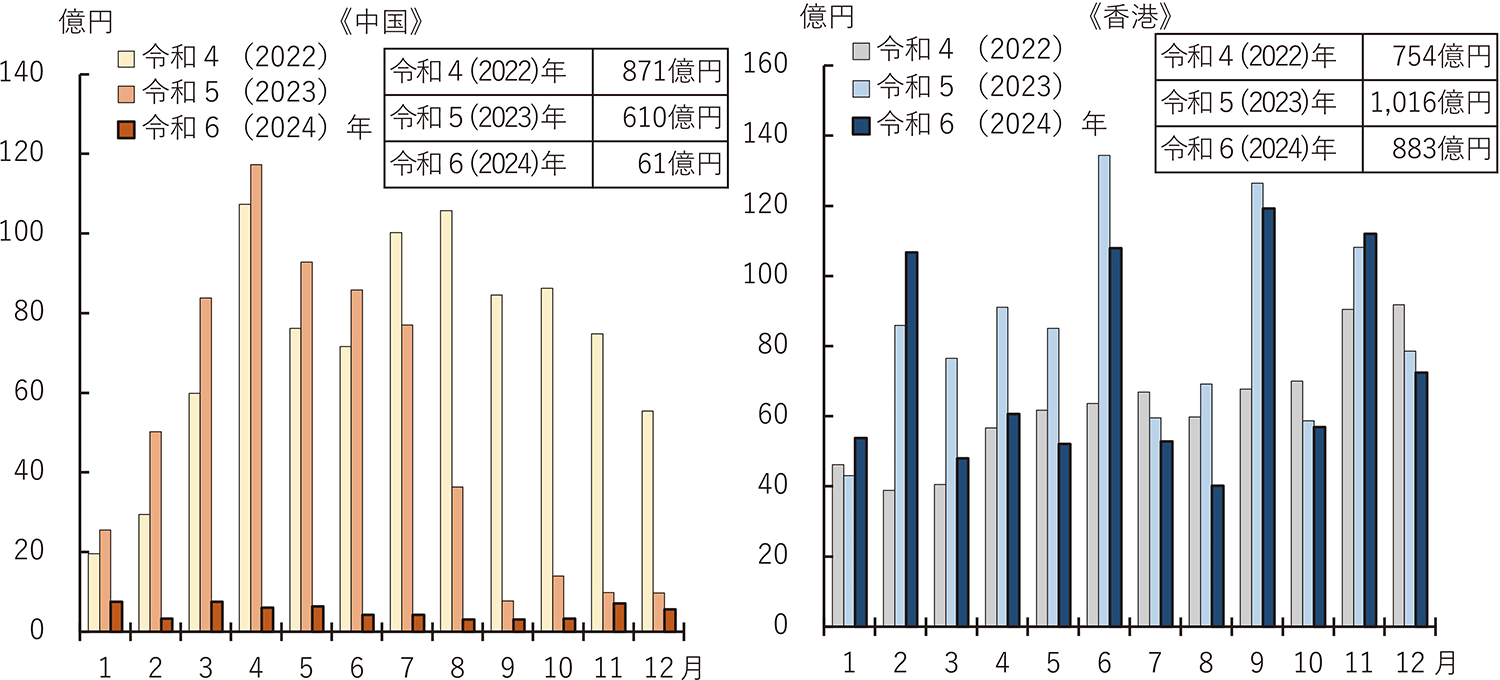(3)ALPS処理水の海洋放出をめぐる動き
ア ALPS処理水の海洋放出とその影響
〈ALPS処理水の海洋放出を受け中国等が日本産水産物の輸入を停止〉
令和5(2023)年8月24日に、ALPS処理水の海洋放出が開始されました。
これに対し、米国は、日本の安全で透明性のある科学に基づいたALPS処理水の海洋放出のプロセスに満足しているとの声明を、EUは、ALPS処理水の海洋放出に対する日本のアプローチが国際的な原子力安全基準及び放射性物質に関する基準の最高水準に合致していると評価したIAEAが令和5(2023)年7月4日に発表した包括的な報告書を歓迎するとの声明を発出しました。
一方、従来の東電福島第一原発事故に伴う輸入規制に加えて、中国及びロシアは全都道府県の水産物を輸入停止としたほか、香港及びマカオは10都県*1の水産物等を輸入停止としました(図表6-9)。
- 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、長野県。
図表6-9 ALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国・地域の食品等の輸入停止の概要(令和7(2025)年1月時点)
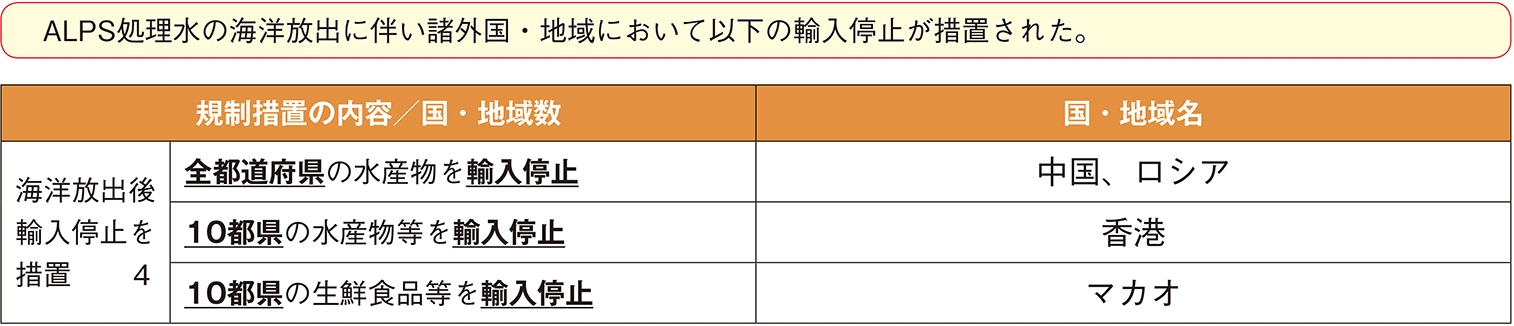
〈中国への水産物輸出が減少〉
ALPS処理水の海洋放出以前の令和4(2022)年の我が国の水産物輸出額の割合を国別に見ると、中国が22.5%と最も高く、次いで香港が19.5%となっています。また、マカオは0.5%、ロシアは0.1%であり、ALPS処理水の海洋放出開始に伴い我が国水産物の輸入規制を行った4か国・地域の水産物輸出額総額に占める割合は4割を超えています。
品目別に見ると、ホタテガイ、ナマコ調整品及びホタテガイ調整品についてはこれらの国・地域の占める割合は5割を超え、カツオ・マグロ類については35%を超えています(図表6-10)。
ALPS処理水の海洋放出に伴う令和5(2023)年8月からの中国による輸入規制の強化により、同月以降中国への輸出額が一時停止し、中国への水産物輸出額は令和4(2022)年比で令和5(2023)年は30%、令和6(2024)年は93%減少しました。また、香港への水産物輸出額は、令和4(2022)年比で令和5(2023)年は35%、令和6(2024)年は17%増加しました(図表6-11)。
図表6-10 令和4(2022)及び6(2024)年の我が国の水産物の輸出先国・地域、主な輸出水産物の輸出先国・地域
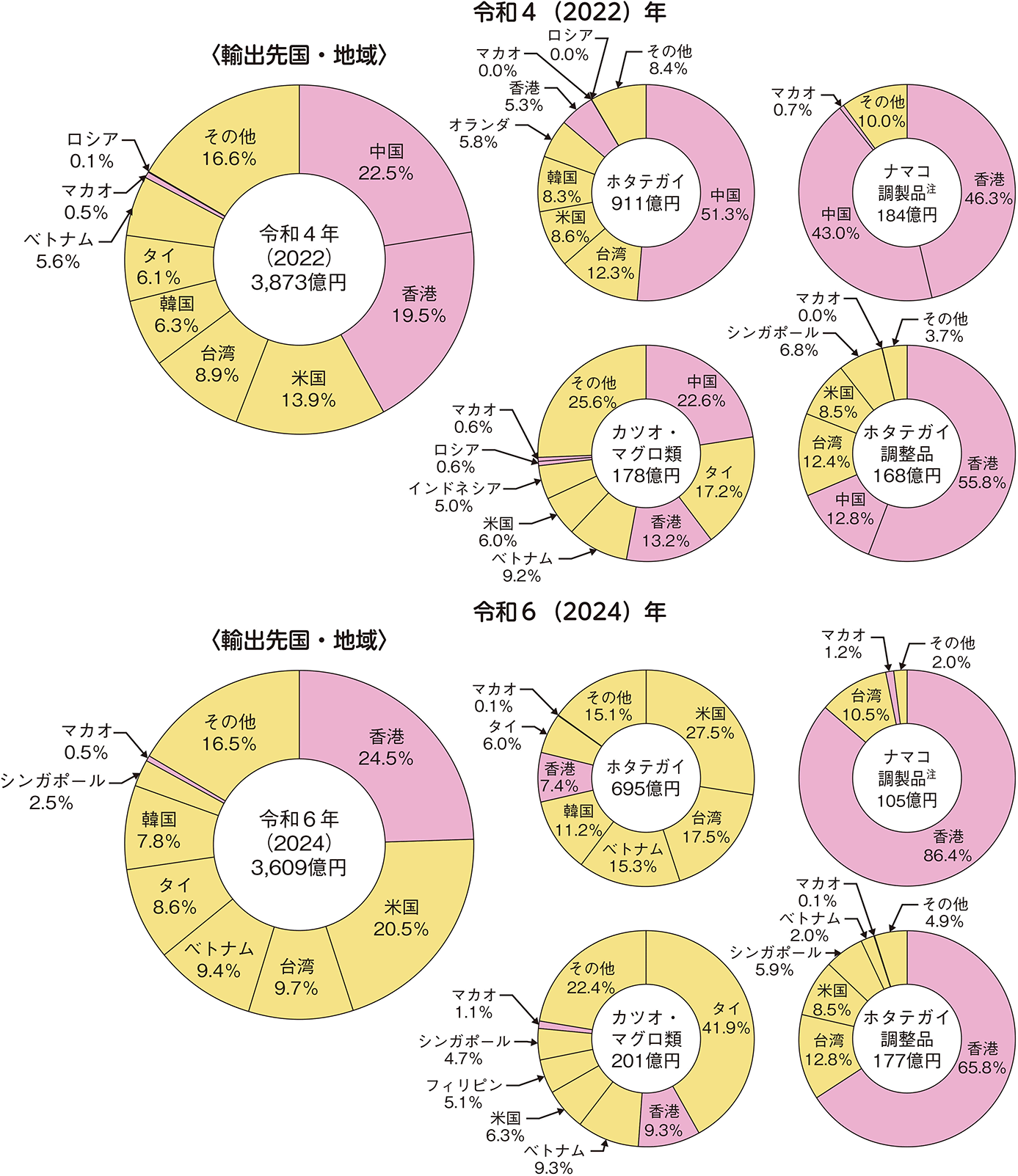
図表6-11 中国及び香港への水産物の輸出額の推移
〈国内における水産物等の動向〉
ALPS処理水の海洋放出以降、東京都中央卸売市場等の大規模消費地市場では国内の水産物価格は全体の傾向として大幅な下落は見受けられていません。中国での殻剥き加工等用に輸出していた北海道のホタテガイについては、多くの産地で価格が下落した時期があったものの輸出先の多角化等により、価格が上向いているとの声もあります。
イ トリチウムを対象とした水産物のモニタリングの実施
〈トリチウムの迅速分析により分析結果を迅速に公表〉
水産庁は、消費者等の安心の回復と信頼の確保につなげるため、令和4(2022)年6月から新たにトリチウムを対象とする水産物のモニタリング分析(精密分析)を開始しました。その後、同分析に加え、令和5(2023)年8月から、短時間でトリチウムの分析が行える手法(迅速分析)を導入し、ALPS処理水の放出口の北北東約4km及び放出口の南南東約5kmで採取した魚類について、採取日から翌々日までに分析結果を公表しています(図表6-12)。
精密分析は、令和4(2022)年6月から令和7(2025)年3月末までの間、636検体の水産物の分析を実施し、これらの分析結果は全て検出限界値(最大で0.408Bq/kg)未満で、放出前後で変化はありませんでした。
また、迅速分析については、令和5(2023)年8月から令和7(2025)年3月末までの間、380検体の水産物の分析を実施し、これらの分析結果は全て検出限界値未満となっており、精密分析と同様に放出前後で変化はなく、海洋放出が問題なく行われていることが裏付けられています。
これらのトリチウムの分析も放射性セシウムの分析と同様の手法により、IAEAとの共同事業の一環として試料採取、分析、比較評価が実施され、分析の透明性の確保に努めています。
図表6-12 水産物の放射性物質モニタリングの検体採取地点(トリチウム)
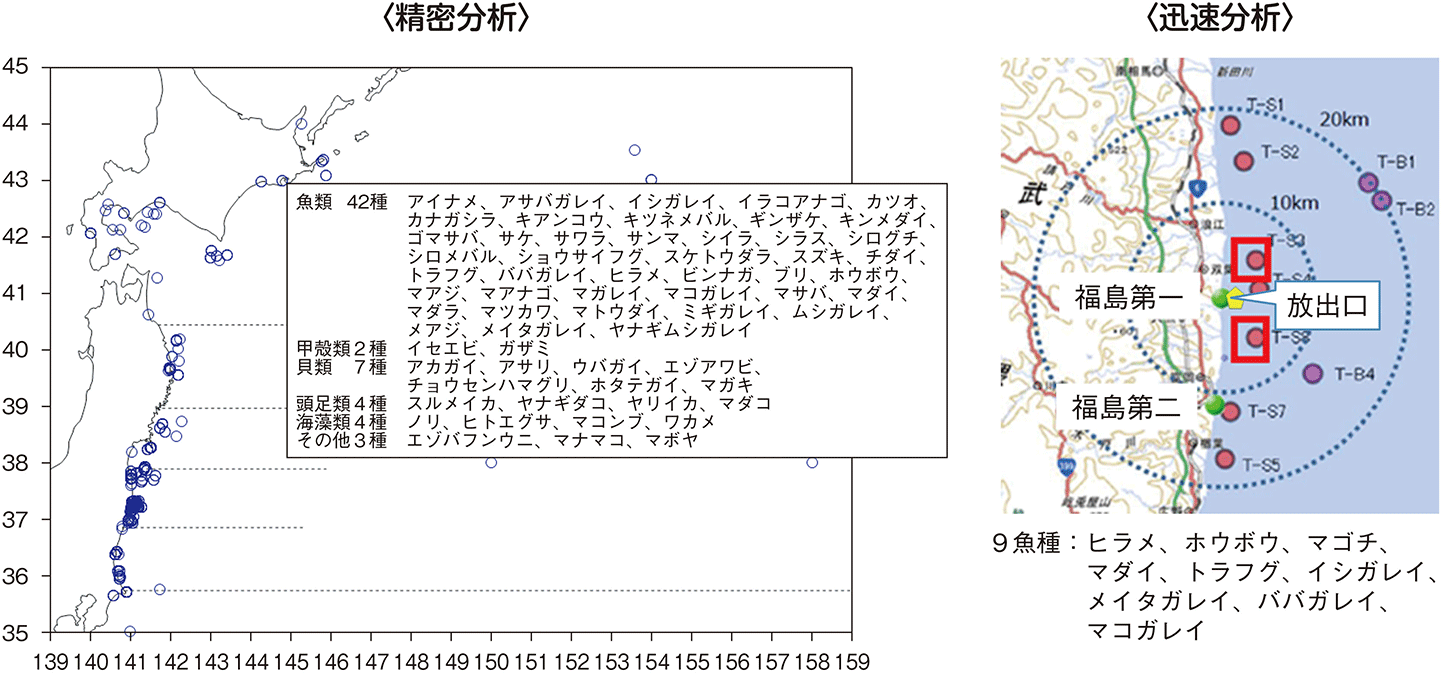
ウ 「水産業を守る」政策パッケージの実施等
〈「水産業を守る」政策パッケージの策定〉
令和5(2023)年9月4日、政府は、ALPS処理水の海洋放出開始以降の中国等の輸入規制強化を踏まえ、科学的根拠に基づかない措置の即時撤廃を求めていくとともに、全国の水産業支援に万全を期するため、総額1,007億円からなる「水産業を守る」政策パッケージを示しました(図表6-13)。
同パッケージは、令和3(2021)年度補正予算において「多核種除去設備等処理水風評影響対策事業」を行うため経済産業省において基金造成された300億円及び令和4(2022)年度第2次補正予算において「ALPS処理水の海洋放出に伴う影響を乗り越えるための漁業者支援事業」を行うため経済産業省において基金造成された500億円の基金による支援、東京電力による賠償等に加え、特定の国・地域への依存を分散するための207億円の緊急支援事業によって、1)国内消費拡大・生産持続対策、2)風評影響に対する内外での対応、3)輸出先の転換対策、4)国内加工体制の強化対策、5)迅速かつ丁寧な賠償の5本柱の政策で構成されています。
また、令和5(2023)年11月には、補正予算により輸出拡大に必要なHACCP*1等対応の施設・機器整備、「地域の加工拠点」施設等を整備する事業等の支援が措置されました。
さらに、令和6(2024)年12月には、補正予算によりALPS処理水関連の輸入規制強化を踏まえた水産業緊急支援事業として、国内外の新規需要開拓、学校給食等の国内販路拡大、日本産水産物の安全性・魅力の情報発信、水産加工業者等の機器の導入等の国内加工体制の強化等の支援が措置されるとともに、海外販路開拓の対策を農水産物の海外輸出推進策の一環で実施していきます。また、ALPS処理水の海洋放出に伴う影響を乗り越えるための国内生産持続対策も実施します(図表6-14)。
- Hazard Analysis and Critical Control Point:危害要因分析・重要管理点。原材料の受入れから最終製品に至るまでの工程ごとに、微生物による汚染や金属の混入等の食品の製造工程で発生するおそれのある危害要因をあらかじめ分析(HA)し、危害の防止につながる特に重要な工程を重要管理点(CCP)として継続的に監視・記録する工程管理システム。国際連合食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(コーデックス)委員会がガイドラインを策定して各国にその採用を推奨している。
図表6-13 「水産業を守る」政策パッケージの概要
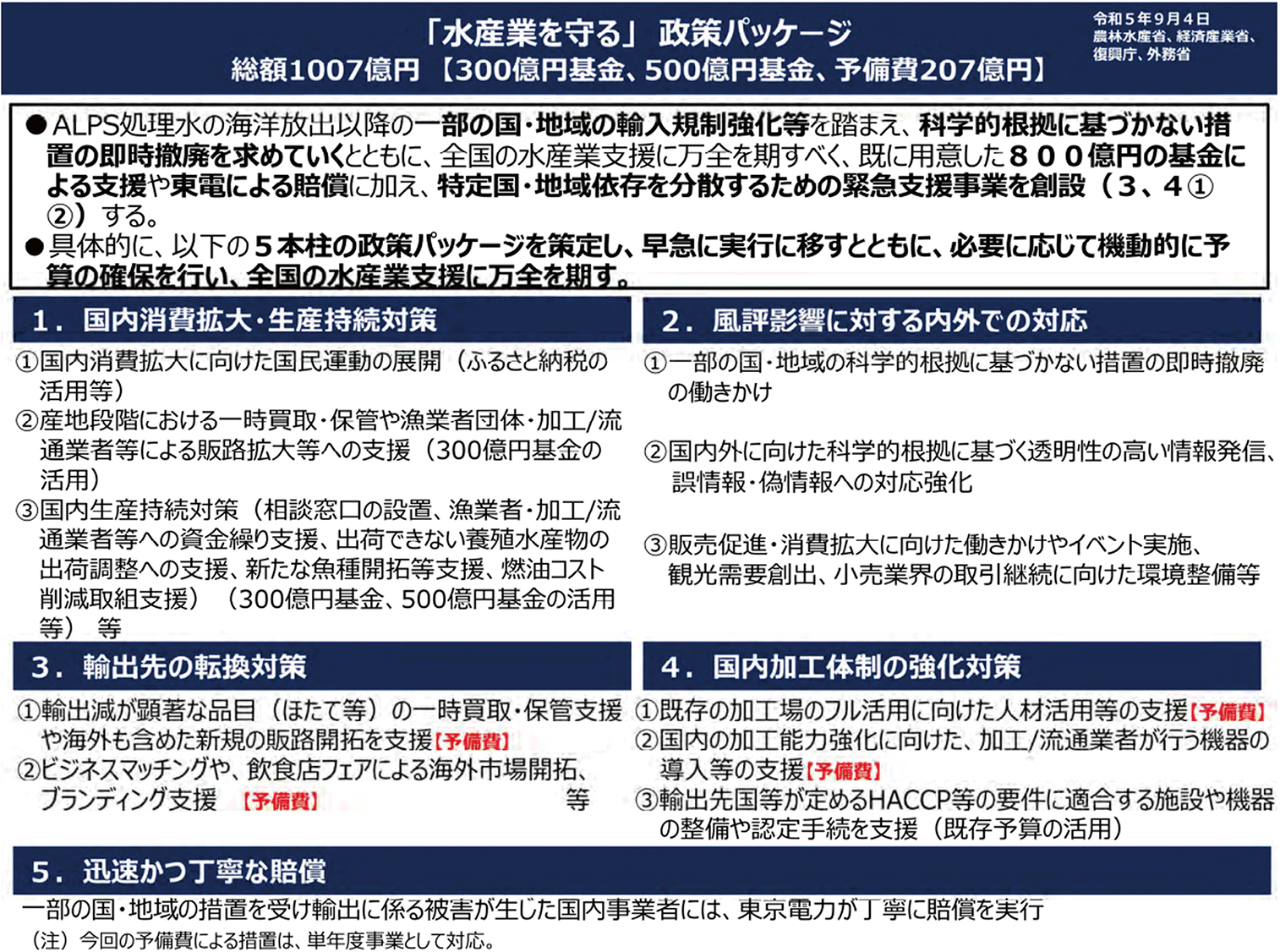
図表6-14 令和6(2024)年度補正予算 ALPS処理水海洋放出に係る水産業支援関連
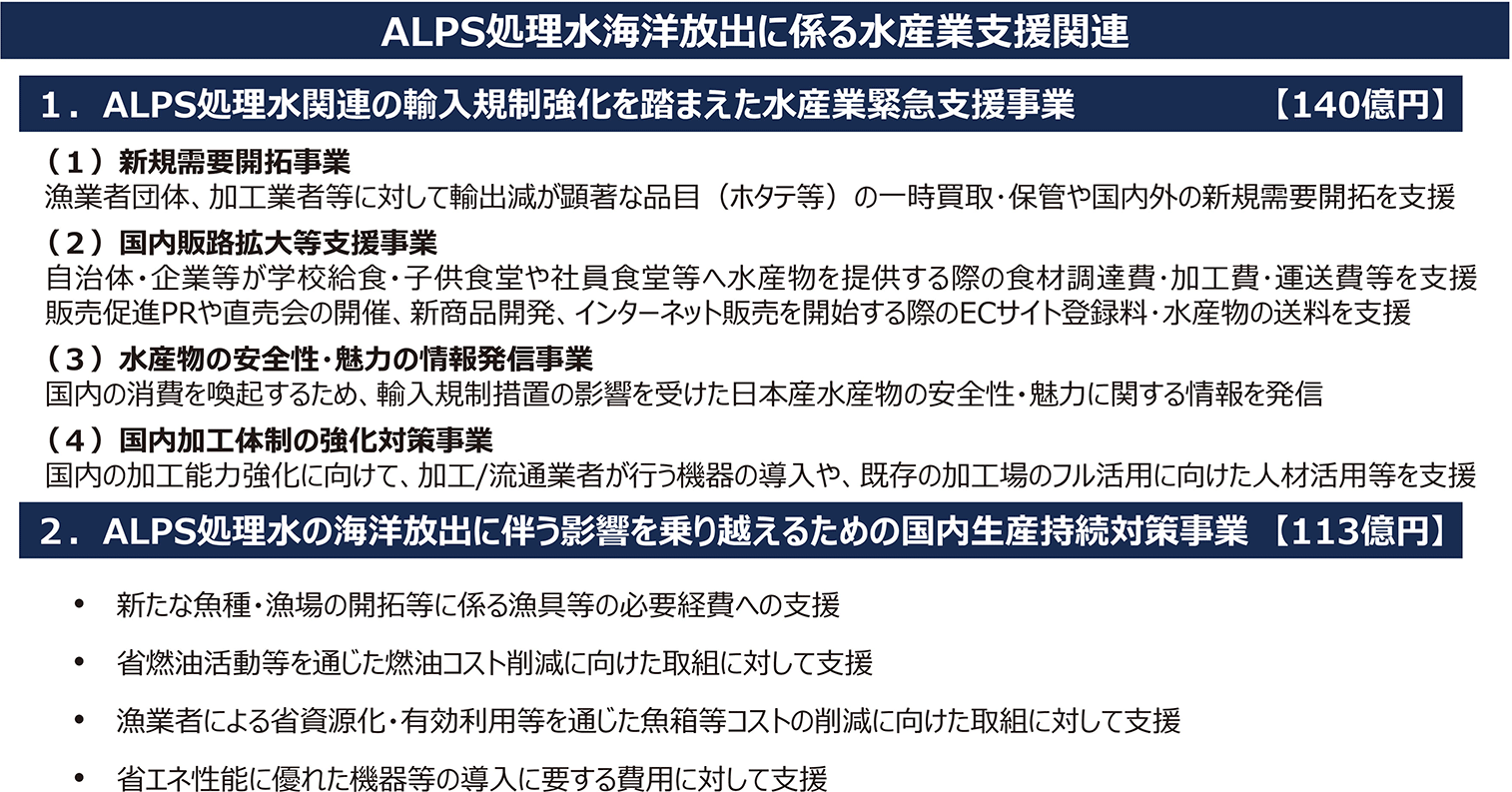
〈日本産水産物の早期輸入回復に向けた働きかけの実施〉
令和6(2024)年9月、中国との間では、ALPS処理水の海洋放出と日本産水産物の輸入規制について「日中間の共有された認識」を発表し、中国側は、IAEAの枠組みの下での追加的モニタリングを実施後、日本産水産物の輸入規制措置の調整に着手し、日本産水産物の輸入を着実に回復させることとなりました。令和6(2024)年11月、日中首脳会談を行い、ALPS処理水の海洋放出と日本産水産物の輸入規制に関する発表を両国できちんと実施していくことを確認しました。また、令和7(2025)年1月、農林水産大臣が訪中し、昨年9月の発表に基づき水産物の輸入再開について着実に進めることを、担当である海関総署と、トップ同士で直接確認しました。このような中、令和6(2024)年9月、我が国とIAEAとの間で、関係国の関心を踏まえ、IAEAの枠組みの下で追加的モニタリングを実施することで一致し、この追加的モニタリングの一環として、令和6(2024)年10月及び令和7(2025)年2月には、IAEAの枠組みの下で追加的モニタリングが実施され、中国を含む参加国の分析機関による採水等が実施されました。令和7(2025)年3月には、日中外相会談及び日中ハイレベル経済対話にて、双方で、昨年9月の発表が着実に履行されていることを共に評価し、日本側から、日本産水産物の輸入を近く再開するよう求め、IAEAの枠組みの下で追加的モニタリングを引き続き実施していくことを確認した上で、分析結果に異常がないことを前提に、日本産水産物の輸入再開に向けて、関連の協議を推進していくことで一致しました。
また、令和6(2024)年8月、農林水産大臣が香港を訪問し、科学的根拠に基づかない輸入規制は極めて遺憾であるとして、撤廃を求めました。我が国として、引き続き、規制を維持している国・地域に対して、輸入規制の即時撤廃を求めていきます。
〈国内消費拡大に向けた取組〉
水産庁では、中国等の輸入規制措置により影響を受ける水産物の国内の消費拡大に向けた対策として、学校給食・子ども食堂等への水産物の提供や、創意工夫による多様な販路拡大の取組への支援を行っています。
また、消費者に向け水産物の魅力や安全性について発信するイベント等を行っているほか、農林水産省においても、SNS等を活用した消費拡大に向けた発信を行っており、例えば、農林水産省公式X(旧Twitter)による「#食べるぜニッポン」を内容とする投稿は、令和6(2024)年度に3千万回以上閲覧されています。
こうした輸入停止等により影響を受ける水産物の応援消費もあり、令和5(2023)年9月から令和6(2024)年8月までの一年間の家計におけるホタテガイの国内消費額が前年同期比で1.4倍になるなどの影響がみられています。
〈国内生産持続に向けた取組〉
輸入規制措置等により影響を受ける水産物の需要減少への対応として、漁業者団体等が行う販路拡大等の取組や水産物の一時的な買取り・保管への支援を行うとともに、出荷が困難となった養殖水産物を養殖場に留め置くために追加的に必要となる飼餌料費等の支援を行っています。
また、ALPS処理水海洋放出の影響のある漁業者に対し、売上高向上や基本コスト削減により持続可能な漁業継続を実現するため、当該漁業者が創意工夫を凝らして取り組む新たな魚種・漁場の開拓等に係る漁具等の必要経費、燃油コスト削減や魚箱等コストの削減に向けた取組、省エネルギー性能に優れた機器の導入に要する費用に対して支援を行っています。
さらに、水産関係事業者への資金繰り支援として、株式会社日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金等について、対象要件の緩和や特別相談窓口の設置等を行うとともに、漁業信用基金協会の保証付融資について、実質無担保・無保証人化措置を講じています。
〈輸出先転換に向けた取組〉
中国等の輸入規制措置を踏まえ、安定的な輸出を継続できるサプライチェーンを構築することが必要です。このため、輸入規制措置等により影響を受ける水産物の輸出先の転換に向けた対策として、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)においては、令和5(2023)年8月に特別相談窓口を設置し、輸入規制等に影響を受けた企業からの相談に対応しているほか、同年9月に「水産品等食品輸出支援にかかる緊急対策本部」を設置し、「水産業を守る」政策パッケージに基づき、海外見本市への出展やバイヤー招へい等による商談機会の組成を行うとともに、日本食品海外プロモーションセンターでは、海外の要人が参加する国際会議等での水産物のプロモーションイベント、海外の飲食・小売店等と連携した水産物フェア等に取り組んでいます。
また、中国へ冷凍両貝で輸出されたホタテガイの一部は、中国でむき身に加工された後に米国向けに輸出されていることから、農林水産省は、JETRO等と連携しベトナム等で殻剥き加工を行い米国等へ輸出するルートの構築等を進め、輸出先の多角化に取り組んでいます。令和6(2024)年においては、ベトナム、タイ、インドネシア等への冷凍両貝の輸出が増加し、これらの輸出先で殻剥き加工が進展しています(図表6-15)。
図表6-15 ベトナム、タイ、インドネシアへのホタテガイの輸出額の推移
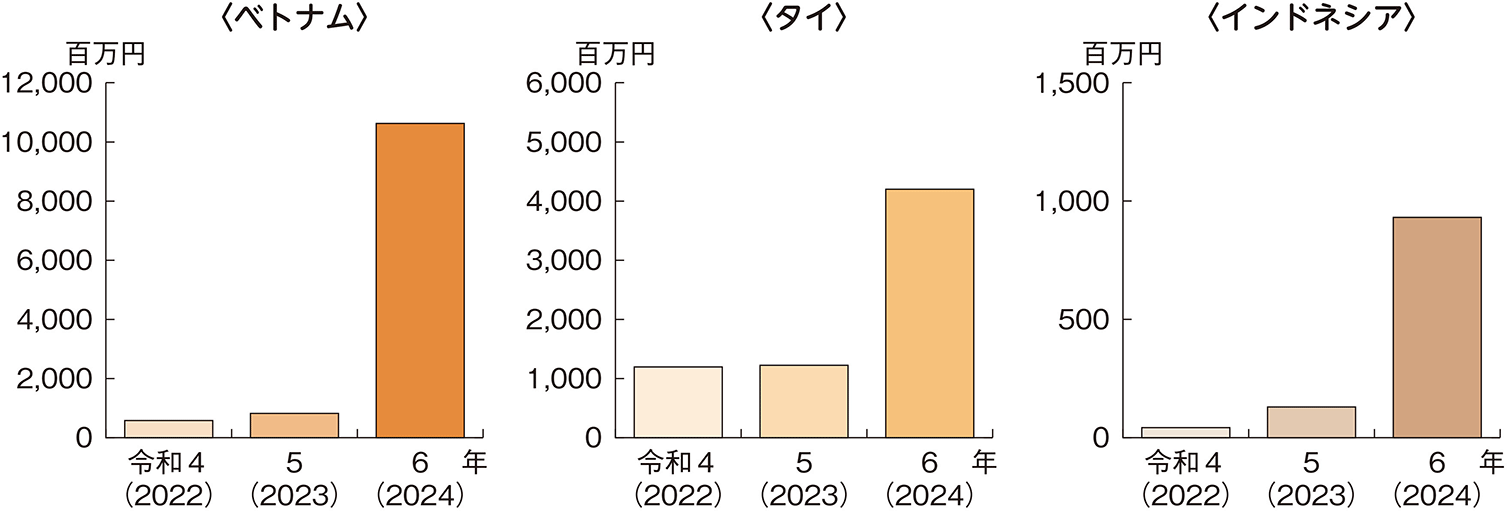
〈国内加工体制の強化に向けた取組〉
中国等による輸入規制強化を踏まえ、特定国・地域依存を分散し、国内外の販路拡大を行うため、例えば中国に殻剥き依存していたホタテガイについては、輸出先のニーズに合わせ、国内で殻を剥くことが重要です。このため、令和5(2023)年9月の予備費や令和5(2023)年11月の補正予算において、加工作業員確保のための人件費の支援や加工能力強化に係る機器導入への支援が措置されたほか、同補正予算においては、広く地域のホタテガイ加工に貢献し、欧米等海外への輸出拠点となる「地域の加工拠点」の整備費用を支援し、加工体制を強化していくこととしています。こうしたことを踏まえ、令和5(2023)年度においては、主流のホタテガイ冷凍貝柱の生産量は、業界紙によれば、令和4(2022)年度比で約1.2倍に増加しました。これらのホタテガイ貝柱の消費地向けの輸出も拡大し、令和6(2024)年においては、令和4(2022)年比で、米国向けの輸出額は約2.4倍、台湾向けは約1.1倍となりました。
また、EUや米国等へ水産物を輸出するためには、水産加工施設等が輸出先国・地域から求められているHACCPの実施、施設基準の適合が必要であることから、HACCP等の要件に適合する施設や機器の整備や認定手続きを支援しています。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344