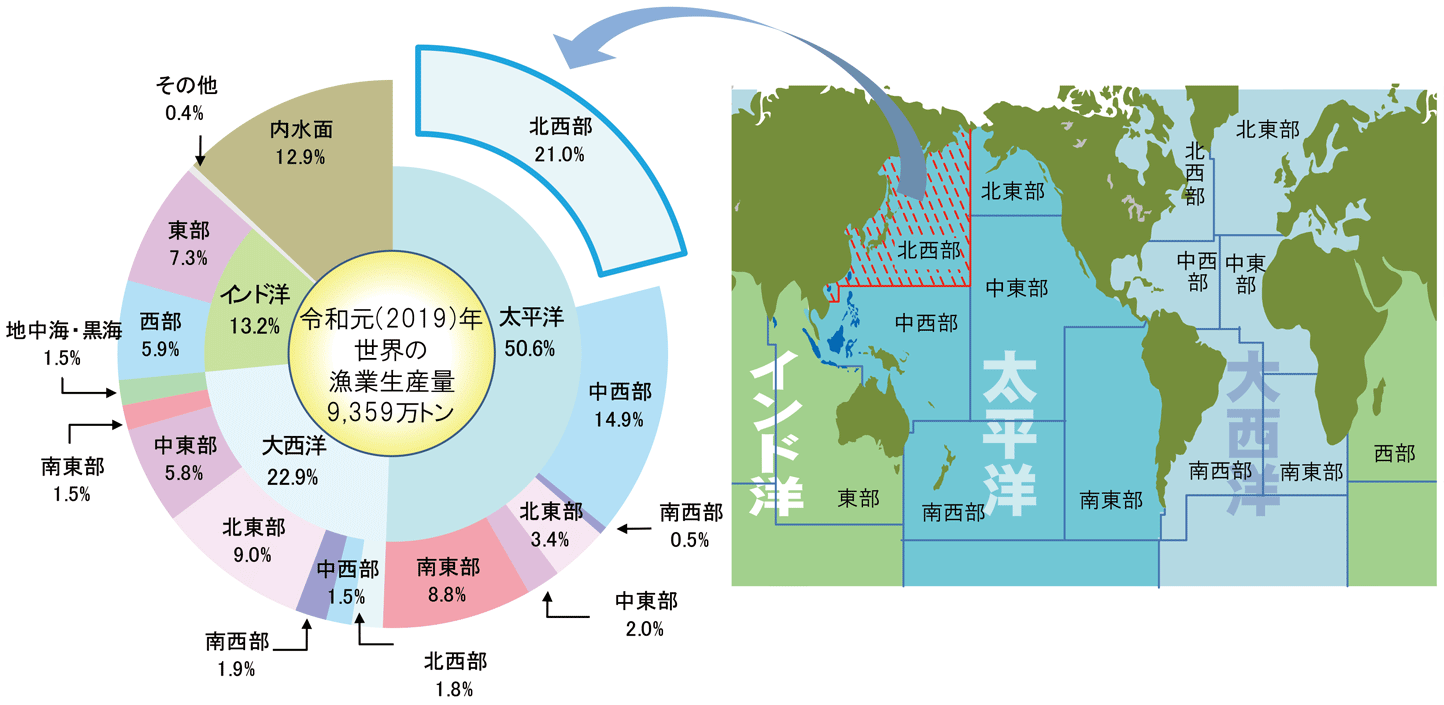(1)我が国周辺の水産資源


ア 我が国の漁業の特徴
〈我が国周辺水域が含まれる太平洋北西部海域は、世界で最も生産量が多い海域〉
我が国周辺水域が含まれる太平洋北西部海域は、世界で最も生産量が多い海域であり、令和元(2019)年には、世界の漁業生産量の21%に当たる1,965万トンの生産量があります(図表3-1)。
図表3-1 世界の主な漁場と漁獲量
この海域に位置する我が国は、広大な領海及び排他的経済水域(以下「EEZ*1」といいます。)を有しており、南北に長い我が国の沿岸には多くの暖流・寒流が流れ、海岸線も多様であることから、その周辺水域には、世界127種の海生ほ乳類のうちの50種、世界約1万5千種の海水魚のうちの約3,700種(うち日本固有種は約1,900種)*2が生息しており、世界的に見ても極めて生物多様性の高い海域となっています。
このような豊かな海に囲まれているため、沿岸域から沖合・遠洋にかけて多くの漁業者が多様な漁法で様々な魚種を漁獲しています。
また、我が国は、国土の7割を占める森林の水源涵養(かんよう)機能や、世界平均の約2倍に達する降水量等により豊かな水にも恵まれており、内水面においても地域ごとに特色のある漁業が営まれています。
- 海上保安庁Webサイト(https://www1.kaiho.mlit.go.jp/JODC/ryokai/ryokai_setsuzoku.html[外部リンク])によると、日本の領海とEEZを合わせた面積は447万km2とされている。
- 生物多様性国家戦略2012‐2020(平成24(2012)年9月閣議決定)による。
イ 資源評価の実施
〈資源評価対象魚種を67魚種から119魚種に拡大〉
水産資源は再生可能な資源であり、適切に管理すれば永続的な利用が可能です。水産資源の管理には、資源評価により資源量や漁獲の強さの水準と動向を把握し、その結果に基づき設定される資源管理の目標に向けて適切な管理措置をとることが重要です。近年では、気候変動等の環境変動が資源に与える影響や、外国漁船の漁獲の増加による資源への影響の把握も、我が国の資源評価の課題となっています。
我が国では、国立研究開発法人水産研究・教育機構を中心に、都道府県水産試験研究機関及び大学等と協力して、市場での漁獲物の調査、調査船による海洋観測及び生物学的調査等を通じて必要なデータを収集するとともに、漁業によるデータも活用して、我が国周辺水域の主要な水産資源について資源評価を実施しています。
平成30(2018)年12月には、「漁業法等の一部を改正する等の法律*1」が成立し、改正後の「漁業法*2」(以下「新漁業法」といいます。)では、農林水産大臣は、資源評価を行うために必要な情報を収集するための資源調査を行うこととし、その結果等に基づき、最新の科学的知見を踏まえて、全ての有用水産資源について資源評価を行うよう努めるものとすることが規定されました。また、国と都道府県の連携を図り、より多くの水産資源に対して効率的に精度の高い資源評価を行うため、都道府県知事は農林水産大臣に対して資源評価の要請ができるとともに、その際、都道府県知事は農林水産大臣の求めに応じて資源調査に協力すること等が規定されました。
このことを受け、水産庁では都道府県及び国立研究開発法人水産研究・教育機構とともに、広域に流通している魚種や都道府県から資源評価の要請があった魚種等を新たに資源評価対象魚種に選定しました。令和2(2020)年度については、資源評価対象魚種を67魚種から119魚種まで拡大し、漁獲量、努力量及び体長組成等の資源評価のためのデータ収集を開始しました(図表3-2)。
そのうち8魚種14系群*3については、新たな資源管理の実施に向け、過去の資源量等の推移に基づく資源の水準と動向の評価から、最大持続生産量(MSY)*4を達成するために必要な「資源量」と「漁獲の強さ」を算出し、過去から現在までの推移を神戸チャート*5により示しました。さらに、資源管理のための科学的助言として、目標管理基準値案、限界管理基準値案及び目標に向かいどのように管理していくのかを検討するための漁獲シナリオ案等に関する助言を国立研究開発法人水産研究・教育機構、都道府県水産試験研究機関等が行いました。資源管理の進め方を検討するに当たり、国立研究開発法人水産研究・教育機構等が、関係する漁業者等に、神戸チャート及び科学的助言の説明を行いました。
新たな資源管理の推進に向け、今後とも、国立研究開発法人水産研究・教育機構や都道府県及び大学等が協力し、継続的な調査を通じてデータを蓄積するとともに、情報収集体制を強化し、資源評価の向上を図っていくことが重要です。
- 平成30(2018)年法律第95号
- 昭和24(1949)年法律第267号
- 1つの魚種の中で、産卵場、産卵期、回遊経路等の生活史が同じ集団。資源変動の基本単位。
- 126ページのコラム参照
- 126ページのコラム参照
図表3-2 資源評価対象魚種数

コラム公海における資源調査
高度回遊性魚類であるサンマやカツオ・マグロ類、遡河性魚類であるシロサケ等は、広く海洋を回遊し生活史の多くの期間を公海で過ごすことから、これら魚種の資源評価や生態解明のためには、公海における成魚の分布、産卵状況及び稚魚の生き残り等の再生産の状況、水温や塩分等の環境の調査が重要となります。
例えば、サンマについては、国立研究開発法人水産研究・教育機構が、日本近海と太平洋公海域において、調査船を用いた調査を実施しています。
この調査は、我が国周辺漁場へのサンマの来遊の見通しに加え、資源評価の精度を向上させるために利用されており、北太平洋漁業委員会(NPFC)における国際的な資源管理の強化にも活用されています。
図:サンマの分布、主な調査海域及び調査船

コラム最大持続生産量(MSY)とは?
水産資源は、漁獲により資源が減少しても自然の回復力が働いて増加します。その増加量(回復量)と同じ量だけ漁獲すれば、資源量は増えもせず減りもせず、その水準で維持されます。
回復量は資源量の増大に伴い増えますが、資源量がある程度以上になると逆に減ります。これは、餌の競合等により成長や生存率が低下するためです。
回復量が最大になる資源量で、その回復量分を漁獲すれば、「最大の漁獲」が続けられる、という考え方が最大持続生産量(MSY:Maximum Sustainable Yield)理論です。
現実には、仔稚魚の生存率や成長速度は海洋環境の変化に大きく影響を受けること等により、MSYの推定には不確実性を伴いますが、科学的知見やデータの蓄積に加え、近年、新たな統計手法やコンピュータ技術の発展により、様々な影響を考慮した推定ができるようになり、資源評価の技術も向上しています。
図:資源量と回復量の関係
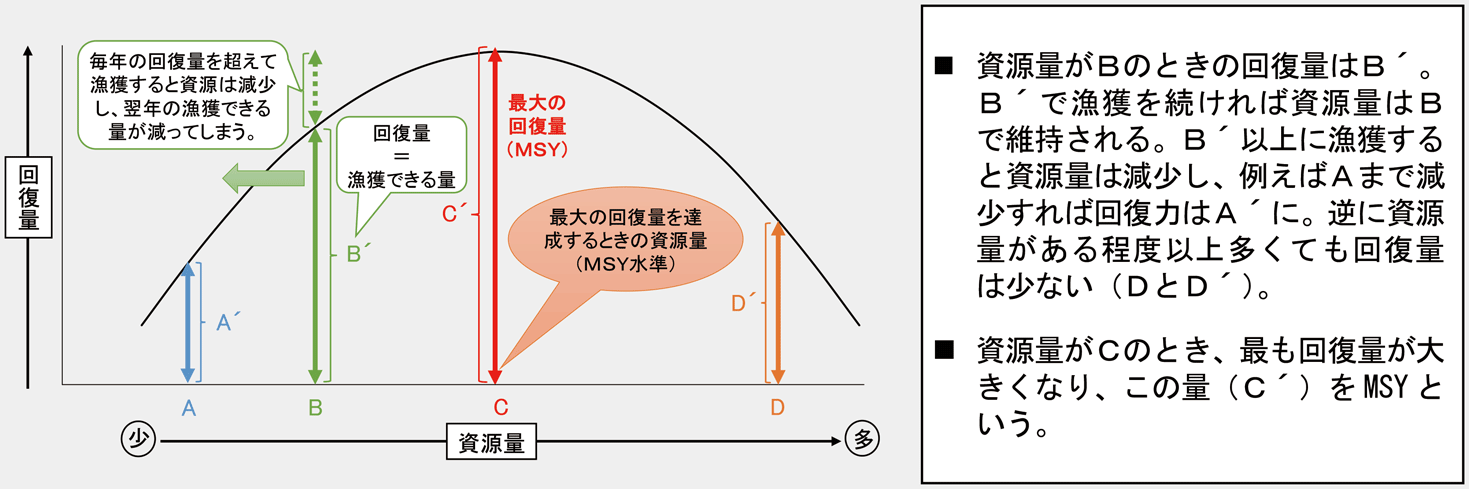
コラム「神戸チャート」とは?
「神戸チャート」は、資源量(横軸)と漁獲の強さ(縦軸)についてMSYを達成する水準(MSY水準)と比較した形で過去から現在までの推移を示したものです。資源が右下の緑の部分に分布するときは、資源量はMSY水準よりも多く、漁獲の強さは適切な状態にあることを示し、資源が左上の赤の部分に分布するときは、資源量はMSY水準よりも少なく、漁獲の強さも過剰であることを示します。
なお、このチャートの名称は、平成19(2007)年に神戸で開催された第1回まぐろ類地域漁業管理機関合同会合に由来しています。
図:神戸チャート
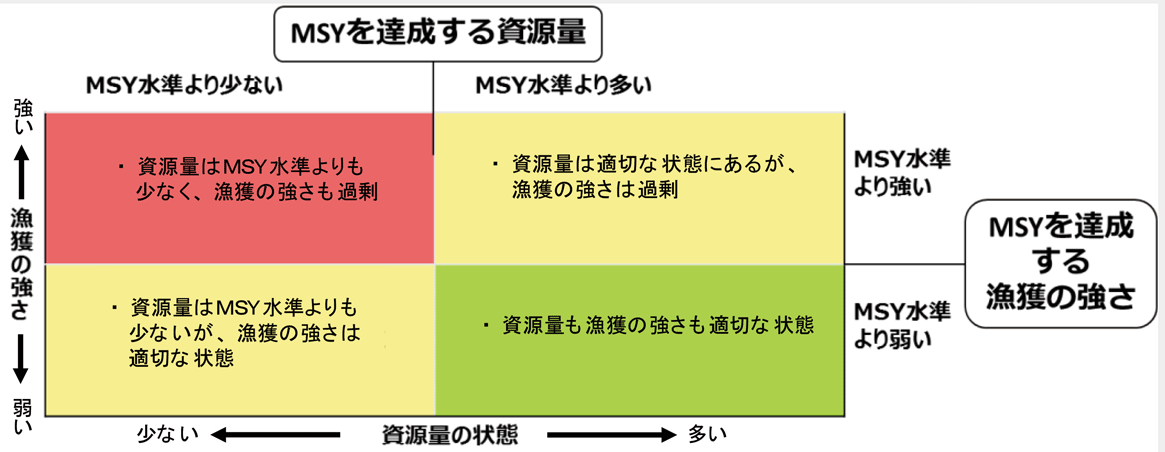
ウ 我が国周辺水域の水産資源の状況
〈8魚種14系群でMSYベースの資源評価、45魚種73系群でMSYベース以外の資源評価を実施〉
令和2(2020)年度の我が国周辺水域の資源評価結果によれば、MSYベースの資源評価を行った8魚種14系群のうち、資源量も漁獲の強さもともに適切な状態であるものはマアジ対馬暖流系群等の3魚種3系群(21%)、資源量は適切な状態にあるが漁獲の強さは過剰であるものはマイワシ太平洋系群の1魚種1系群(7%)、資源量はMSY水準よりも少ないが漁獲の強さは適切な状態であるものはホッケ道北系群等の3魚種3系群(21%)、資源量はMSY水準よりも少なく漁獲の強さも過剰であるものはマサバ太平洋系群等の4魚種7系群(50%)と評価されました(図表3-3)。
図表3-3 我が国周辺の資源水準の状況(MSYをベースとした資源評価 8魚種14系群)

MSYベース以外の資源評価により、資源の水準と動向を評価した45魚種73系群について、資源水準が高位にあるものが18系群(25%)、中位にあるものが17系群(23%)、低位にあるものが38系群(52%)と評価されました(図表3-4)。魚種・系群別に見ると、マダラ北海道太平洋やサワラ瀬戸内海系群については資源量に増加の傾向が見られる一方で、カタクチイワシ太平洋系群やウルメイワシ太平洋系群については資源量に減少の傾向が見られています。
図表3-4 我が国周辺の資源水準の状況(「高位・中位・低位」の3区分による資源評価 45魚種73系群)
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
FAX番号:03-3501-5097