(1)これまでの水産基本計画
ア 水産基本計画とは
〈水産基本法と水産基本計画〉
平成13(2001)年6月に、水産に関する施策の基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定めた「水産基本法*1」(以下「基本法」といいます。)が施行され、以降、基本法が掲げる「水産物の安定供給の確保」と「水産業の健全な発展」という二つの基本理念(図表特-1-1)の実現を図るための施策を推進してきました。
- 平成13(2001)年法律第89号
図表特-1-1 水産基本法の基本理念
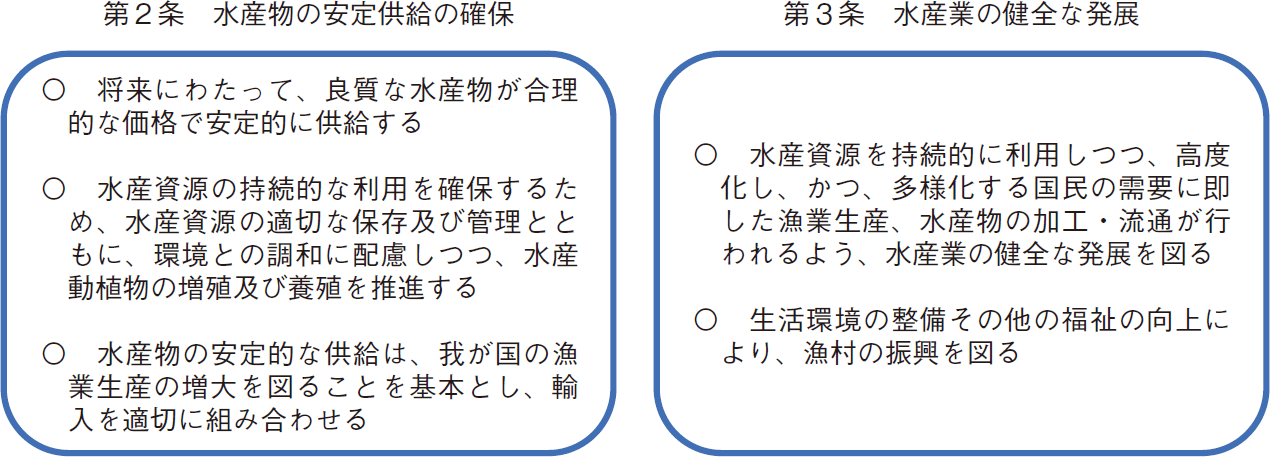
水産基本計画(以下「基本計画」といいます。)は、基本法が掲げる基本理念の実現に向けて、10年程度先を見通し、水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために策定する計画であり、水産をめぐる情勢の変化や施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに変更することとしています。
また、基本法第11条第3項において、「水産物の自給率の目標は、その向上を図ることを旨とし、我が国の漁業生産及び水産物の消費に関する指針として、漁業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定める」こととされており、基本計画では食用魚介類、魚介類全体(食用魚介類に飼肥料向け魚介類を加えたもの)及び海藻類の自給率の目標を設定しています。
イ 各基本計画の概要
〈平成14(2002)年策定の基本計画〉
最初の基本計画は、平成6(1994)年の国連海洋法条約の発効による本格的な200海里体制への移行、我が国の漁業生産の減少、漁業の担い手の減少と高齢化の進行、水産物の自給率の低下等、水産をめぐる状況が大きく変化してきたことを背景に制定された基本法に基づき、平成14(2002)年に策定されました。
本基本計画では、漁業生産及び水産物消費の面において、関係者が取り組むべき具体的な課題を明らかにした上で、これらの課題が解決された場合に実現可能な漁業生産量*1及び消費量の水準を、それぞれ「持続的生産目標」と「望ましい水産物消費の姿」として明示し、平成24(2012)年度の水産物の自給率目標を設定しました。そして、その目標の達成に向けて、適切な国際漁業管理のために必要な体制の構築と運営、資源回復計画*2の推進、HACCP*3の導入等の水産物の安定供給の確保に関する施策、水産基盤の一体的な整備の推進等の水産業の健全な発展に関する施策、漁業協同組合(以下「漁協」といいます。)の合併等の団体の再編整備に関する施策を展開することとしました(図表特-1-2)。
- 漁業・養殖業の生産量のこと。
- 資源の回復を図ることが必要な魚種や漁業種類を対象として、減船、休漁等の漁獲努力量の削減をはじめ、積極的な資源培養、漁場環境の保全等の措置を総合的に行い、資源を回復することを目的とする計画。平成23(2011)年度終了。
- Hazard Analysis and Critical Control Point:危害要因分析・重要管理点。原材料の受入れから最終製品に至るまでの工程ごとに、微生物による汚染や金属の混入等の食品の製造工程で発生するおそれのある危害要因をあらかじめ分析(HA)し、危害の防止につながる特に重要な工程を重要管理点(CCP)として継続的に監視・記録する工程管理システム。国際連合食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格(コーデックス)委員会がガイドラインを策定して各国にその採用を推奨している。91ページ参照。
図表特-1-2 平成14(2002)年策定の基本計画の概要
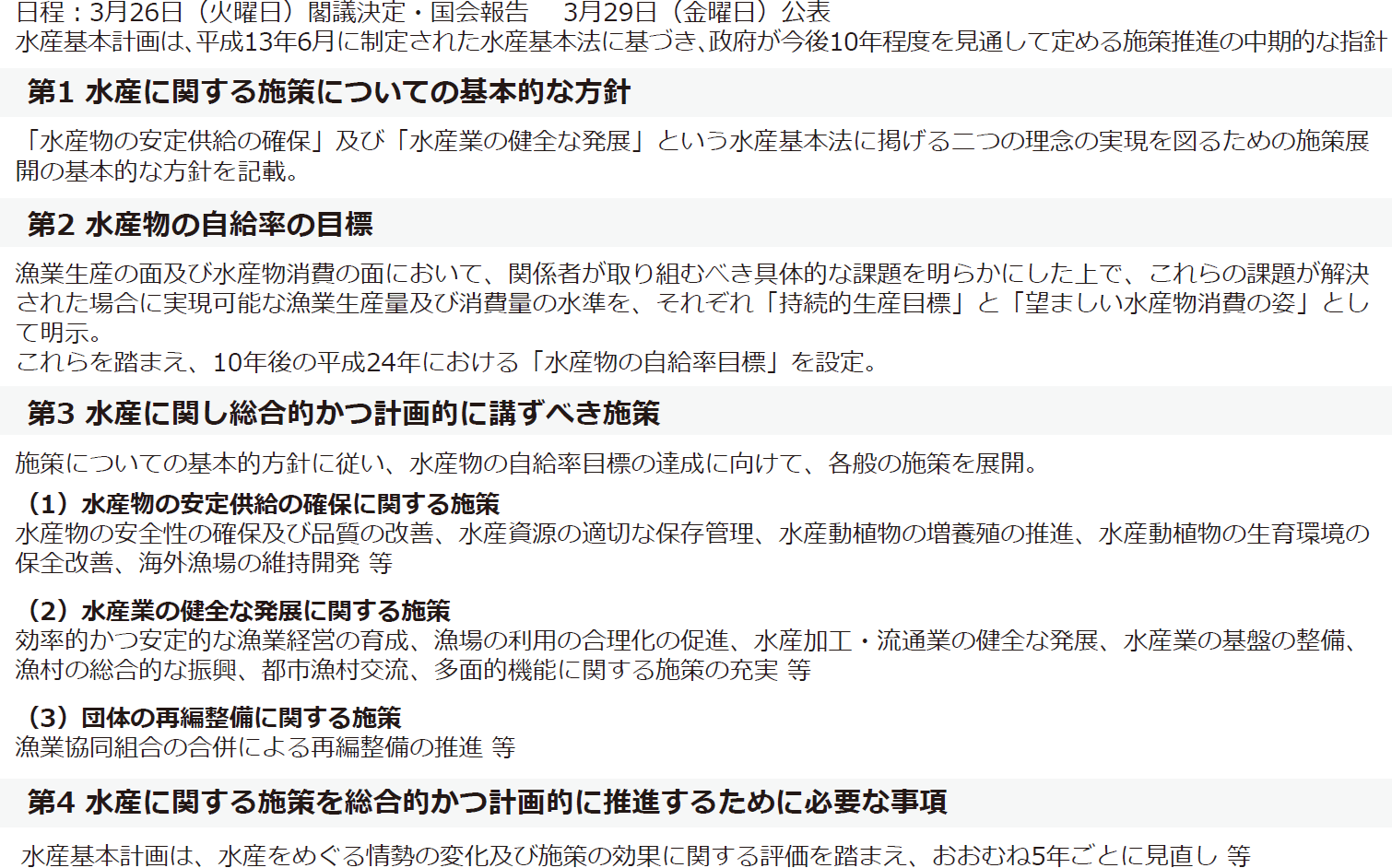
〈平成19(2007)年策定の基本計画〉
平成14(2002)年の基本計画策定以降、漁業就業者の高齢化や漁船の高船齢化等の漁業生産構造の脆弱(ぜいじゃく)化、資源状況の悪化、急速な「魚離れ」や消費流通構造の変化、水産物の世界的需要の高まりによる「買い負け」等が起こりました。一方、栄養バランスの優れた「日本型食生活」の実現を図る上での水産物の重要性が再認識されるとともに、自然環境や生態系の保全、国民の生命・財産の保全、居住や交流の場の提供等、水産業・漁村が有する多面的機能に対する国民の期待が高まりました。
このような情勢の変化を踏まえ、平成19(2007)年の基本計画では、生産構造の脆弱化に対応するため、収益性重視の操業・生産体制の導入や改革型漁船の取得等による経営転換を促進するための漁船漁業構造改革対策に加え、新しい経営安定対策等により、国際競争力のある経営体の育成・確保を図ることとしました。さらに、低位水準にとどまっている水産資源の回復・管理の推進のほか、国産水産物の競争力の強化を目的としたロットや規格を揃えた水産物の流通拠点の整備や水産物の輸出戦略の積極的な展開、水産業・漁村の多面的機能の発揮等の施策を講ずることとし、関係法令の改正に取り組むこととしました(図表特-1-3)。
図表特-1-3 平成19(2007)年策定の基本計画の概要

〈平成24(2012)年策定の基本計画〉
平成19(2007)年の基本計画策定後の大きな情勢の変化としては、平成23(2011)年に発生した東日本大震災が挙げられ、同震災により我が国の漁業の一大生産拠点である太平洋沿岸をはじめとする全国の漁業地域は甚大な被害を受けました。また、我が国周辺水域の水産資源で低位水準のものが少なくなるなど資源管理に一定の成果が見られる一方、水産物の生産体制の脆弱化が進んでいること等から、資源管理の一層の推進と漁業経営の安定確保の両立を図るため、平成23(2011)年度に資源管理指針と資源管理計画に基づく資源管理・漁業所得補償対策を導入しました*1。
これらを受けて、平成24(2012)年策定の基本計画では、東日本大震災からの復興を大きなテーマとし、東日本大震災からの復興の基本方針、水産復興マスタープラン等で示し実施してきた水産復興の方針を改めて基本計画に位置付けました。
また、資源管理・漁業所得補償対策を中核施策として明記し、我が国にとって「身近な自然の恵み」である周辺水域を中心とする水産資源の活用を図ることとしました。
このほか、加工・流通・消費に関して、6次産業化の取組の加速、HACCP等衛生管理の高度化、水産物流通ルートの多様化、魚食普及、輸出等を推進するとともに、安全な漁村づくりと水産業・漁村の多面的機能の発揮に向けた施策や漁船漁業の安全対策の強化等に取り組むこととし、漁業生産や水産物消費の回復を目指しました(図表特-1-4)。
- 資源管理指針及び資源管理計画については、108ページ参照。
図表特-1-4 平成24(2012)年策定の基本計画の概要
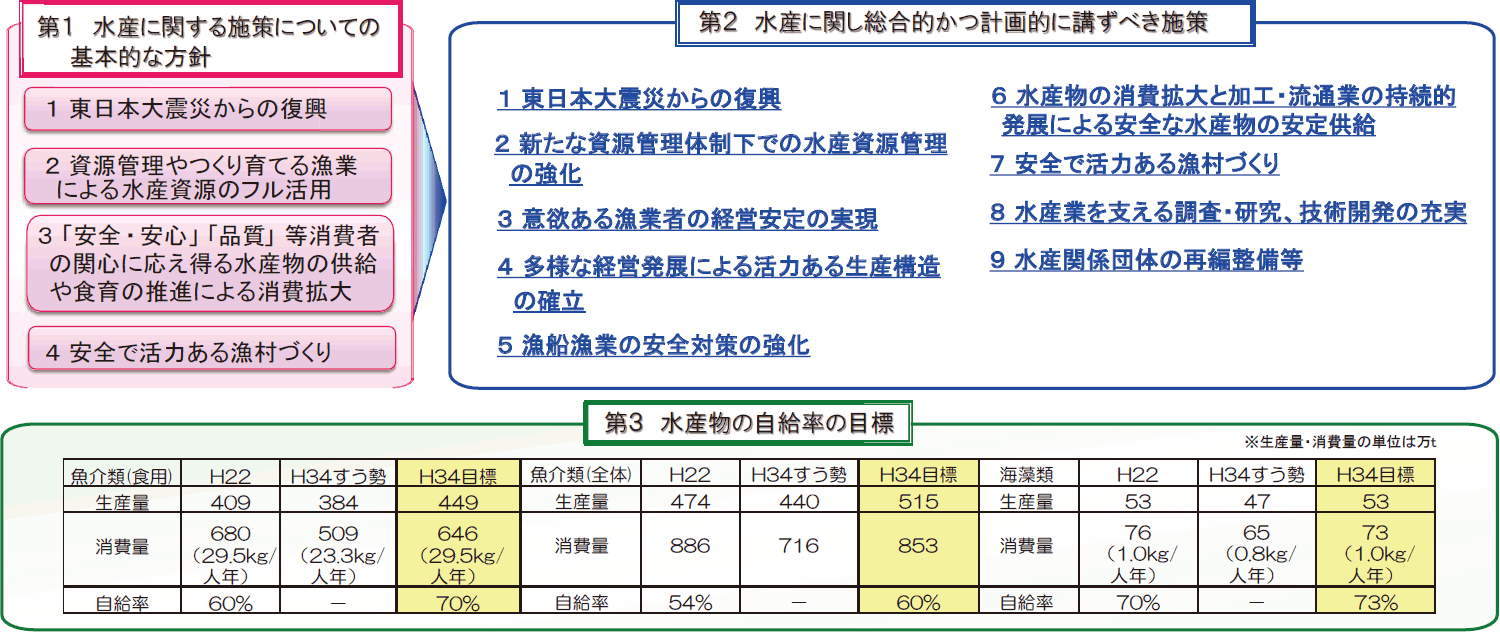
〈平成29(2017)年策定の基本計画〉
平成29(2017)年策定の基本計画では、平成14(2002)年に基本計画が初めて策定されて以来、世界的に水産物の需要が増大し、我が国周辺の豊かな水産資源を適切に管理し、国民に安定的に水産物を供給していくことの重要性が高まっている反面、漁船の高船齢化や漁業者の減少・高齢化等による水産物の生産体制の脆弱化や国民の魚離れが進行していることを受けて、水産資源を持続的な形でフル活用することを図るとともに、産業としての生産性の向上と所得の増大による漁業の成長産業化、また、その前提となる資源管理の高度化を図ることとしました。
具体的には、1)国際競争力のある漁業経営体の育成、2)所得向上に向けた浜の活力再生プラン・浜の活力再生広域プラン*1(以下それぞれ「浜プラン」・「広域浜プラン」といいます。)の着実な実施、3)海技資格の早期取得のための新たな仕組みの構築を含めた海技士等の人材の育成・確保、4)魚類・貝類養殖業等への企業の参入、5)資源管理目標や数量管理等による資源管理の充実と沖合漁業等の規制緩和、6)持続可能な漁業・養殖業の確立、7)産地卸売市場の改革、8)多面的機能の発揮の促進、等について、重点的に取り組むこととしました。さらに、数量管理等による資源管理の充実や漁業の成長産業化等を強力に進めるために必要な施策について、関係法令の見直しも含め、引き続き検討していくこととしました(図表特-1-5)。
- 浜の活力再生プラン及び浜の活力再生広域プランについては、70ページ参照。
図表特-1-5 平成29(2017)年策定の基本計画の概要

お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
FAX番号:03-3501-5097




