(2)新たな水産基本計画
〈水産に関する施策についての基本的な方針〉
新たな基本計画は、これまでの施策の評価及び水産をめぐる情勢の変化と課題を踏まえて、令和4(2022)年3月に策定されました。
水産をめぐる情勢の変化としては、平成29(2017)年策定の基本計画以降、水産庁が、平成30(2018)年12月に成立した「漁業法等の一部を改正する等の法律*1」や令和2(2020)年9月に策定した「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ*2」(以下「ロードマップ」といいます。)等に基づき、新たな資源管理システムの構築、生産性の向上に資する漁業許可制度の見直し、海面利用制度の見直し等の「水産政策の改革」(以下「水産改革」といいます。)に取り組んできたことが挙げられます。
さらに、水産庁は、令和2(2020)年7月に策定(令和3(2021)年7月改訂)した「養殖業成長産業化総合戦略」(以下「養殖戦略」といいます。)に基づき、国内外の需要を見据えて、生産から販売・輸出に至る総合戦略によるマーケットイン型養殖業への転換に取り組んできました。特に、ぶり、たい、ホタテ貝及び真珠については、令和2(2020)年12月に策定された「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略*3」(以下「輸出戦略」といいます。)において輸出重点品目として位置付け、令和12(2030)年までに農林水産物・食品の輸出額を5兆円とする目標の達成に向けて輸出促進に取り組んできました。
このような取組により、漁船漁業の構造改革や養殖業における大規模化が進展するとともに、水産物の輸出が拡大してきています。また、漁港施設の再編整備や「海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業」(以下「海業(うみぎょう)*4」といいます。)の広がり等の明るい動きが見えてきています。
しかしながら、近年顕在化してきた海洋環境の変化をはじめとした地球規模の環境変化を背景に、我が国の主要な魚種の不漁等、我が国水産業にとって厳しい状況が続いています。
また、社会経済全体では、我が国において、少子・高齢化と人口減少による経済の停滞、地方の衰退、労働力不足等が懸念され、さらには、新型コロナウイルス感染症拡大により社会経済活動の制限、個人の行動様式の変化等の影響が生じています。加えて、持続的な社会の実現に向け、持続可能な開発目標(SDGs)やカーボンニュートラルをはじめとした様々な環境問題への国際的な取組の広がりやデジタル化の進展が人々の意識や行動を大きく変えつつあります。
このような情勢を踏まえると、水産物を安定的に供給するため、沿岸・沖合・遠洋漁業や養殖業、加工・流通業の形態が果たす役割の重要性を再認識し、資源評価の高度化を図りながら、海洋環境の変化への対応や漁獲量の増大と漁業者の所得向上に向け、資源管理を着実に実施していく必要があります。
また、長期的な社会・経済・環境等の変化を見通した上で、実態に合わなくなった制度やシステムを見直し、新たな人材・組織や資金を呼び込み、新技術を活用し、水産業を成長産業へ転換させ、漁村の活性化を図っていく必要があります。
このような考え方の下、水産に関する施策についての基本的な方針として、1)海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施、2)増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化の実現、3)地域を支える漁村の活性化の推進、の3本の柱を中心に施策を展開することとしました。基本的な方針の概要は以下のとおりです(図表特-1-6)。
1)海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施
水産改革に基づく新たな水産資源管理の着実な実施を図るため、ロードマップに従い、資源調査・評価体制の整備を進めるとともに、漁業者をはじめとした関係者の理解と協力を得た上で、科学的知見に基づいて新たな資源管理を推進する。その際、地球温暖化等を要因とした海洋環境の変化が水産業へ及ぼす影響や原因を把握し、変化に応じた具体的な取組を進めていく。
2)増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化の実現
(ア)漁船漁業の成長産業化
漁業現場に合わせたスマート水産技術の開発・現場実装を図るとともに、資源変動等の変化に適応した弾力性のある経営体の育成や漁船の脱炭素化等、漁船漁業の持続的な成長に向け、沿岸、沖合、遠洋漁業ごとの課題に対応した具体的な取組を進めていく。また、不足する漁業人材を確保するため、水産教育の充実と若者に魅力ある就業環境等を整備するとともに、外国人材の受入環境の整備を図っていく。
(イ)養殖業の成長産業化
養殖戦略に基づく取組を着実に実施し、マーケットイン型養殖業の推進、ICT*5等を活用した生産性の向上、経営体の強化、輸出の拡大等、養殖業の成長産業化に向けた課題に対応した具体的な取組を進めていく。また、ICTを活用した生産管理、省人化・省力化のための機器導入等といった養殖業者による成長産業化への取組の更なる推進や、環境負荷の低減が可能な大規模沖合養殖の促進を図っていく。
3)地域を支える漁村の活性化の推進
漁村の活性化を図るため、漁業実態に応じた漁港施設の再編整備を進めるとともに、拠点漁港等を核として、複数漁協間の広域合併や連携強化を進める。その際、海業などを行う漁協等の民間事業者との連携により、漁業以外の産業の取込みを推進する等、漁村地域の所得向上に対応した具体的な取組を進めていく。
- 平成30(2018)年法律第95号
- 新たな資源管理の推進に向けたロードマップについては、103ページ参照。
- 農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略については、55ページ参照。
- 海業については、160ページ参照。
- Information and Communication Technology:情報通信技術
図表特-1-6 新たな基本計画の概要
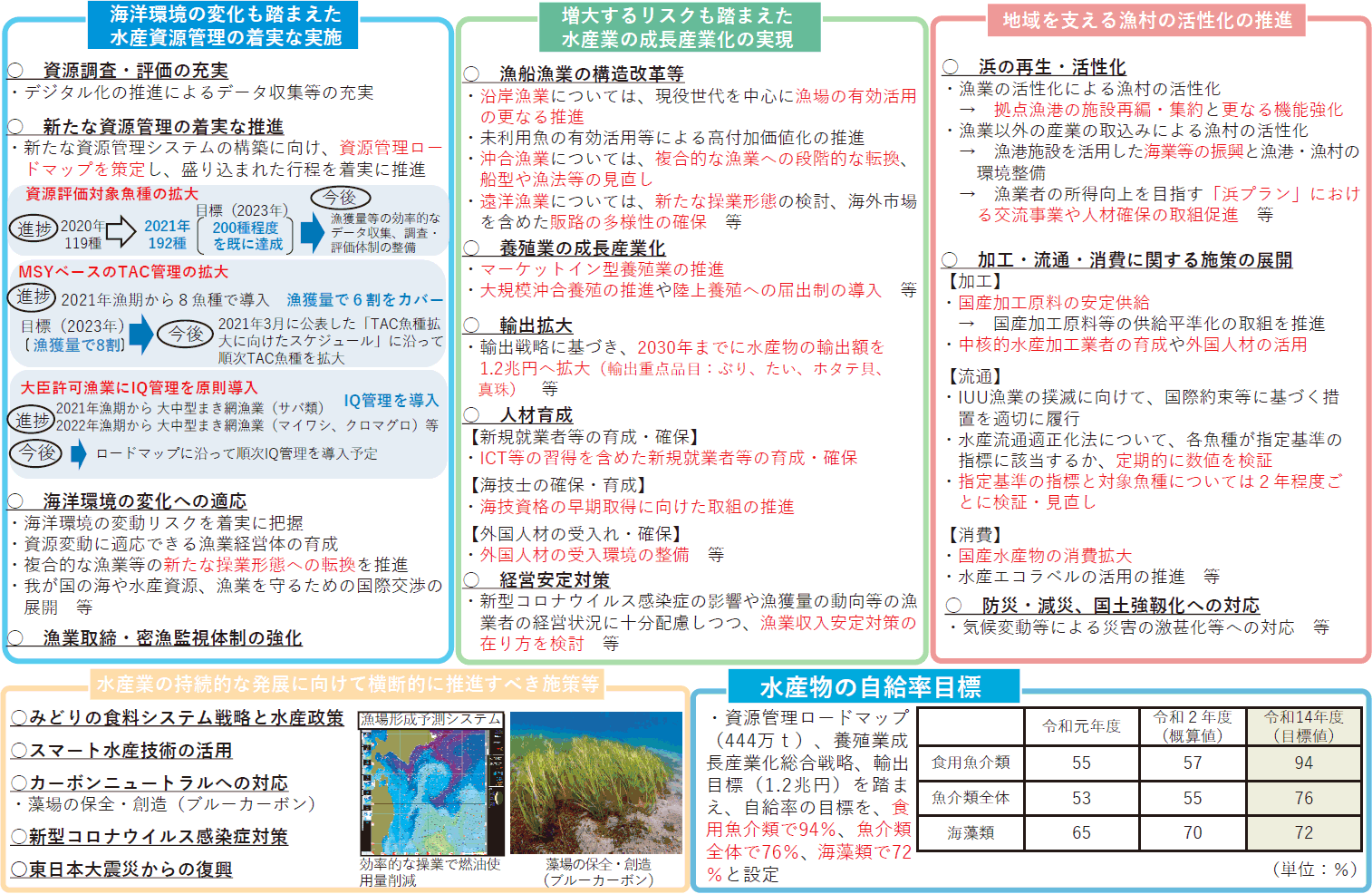
〈新たな水産基本計画における講ずべき施策〉
新たな基本計画では、水産業をめぐる情勢等を踏まえ、講ずべき施策を記述しています。
基本的な方針の一つ目の柱である「海洋環境の変化も踏まえた水産資源管理の着実な実施」では、主に以下の施策に取り組むこととしています。
1)資源調査・評価の充実
ロードマップに基づき、資源評価への理解の醸成を促進しつつ、MSY*1ベースの資源評価及び評価対象種の拡大等、資源評価の高度化を図る。
2)新たな資源管理の着実な推進
ロードマップに盛り込まれたTAC*2魚種の拡大やIQ*3管理の導入、資源管理協定*4への移行等を着実に実施するとともに、遊漁についても漁業と一貫性のある管理を目指す。また、栽培漁業については、資源造成効果の高い対象種、適地での種苗放流を推進する。
3)漁業取締・密漁監視体制の強化
実効ある資源管理のため、取締船の計画的な代船建造等、漁業取締体制の強化を進め、外国漁船等による違法操業に対する取締りや沿岸域での密漁監視体制の強化、周辺国との協議・協力を図る。
4)海洋環境の変化への適応
海洋環境の変化による分布・回遊の変化等の資源変動への順応に向け、複合的な漁業や次世代型漁船への転換、サケのふ化放流やさけ定置漁業の合理化等を推進する。
- Maximum Sustainable Yield:最大持続生産量。現在の環境下において持続的に採捕可能な最大の漁獲量。95ページ参照。
- Total Allowable Catch:漁獲可能量。100ページ参照。
- Individual Quota:漁獲割当て。108ページ参照。
- 資源管理協定については、108ページ参照。
二つ目の柱の「増大するリスクも踏まえた水産業の成長産業化の実現」では、主に以下の施策に取り組むこととしています。
1)沿岸漁業
操業の効率化・生産性の向上を促進し、漁場の有効活用を推進するとともに、浜プランの見直しを図る。遊漁については、漁場利用調整に支障のない範囲で水産関連産業の一つとして位置付ける。また、海面利用制度の適切な運用に取り組む。
2)沖合漁業
資源変動に適応できる漁業経営体の育成と資源の有効利用を図るため、IQの導入や、複合的な漁業への転換、機械化による省人化等を推進する。
3)遠洋漁業
将来にわたって収益や乗組員の安定確保ができ、様々な国際規制等にも対応できる経営体の育成・確立のため、操業モデルの変革や海外市場を含めた販路の多様化の確保等、国際的な資源管理、入漁の確保等を推進する。
4)養殖業の成長産業化
養殖戦略等に基づき、戦略的養殖品目の増産や海外への輸出拡大を目指し、沖合養殖の拡大を含め規模の大小を問わない成長産業化への取組を着実に進める。また、陸上養殖を「内水面漁業の振興に関する法律*1」に基づく届出養殖業に位置付ける。
5)経営安定対策
近年の漁業及び養殖業の経営を取り巻く環境の大きな変化に際し、これらの経営の安定を維持するため、漁業保険制度やセーフティーネット対策等の適切な運営を行う。
6)輸出の拡大と水産業の成長産業化を支える漁港・漁場整備
輸出戦略に基づく輸出拡大や水産業の成長産業化を目指し、新たな輸出先の開拓等に取り組むとともに、漁港の有効活用や加工・流通施設等の一体的な整備を推進する。
7)内水面漁業・養殖業
内水面漁業においては、漁業生産の持続性の確保や良好な漁場環境の保全、内水面養殖業においては、ウナギ資源の管理・適正利用、錦鯉の輸出拡大等を推進する。
8)人材育成
水産資源の適切な管理や水産業の成長産業化を支える人材育成のため、新規就業者の確保・育成、水産教育、海技士等の人材の確保・育成、外国人材の受入れ等を進める。
9)安全対策
漁業者の命を守ることに加え、魅力的な就業環境の実現や人材確保のため、安全推進員・安全責任者の養成やライフジャケットの普及、安全確保に向けた新技術の開発・導入等を促進する。
- 平成26(2014)年法律第103号
三つ目の柱の「地域を支える漁村の活性化の推進」では、水産業の生産性向上や付加価値向上を図るほか、漁業以外の産業の取込みによる漁村地域の活性化を推進することとし、主に以下の施策に取り組むこととしています。
1)浜の再生・活性化
海業の振興や民間活力の導入を促進し、漁業以外も含めた活躍の場の提供等による人材の定着と漁村の活性化についても推進できるよう浜プラン・広域浜プランの見直しを図る。
2)漁協系統組織の経営の健全化・基盤強化
複数漁協間での広域合併や経済事業の連携等の実施、漁協施設の機能再編を進めることにより、漁業者の所得向上及び漁協の経営の健全性確保のための取組等を推進する。
3)加工・流通・消費に関する施策の展開
加工については、環境等の変化に適応可能な産業への転換に向けた取組や国産加工原料の安定供給等を推進する。流通については、水産バリューチェーンの強化や産地市場の統合・重点化、違法に採捕された水産物の流通防止や水産物の食品表示の適正化等といった水産物等の健全な取引環境の整備を推進する。消費については、国産水産物の消費拡大や水産エコラベル*1の活用の推進を図る。
4)水産業・漁村の多面的機能の発揮
水産業・漁村の持つ水産物の供給以外の多面的な機能が将来にわたって発揮されるよう、一層の国民の理解の増進を図りつつ、効率的・効果的に取組を促進する。
5)漁場環境の保全・生態系の維持
海洋生態系を維持しつつ、持続的な漁業を行うため、藻場・干潟等の保全・創造、栄養塩類管理、赤潮対策、野生生物による漁業被害対策、海洋プラスチックごみ対策等を戦略的に推進する。
6)防災・減災、国土強靱(きょうじん)化への対応
災害発生後の水産業の継続や早期の再開を図るため、事前の防災・減災対策、災害からの早期復旧に向けた対応、持続可能なインフラ管理等に取り組む。
- 水産エコラベルについては、47ページ参照。
そのほか、「水産業の持続的な発展に向けて横断的に推進すべき施策」として、主に以下の施策に取り組むこととしています。
1)みどりの食料システム戦略*1と水産政策
今後の技術開発やロードマップ等を踏まえ、関係者の理解を得ながら、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立に向けて着実に実行する。
2)スマート水産技術の活用
ICT を活用して漁業活動や漁場環境の情報を収集し、適切な資源評価・管理を促進するとともに、生産性を向上させるスマート水産技術を活用する。また、漁村や洋上における通信環境等の充実やデジタル人材の確保・育成を推進する。
3)カーボンニュートラルへの対応
漁船の電化・燃料電池化、漁港・漁村のグリーン化を推進する。
4)新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症の影響に応じた販売促進・消費拡大、水産物の輸出の維持・促進等を図る。さらに、人手不足を解消するため、引き続き必要な労働力の確保支援を行う。
また、東日本大震災からの復旧・復興及び原発事故の影響克服について、引き続き取り組むこととしています。
- みどりの食料システム戦略については、126ページ参照。
〈水産物の自給率の目標〉
水産物の自給率は、基本法の基本理念の達成度合いを全体として測る上での有効な指標であるとともに、我が国の漁業生産が国民の水産物消費にどの程度対応しているかを評価する上で端的で分かりやすい指標です。
新たな基本計画では、漁業者その他の関係者の努力によって漁業生産・水産物消費に関する課題を解決することにより見込まれる令和14(2032)年度における生産量及び消費量の目標を設定し、これらを基に自給率の目標を、食用魚介類で94%、魚介類全体で76%、海藻類で72%と設定しました(図表特-1-7)。
図表特-1-7 水産物の自給率、生産量、消費量の目標
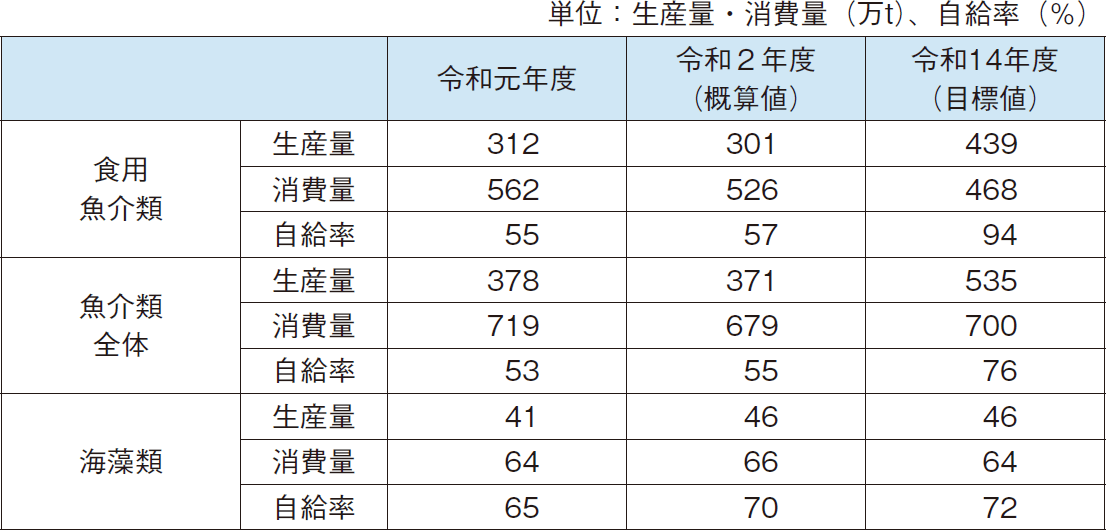
〈水産施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項〉
基本計画には、前述した施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項についても記述しています。
1)関係府省等の連携による施策の効率的な推進、2)施策の進捗管理と評価、3)消費者・国民ニーズを踏まえた公益的な観点からの施策の展開、4)事業者や産地の主体性と創意工夫の発揮の促進、5)財政措置の効率的かつ重点的な運用、に留意しつつ施策を推進していくこととしています。

お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
FAX番号:03-3501-5097




