(3)北西太平洋での我が国漁業におけるロシアとの関係
〈北西太平洋の漁業における我が国とロシアの主な関係〉
我が国は、ロシアと水域を接し、スケトウダラやサンマといった双方の水域にまたがって分布する水産資源を漁獲しており、二国間の協定に基づく相互入漁や公海域における国際的な資源管理等、北西太平洋における漁業の枠組みを構築する上でロシアとの関係は重要です。
我が国とロシアとの二国間では、1)サンマ、スルメイカ、マダラ、サバ等を対象とした相互入漁に関する日ソ地先沖合漁業協定*1、2)ロシア系サケ・マス(ロシアの河川を母川とするサケ・マス)の我が国漁船による漁獲に関する日ソ漁業協力協定*2、3)北方四島の周辺12海里内での日本漁船の操業に関する北方四島周辺水域操業枠組協定*3等の漁業に関する政府間協定が結ばれています。また、これらに加え、民間協定として、北方四島のうち歯舞群島(はぼまいぐんとう)の一部である貝殻島(かいがらじま)の周辺12海里内において我が国の漁業者が安全にコンブ採取を行うための貝殻島昆布協定*4が結ばれています。
また、北太平洋の公海域では、北太平洋漁業委員会(NPFC)において、サンマやサバ、底魚類等の資源管理を実施しており、同委員会に我が国とロシアも参加しています。
ロシア・ウクライナ情勢下での交渉においても、水産物の供給の確保と北西太平洋での我が国漁業の継続に資するよう、各協定に基づく交渉の実施・進展に努めてきました。
以下、各交渉の状況について記述しています。
- 正式名称:日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の両国の地先沖合における漁業の分野の相互の関係に関する協定
- 正式名称:漁業の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定
- 正式名称:日本国政府とロシア連邦政府との間の海洋生物資源についての操業の分野における協力の若干の事項に関する協定
- 正式名称:日本漁民による昆布採取に関する北海道水産会とソヴィエト社会主義共和国連邦漁業省との間の協定
〈日ソ地先沖合漁業協定〉
我が国と旧ソ連双方の200海里水域における相互入漁のため、昭和59(1984)年に両政府間で、日ソ地先沖合漁業協定が締結され、ソ連が崩壊した平成3(1991)年12月以降も我が国とロシアとの間で引き続き有効となっています(図表特-1-13)。この協定に基づいて、毎年、日ロ漁業委員会を開催し、日ロ双方の200海里水域における相互入漁の操業条件等を協議しています。
令和5(2023)年の操業条件等については、令和4(2022)年12月にウェブで開催された日ロ漁業委員会第39回会議において妥結し、ロシア200海里水域における我が国漁船の相互入漁のための漁獲割当量は50,000t(サンマ、スルメイカ、マダラ等)、有償入漁のための漁獲割当量は約695tとなり、我が国200海里水域におけるロシア漁船の相互入漁のための漁獲割当量は50,000t(サバ、マイワシ、イトヒキダラ)となりました。
図表特-1-13 日ソ地先沖合漁業協定操業水域概念図
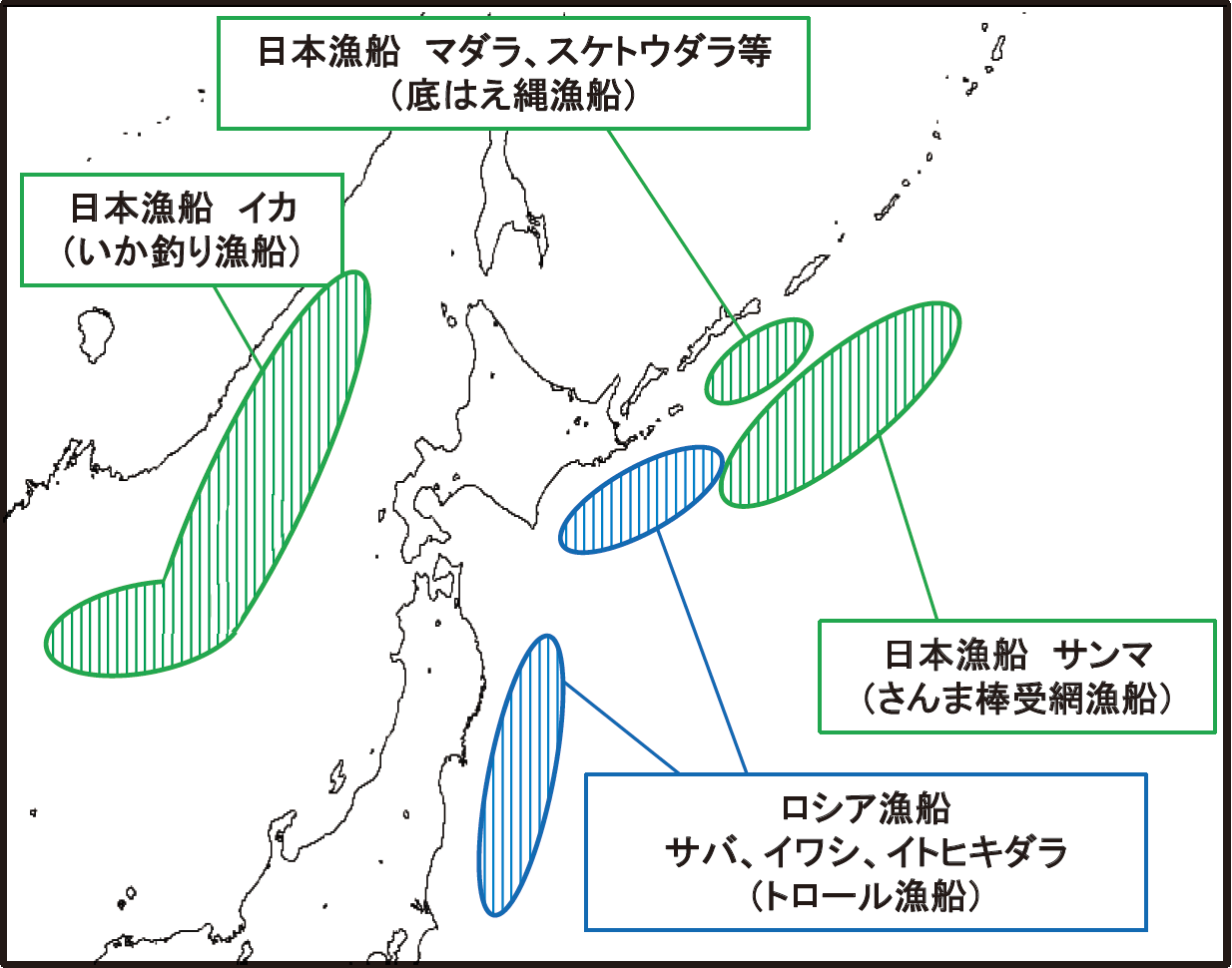
〈日ソ漁業協力協定〉
サケ・マスのような溯河性(さくかせい)魚類について、母川の所在する国がその資源に関する一義的な利益と責任を有する、いわゆる「母川国主義」の考えが盛り込まれた国連海洋法条約*1が昭和57(1982)年に採択されたこと等を踏まえて、昭和60(1985)年に日ソ漁業協力協定が締結され、平成3(1991)年12月以降も我が国とロシアとの間で引き続き有効となっています(図表特-1-14)。本協定に基づき、毎年、日ロ漁業合同委員会を開催し、我が国200海里水域における我が国漁船によるロシア系サケ・マスの操業条件等を協議するとともに、本協定及び日ソ地先沖合漁業協定に基づき、日ロ政府間協議を開催し、ロシア200海里水域における我が国漁船の操業条件を協議しています。
令和5(2023)年の我が国200海里水域における我が国漁船によるロシア系サケ・マスの操業条件については、同年3月にウェブで開催された日ロ漁業合同委員会第39回会議において妥結し、漁獲量は、カラフトマス等1,550t、サケ(シロサケ)500tで、漁業協力費は、2億円~約3億13万円の範囲で漁獲実績に応じて決定することとなりました。なお、ロシア200海里水域における曳(ひ)き網によるサケ・マスの試験的な操業については、令和5(2023)年の対応は、令和5(2023)年3月末時点で検討中となっています。
- 正式名称:海洋法に関する国際連合条約
図表特-1-14 日ソ漁業協力協定操業水域概念図
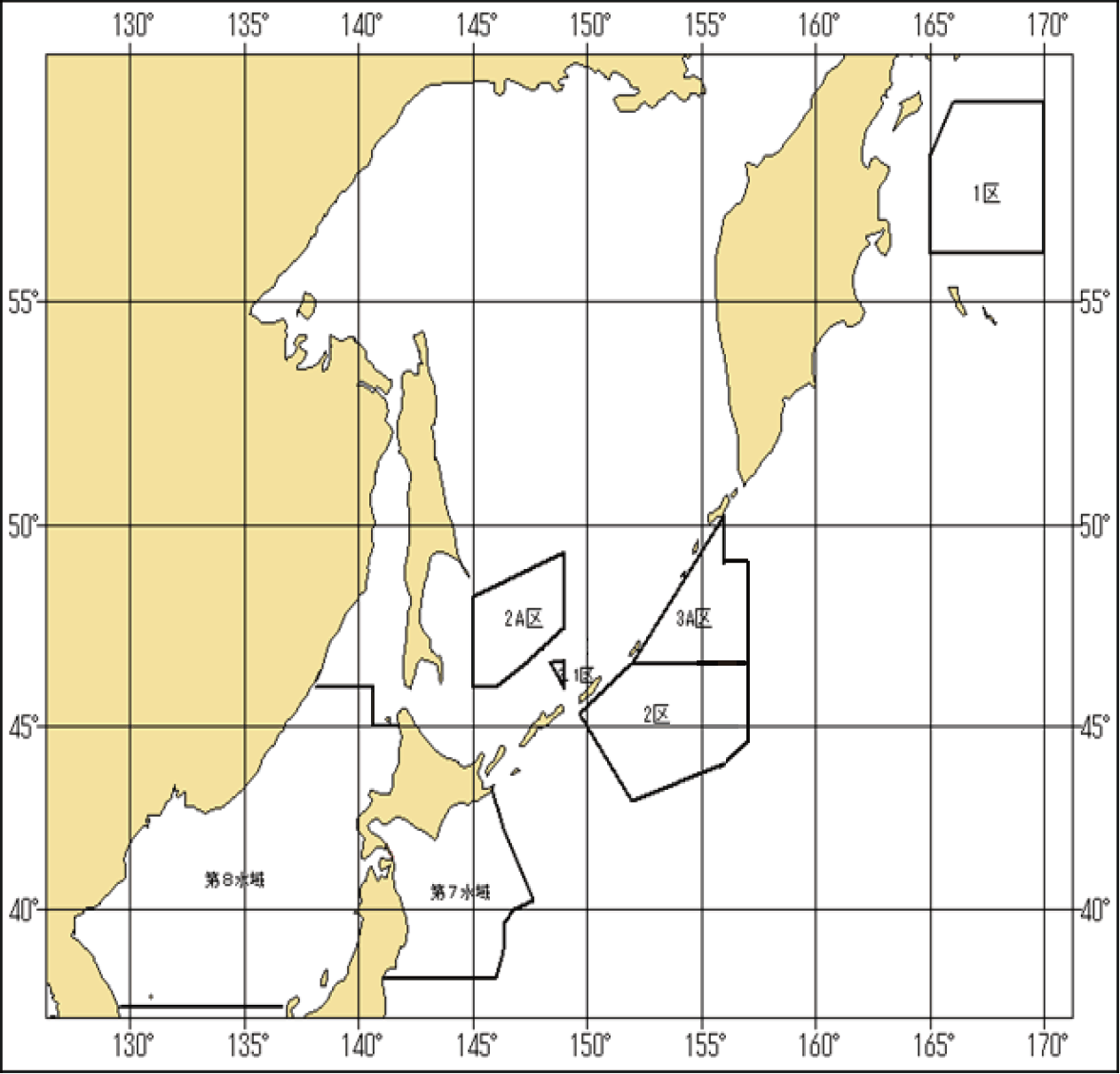
〈北方四島周辺水域操業枠組協定〉
北方四島周辺12海里水域における我が国漁業者の安全操業を確保し、海洋生物資源の保存、合理的利用及び再生産のための協力を目的として、平成10(1998)年に日ロ両政府間で、北方四島周辺水域操業枠組協定が締結されました(図表特-1-15)。この協定に基づいて、政府間協議及び民間交渉を行っています。この協定に基づく令和5(2023)年分操業の交渉については、令和5(2023)年3月末時点でロシア側が応じていない状況が続いています。
図表特-1-15 北方四島周辺水域操業枠組協定操業水域概念図
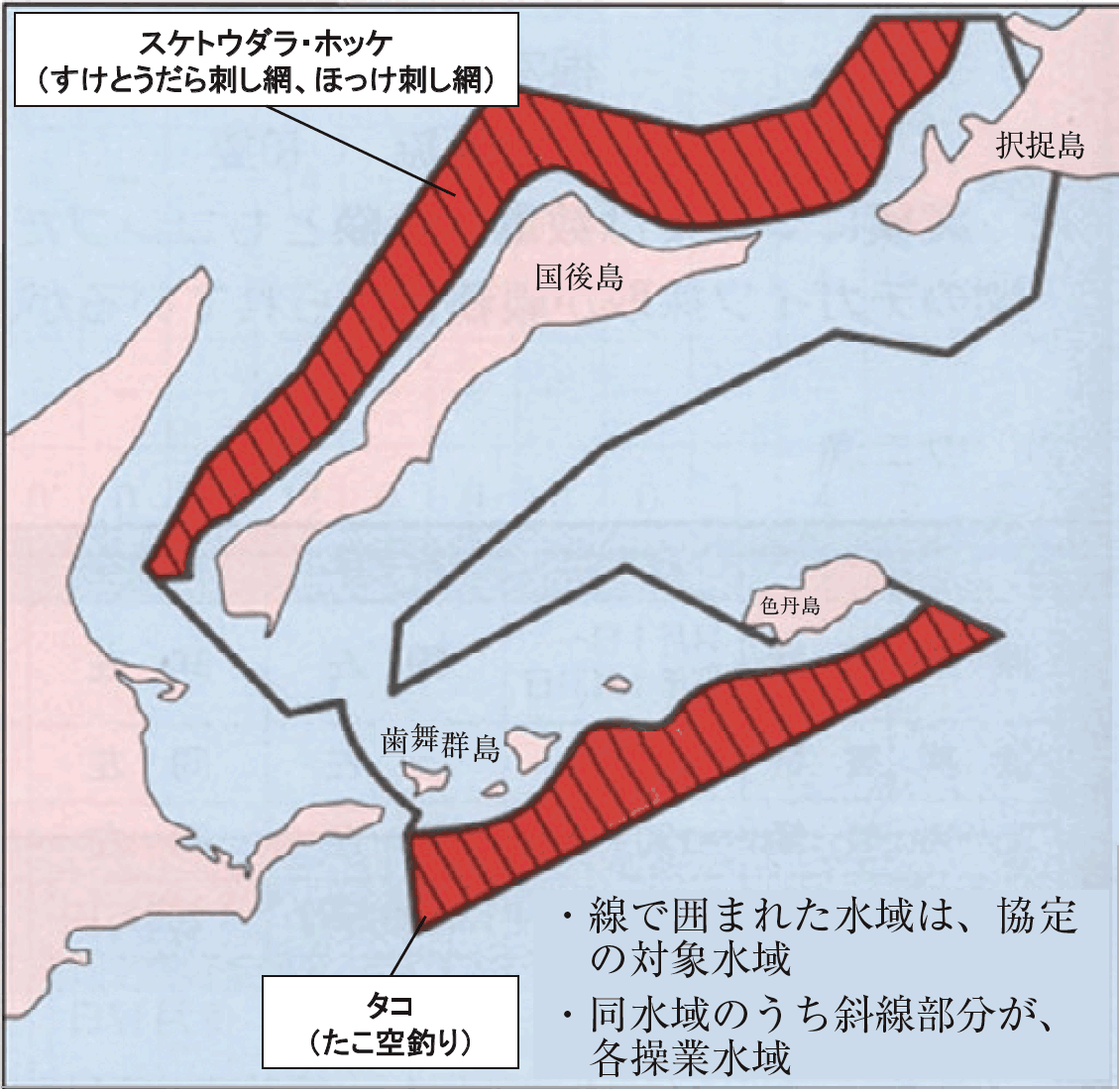
〈貝殻島昆布協定〉
歯舞群島の一部である貝殻島周辺で我が国漁業者が安全にコンブ採取を行うため、昭和56(1981)年に社団法人北海道水産会(ほっかいどうすいさんかい)(現在の一般社団法人北海道水産会)とソ連漁業省(現在のロシア漁業庁)との間で貝殻島昆布協定(民間協定)が締結され(図表特-1-16)、同協定に基づき、一般社団法人北海道水産会とロシア漁業庁は、毎年、我が国漁業者の操業条件等を協議しています。
令和4(2022)年の操業条件等については、同年5月から6月にかけてウェブにより民間交渉が行われ、採取量は褐藻類3,787t(うちコンブ3,381t)、採取権料は約8,851万円、機材供与は350万円となりました。
図表特-1-16 貝殻島昆布協定水域概念図
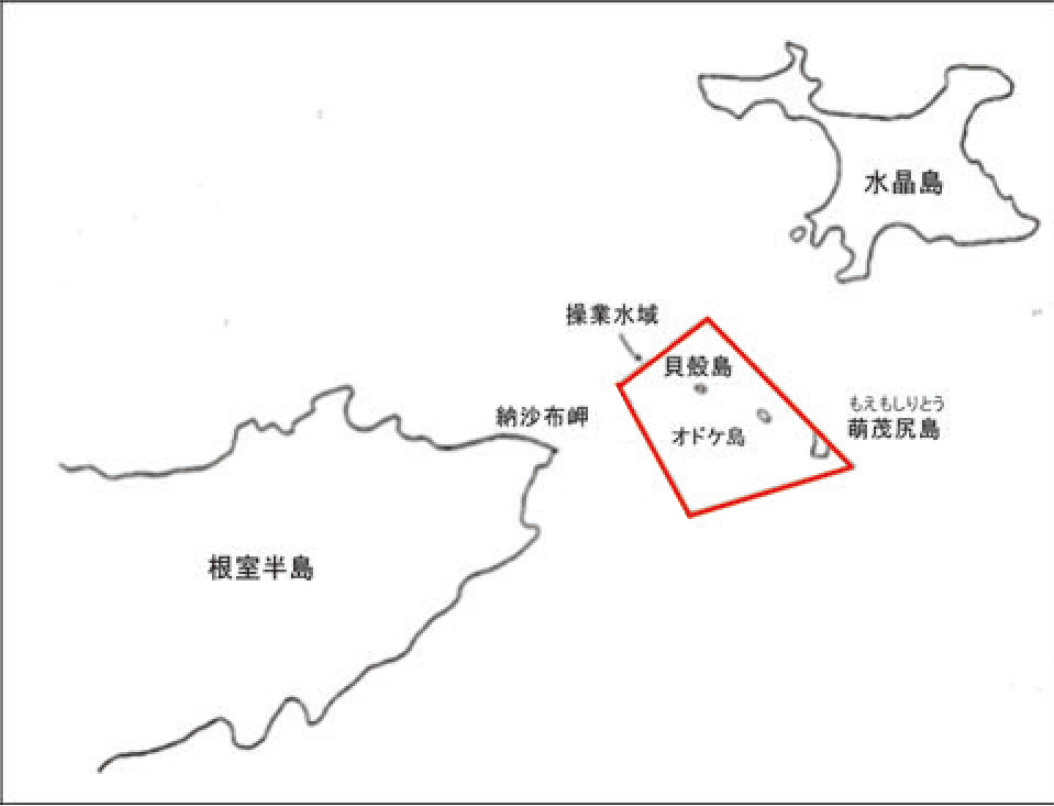
〈北太平洋漁業委員会(NPFC)〉
NPFCは、北太平洋公海における海洋生態系を保護しつつ、漁業資源の長期的な保存及び持続可能な利用を確保することを目的とした北太平洋漁業資源保存条約*1に基づき設立された地域漁業管理機関です。参加する国・地域は、我が国のほか、カナダ、ロシア、中国、韓国、米国、バヌアツ、台湾及びEUです。対象水域は、おおむね北緯20度以北の北太平洋の公海です(図表特-1-17)。また、対象資源は、サンマ、サバ、アカイカ、底魚類等であり、マグロ類、サケ・マス等、他の条約の対象資源は対象外となっています。我が国の漁船は本条約の適用水域において、サンマ、イカ、底魚類等を対象とした漁業を行っています。
令和3(2021)年の年次会合は、令和3(2021)年及び令和4(2022)年におけるサンマの公海での漁獲可能量(TAC:Total Allowable Catch)等が合意されました。
一方、令和4(2022)年3月28~30日に開催が予定されていた同年の年次会合は、ロシア・ウクライナ情勢等を背景に多数の国の意向により、延期となりましたが、令和3(2021)年に合意されたサンマの保存管理措置が2年間有効であったこと等から、令和4(2022)年においても大きな混乱なく同措置が適用されました。
令和5(2023)年3月22~24日に年次会合が再開され、令和5(2023)及び6(2024)年におけるサンマの公海でのTACや、小型魚保護のための措置、漁獲努力量削減のための措置等が合意されました。
- 正式名称:北太平洋における公海の漁業資源の保存及び管理に関する条約
図表特-1-17 NPFC対象水域図
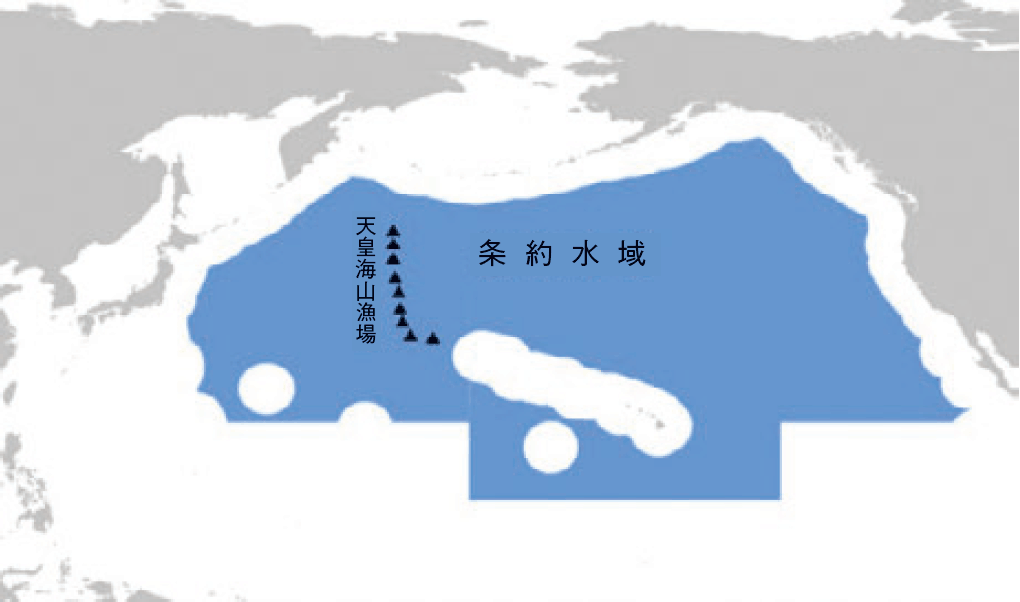
〈第1節のおわりに〉
我が国とロシアは、水域を接し、共通の水産資源を利用していることから、資源を適切に管理し、持続的に利用するため、上記のような多岐にわたる協議・協力の関係を築いてきました。例えば二国間交渉の枠組みでは、それぞれの200海里水域において相手国漁船の入漁を相互に認め合うなど、困難な交渉や調整を経ながらも、互いの漁業者による資源の利用や資源管理のための協力を図ってきたところです。また、多国間協議の枠組みによる国際的な資源管理においても、例えば両国はNPFCのメンバー国として、国際協調の下でサンマ、サバ等の資源管理に取り組んでおり、共に沿岸国としての立場を有し、自国水域を含めた資源の適切な保存管理を図る観点では協力する関係にあります。このほか、タラコ、イクラ、サケ、カニといった、日本食には不可欠の食材がロシアから供給されているという面もあります。
このように、水産に関して我が国とロシアは重層的・複層的な関係にあると言えますが、このような関係は、今後も資源の適切な管理を着実に進め、我が国が資源を持続的に利用できるようにする観点から、適切な形で維持されていく必要があります。ロシア・ウクライナ情勢は重層的・複層的な両国関係や国民生活に様々な影響を及ぼしていますが、このような中でも、日ロ間の水産に関する特殊な関係性を踏まえながら、水産資源の適切な管理や我が国の漁業活動に係る権益の維持・確保の観点等も踏まえ、戦略的に対応していく必要があります。
また、今般のロシア・ウクライナ情勢による我が国とロシアの関係の変化は、我が国の水産物の安定供給に大きな影響を及ぼしており、ロシアをはじめとする諸外国との関わりが食料安全保障上大きな要因となることを改めて浮き彫りにしました。対ロシア関係はあくまで一例であり、水産物の安定供給の確保の観点から、今後とも、他の関係国を含め、国際情勢の動向を注視しつつ関連施策に取り組んでいく必要があります。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344




