(3)海業推進のための施策等
〈水産基本計画及び漁港漁場整備長期計画において海業の振興を位置付け〉
水産庁では、水産基本計画及び漁港漁場整備長期計画において、「海業の振興」を位置付け、漁港を海業等に利活用しやすい環境を整備することを明記し、地域の理解と協力の下、海や漁村に関する地域資源を活かした海業の取組を促進しています(図表特-2-2、図表特-2-3)。
また、水産基本計画では、浜ごとの漁業所得向上を目標としてきた「浜の活力再生プラン」(以下「浜プラン」といいます。)において、海業等の漁業外所得確保の取組の促進や、地域の将来を支える人材の定着と漁村の活性化についても推進していけるよう見直しを図ること、漁港漁場整備長期計画では、海業等の多様な取組による活性化を目指す浜プランの実践を推進することが位置付けられています。
さらに、漁港漁場整備長期計画では、令和8(2026)年度を目途に、漁港における新たな海業等の取組をおおむね500件展開するとした成果目標を設定しています。
図表特-2-2 水産基本計画における「海業」に関する主な記載

図表特-2-3 漁港漁場整備長期計画における「海業」に関する主な記載

〈海業の推進に必要な調査、活動、施設整備等を支援〉
農林水産省においては、海業の推進に当たり、地域人材の育成や漁港機能の有効活用に関する調査等の海業の展開に必要な調査等、地域資源を魅力ある観光コンテンツとして磨き上げる取組等の海業に係る活動支援及び漁港施設・用地の再編・整序や地域水産物普及施設の整備等の漁港の利活用環境整備・海業支援施設の整備といった支援事業を実施しています。
また、海業の推進や漁港の活用促進を着実に実施するため、水産庁の組織を見直し、海業推進に向けた体制を強化することとしています。
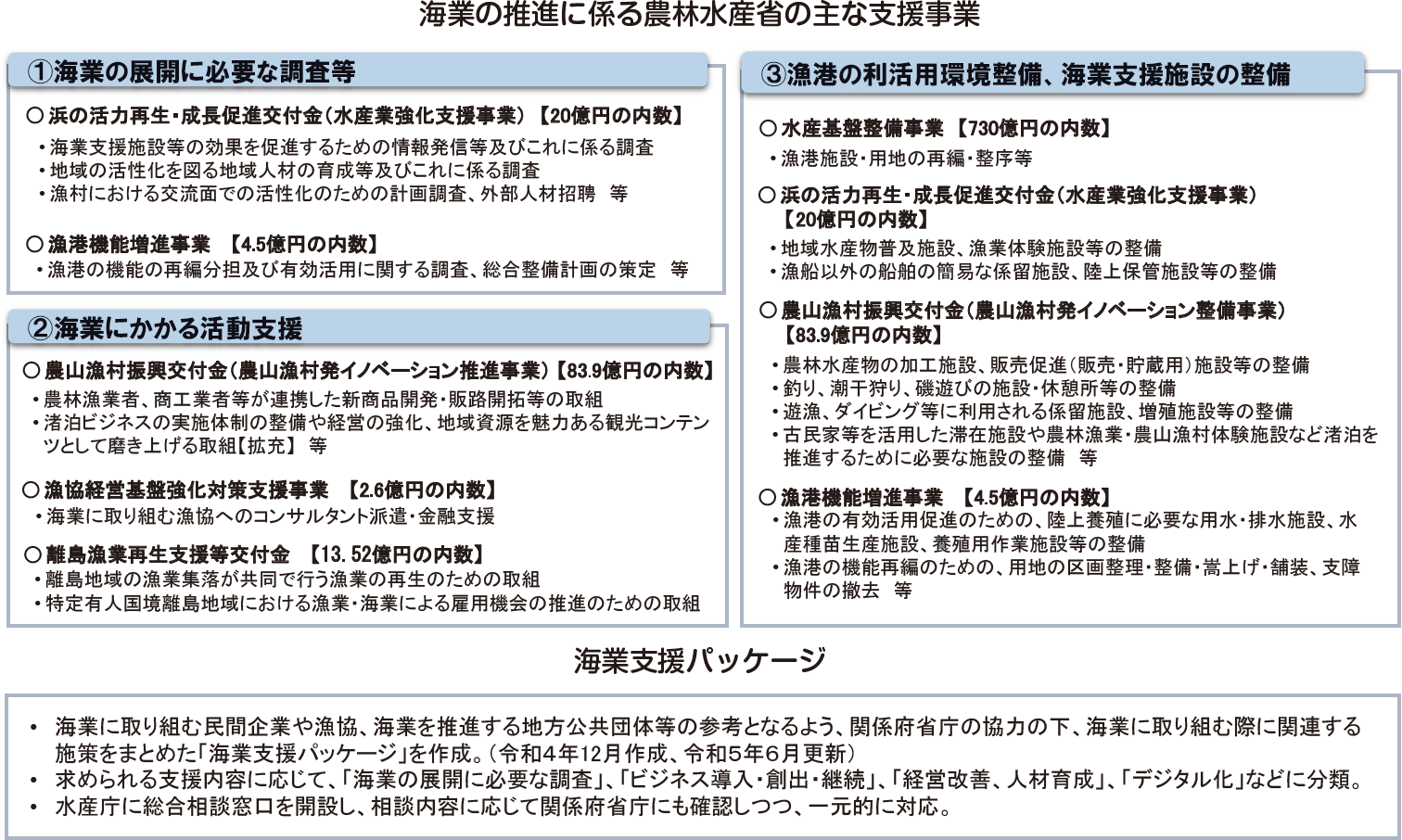
〈海業支援パッケージの作成、海業振興総合相談窓口の設置〉
海業に係る支援は多岐の分野に渡ることから、水産庁では、海業の取組をより一層推進するため、関係府省庁の協力の下、これから海業に取り組む民間企業や個人、海業を推進する地方公共団体等の参考となるよう、海業に取り組む際に関連する施策をまとめた「海業支援パッケージ」を令和4(2022)年12月に作成しました。本資料は、海業自体を目的として実施するものだけではなく、漁村がある沿岸市町村で、海や漁村の地域資源を活用した取組を支援する施策や、そのような取組を推進する市町村等が活用可能な施策を幅広く掲載しており、関連する施策やその担当部署等を速やかに調べられるようにすることを目指しています。
また、海業支援パッケージの一環として、関係府省庁の協力の下、海業振興に取り組む方々に向けて海業振興に係る相談を総合的に受け付ける「海業振興総合相談窓口(海業振興コンシェルジュ)」を開設しました。

〈漁港における海業の取組事例集等を作成・公表〉
水産庁では、海業に関する各地の取組がより一層進められるよう、これまでに行われている取組事例を集めた事例集等を作成し、公表しています。
令和3(2021)年8月には、漁港を活用した地域水産業の活性化及び漁村の賑わい創出に向け、漁港施設の有効活用に関する制度、留意すべきプロセス、全国の取組事例等を取りまとめた「漁港施設の有効活用ガイドブック」及び「有効活用事例集」を作成しました。
また、令和5(2023)年8月には、これまで行われている海業に関する各地の取組のうち一定の効果が発揮されている取組や、更に効果の発現が期待される取組について取りまとめた「海業の取組事例集」を作成しました。
渚泊については、令和3(2021)年7月に公表した「渚泊推進対策取組参考書」や「渚泊取組事例集」の作成により取組を推進しています。
くわえて、漁港機能の再編・集約等により生じた空いた漁港の水域や用地等が増養殖に活用されている事例も多く、この一層の利用促進を図るため、水産庁では、令和2(2020)年9月に「漁港水域等を活用した増養殖の手引き」を作成し、公表しました。
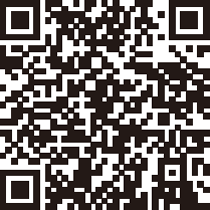

〈海業振興モデル地区の選定〉
水産庁では、5年間でおおむね500件の漁港における新たな海業等の取組実施に向け、海業振興の先行事例を創出し広く普及を図っていくため、海業振興のモデル形成に取り組む意欲のある地区を募集しました。この応募があった地区の中から海業振興モデル地区公募要領の選定基準等に基づき審査を行った結果、令和5(2023)年3月に12件の海業振興モデル地区を選定しました。
本モデル地区において、調査支援や関係者協議支援、計画策定支援等を行うことにより、当該地区と協力して海業の事業化を目指すこととしています。本支援により得られた成果や情報については、今後、海業振興に取り組む自治体等の参考となるよう、普及のための資料や講演、ホームページ等において幅広く提供していく予定です。
〈漁港等における適切な釣り利用に向けたガイドラインを策定〉
釣り等の親水性レクリエーションを通じた漁村への交流人口の増加を図るに当たり、漁業と調和のとれた水面等の利用の促進が必要です。特に、漁港における釣りにおいては、一部の釣り人の垂らした釣り糸が航行する漁船に巻き付き航行の障害になり、漁業活動への支障になっているほか、立ち入り禁止区域への侵入による危険行為等のトラブルが発生しています。また、水産資源管理の観点からは、遊漁により採捕されている魚は漁業にとっても重要な資源であり、漁業と一貫性のある資源管理が求められます。
このような状況において、水産庁では、令和5(2023)年6月に、漁港における釣り利用について、利用ルール、マナー確保対策、釣り人の安全確保対策、漁港の釣り利用による所得・雇用の創出方策等の考え方を示すため、「漁港における釣り利用・調整ガイドライン」を作成しました。

お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344









