第2節 海業による漁村活性化の取組
前節で見たように、我が国の漁業・養殖業の生産量、食用魚介類の消費量、漁業就業者数等が減少傾向にある中、漁村における高齢化の進行等により、漁村の活力が低下している現状があります。一方、漁村は新鮮な水産物や豊かな自然環境等の多くの地域資源を有しており、これらの価値や魅力を活かした海業の推進により、漁村の賑わいを生み出し、地域の所得向上と雇用機会の確保を図ることが重要です。本節では、海業の先行的な取組や海業推進のための施策等を紹介していきます。
(1)地域経済の活性化を目指す海業とその取組の現状
〈海や漁村に関する地域資源を活かした「海業」〉
漁業をはじめとする水産業が基幹産業である漁村においては、これまで水産物の生産、加工、流通、販売等の直接的な水産業の活動が主眼でしたが、漁村には、四季折々の新鮮な水産物、豊かな自然環境、親水性レクリエーションの機会等の様々な地域資源があることから、それらを十分に把握し最大限に活用することが漁村の経済的な活性化を図る上で重要となっています。
また、国民が、漁港を訪れて水産物を食し、漁業に触れ合うことで水産業との関わりを持ち、海に親しむ取組を進めることは、水産業に対する国民の理解醸成にも繋(つな)がり、我が国の水産業の持続的な発展に寄与するものです。
このような考え方の下、水産基本計画及び漁港漁場整備長期計画において、「海業」という言葉が盛り込まれました。この言葉は、昭和60(1985)年に神奈川県三浦(みうら)市により提唱されたもので、「海の資質、海の資源を最大限に利用していく」ことをコンセプトに、漁業や漁港を核として地域経済の活性化を目指すものです。
両計画において、海業は「海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用する事業」と定義されています。漁村の人口減少や高齢化等、地域の活力が低下する中で、漁業利用との調和を図りつつ地域資源を最大限に活用し、水産業と相互に補完し合う産業である海業を育成し、根付かせることによって、地域の所得と雇用の機会の確保を目指しています。
特に漁港は、地域を支える基幹的なインフラとして様々な事業活動を受け入れる能力を有し、静穏な水域が確保され海洋資源にアクセスしやすく、漁業そのものが持つ魅力を直接国民が享受することができる利点を有することから、海業の展開に適しており、漁港の用地、水域等を活用した多くの事業が実施されています。
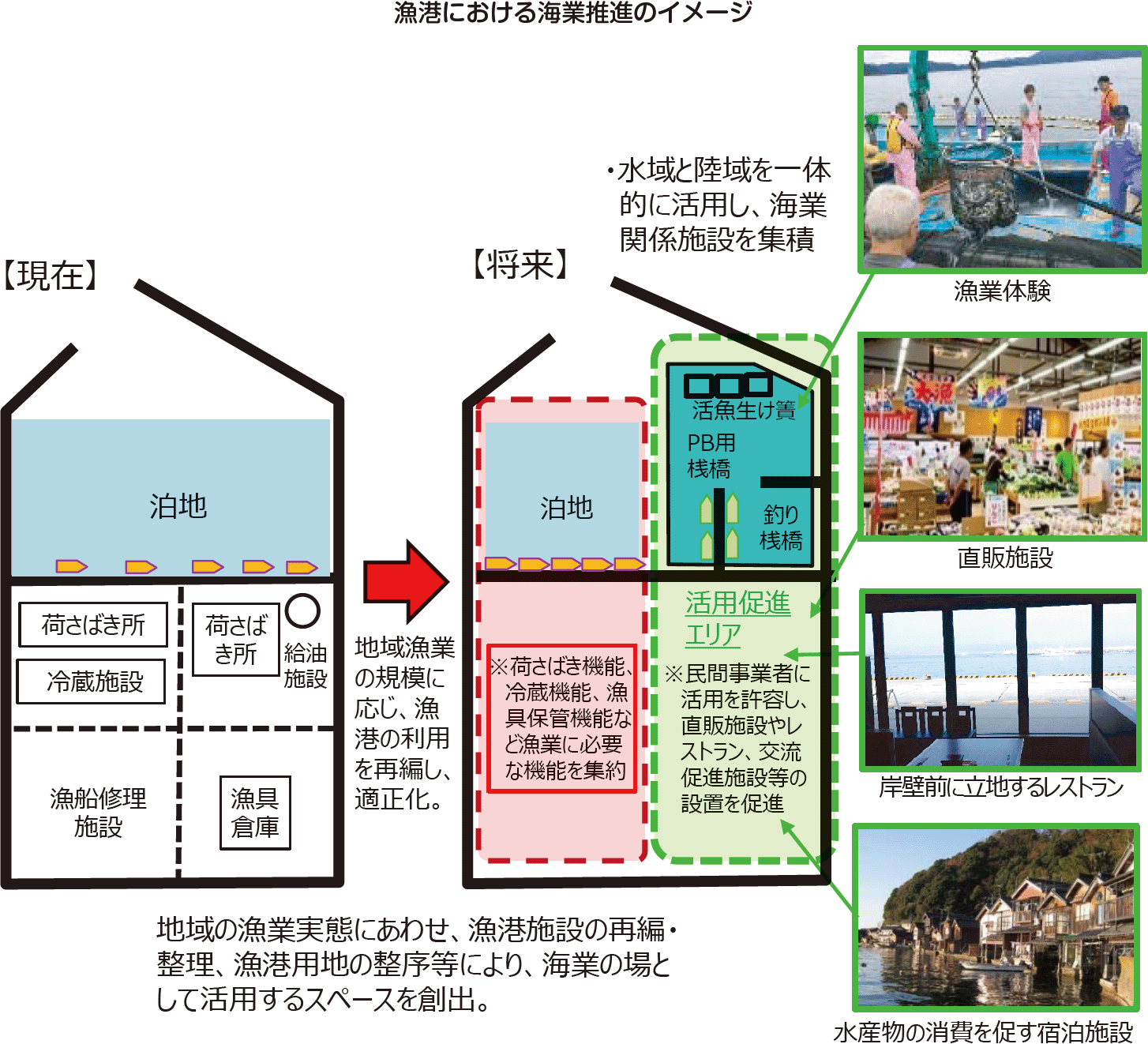
〈漁港用地を活用した陸上養殖の数は増加傾向〉
漁港は、流通関連施設の集積や取水・排水等の事業環境が整っていること、防波堤等により静穏域が確保されていることなどから、漁港施設の再編・整理、漁港用地の整序等により、漁港の用地を活用した陸上養殖や水域を活用した増養殖・蓄養の取組を行いやすい環境にあります。漁港の用地を活用した陸上養殖の取組は増加傾向にあり、令和2(2020)年3月時点で136漁港において陸上養殖の取組が行われています(図表特-2-1)。
図表特-2-1 漁港の用地を活用した陸上養殖の取組
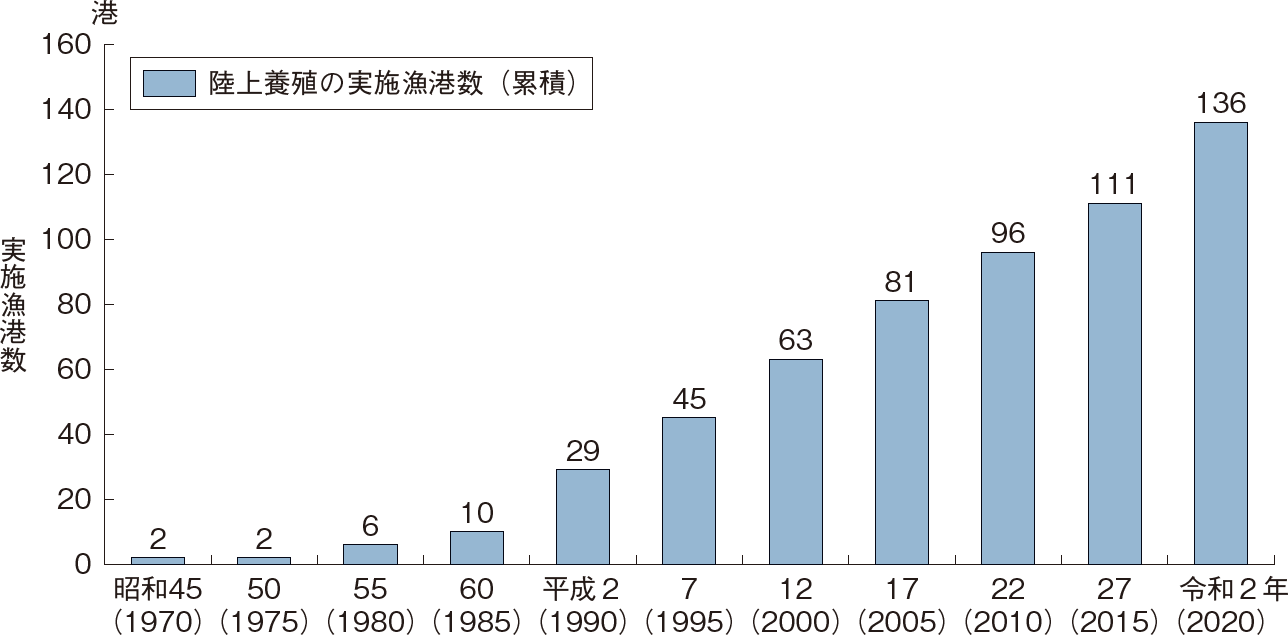
〈多様化する消費者のニーズに向けて期待される漁港の役割〉
近年、消費者のニーズは、モノを購入する「モノ消費」から、体験やサービスを消費する「コト消費」や感動を他の参加者と共有する「トキ消費」へと移行していると言われています。漁港は、漁場に近く、水揚げの根拠地であり、鮮度の高い水産物をはじめ、漁業体験、独自の風景や歴史など、水産物の「モノ消費」だけでなく、「コト消費」や「トキ消費」のための大きなポテンシャルも有しており、これらの多様なニーズから多くの方が漁港を訪れています。水産物消費の減少等の課題に対して、漁港において、海や漁村の価値や魅力を活かす海業の取組により、都市など他の地域との交流を促進しつつ、多様化する消費者のニーズに対応することにより、水産業の持続的な発展に寄与していくことが求められます。
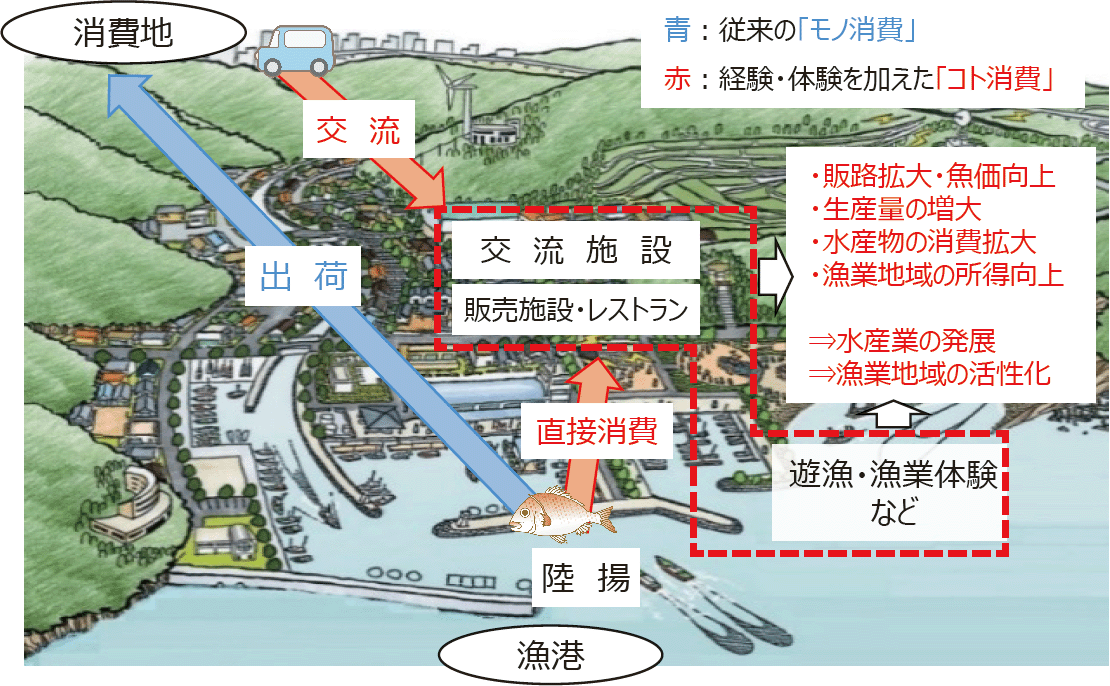
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344




