(3)漁村が果たす役割
ア 漁村における水産業の役割
〈水産業は漁村における基幹産業〉
漁村は、漁業就業者などの住民の生活の場としてのみならず、漁業をはじめとする水産業の拠点として重要な役割を果たしています。漁村の中でも、漁港においては、漁業の操業に必要な物資の供給、漁獲物の陸揚げ、水産物の流通、販売、加工等消費者に新鮮で安全な水産物を安定的に供給する役割のほか、漁船係留や避難基地としての役割も果たしています(図表特-1-5)。
また、これまでみてきたように、漁村の多くは漁業には適地である一方、交通等においては条件不利地に立地していることから、雇用機会が限られる中、漁業は漁村の基幹産業として重要であり、特に集落の規模が小さいほど漁家世帯の割合が高いことがわかります(図表特-1-6)。
さらに、漁村に住む人々からなるコミュニティは、基幹産業である漁業を通じ、地域における水産資源や漁場の利用・管理・保全、水産業関連施設等の共同管理等の役割を果たしています。
図表特-1-5 漁港の役割
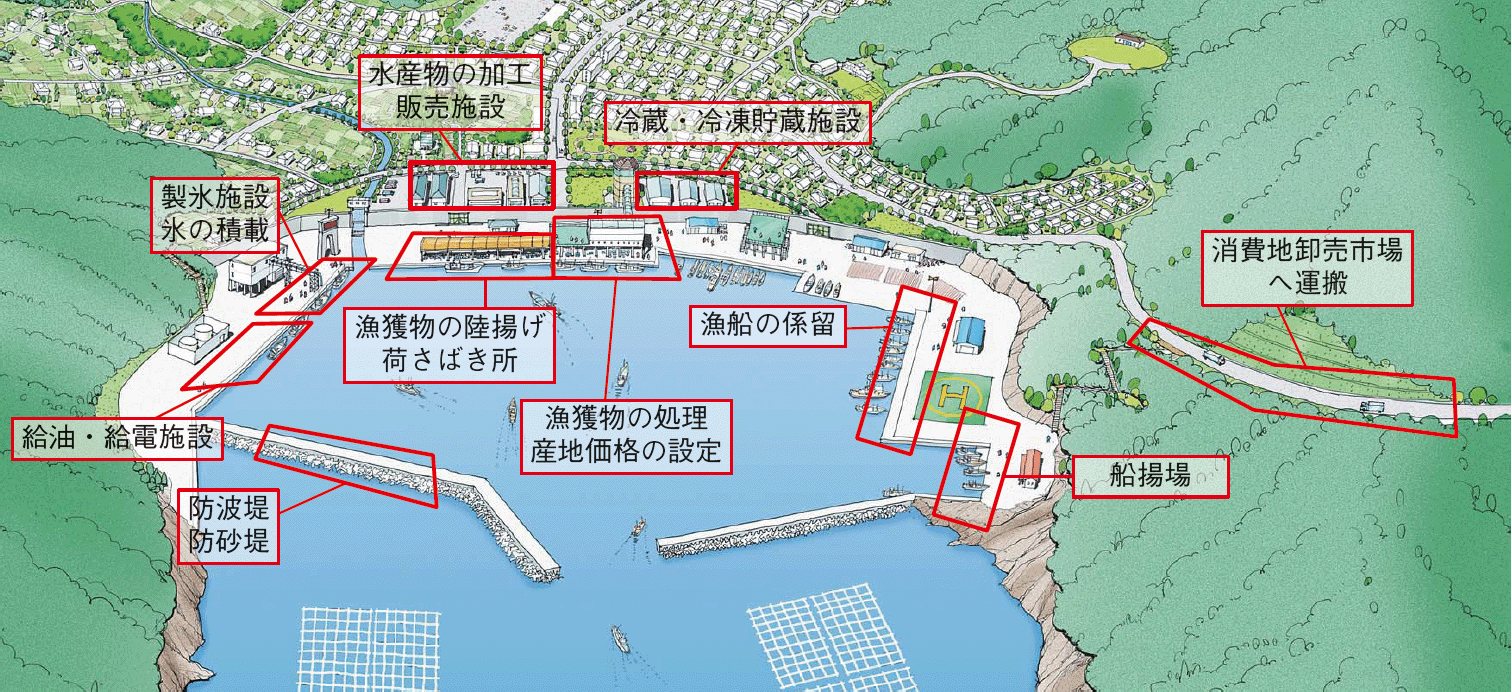
図表特-1-6 漁港背後集落の規模別の漁家世帯の割合
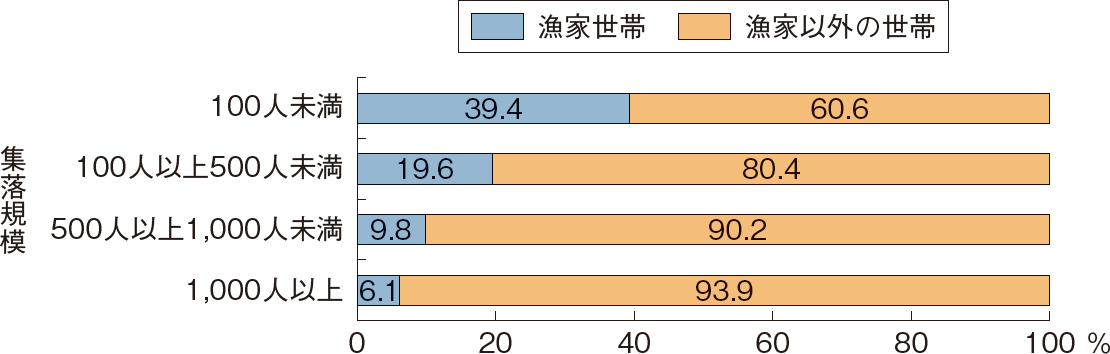
イ 漁村が有する多面的機能
〈水産業・漁村は広く国民一般にも及ぶ多面的機能を有する〉
水産業・漁村は、国民に水産物を供給する役割だけでなく、1)自然環境を保全する機能、2)国民の生命・財産を保全する機能、3)交流等の場を提供する機能、4)地域社会を形成し、維持する機能、等の多面的な機能も果たしており、その恩恵は、漁業者や漁村の住民にとどまらず、広く国民一般にも及びます(図表特-1-7)。とりわけ、漁村は四季折々の新鮮な水産物、豊かな自然環境、親水性レクリエーションの機会等を有しており、都市と地方の交流の場を提供しています。
図表特-1-7 水産業・漁村の多面的機能
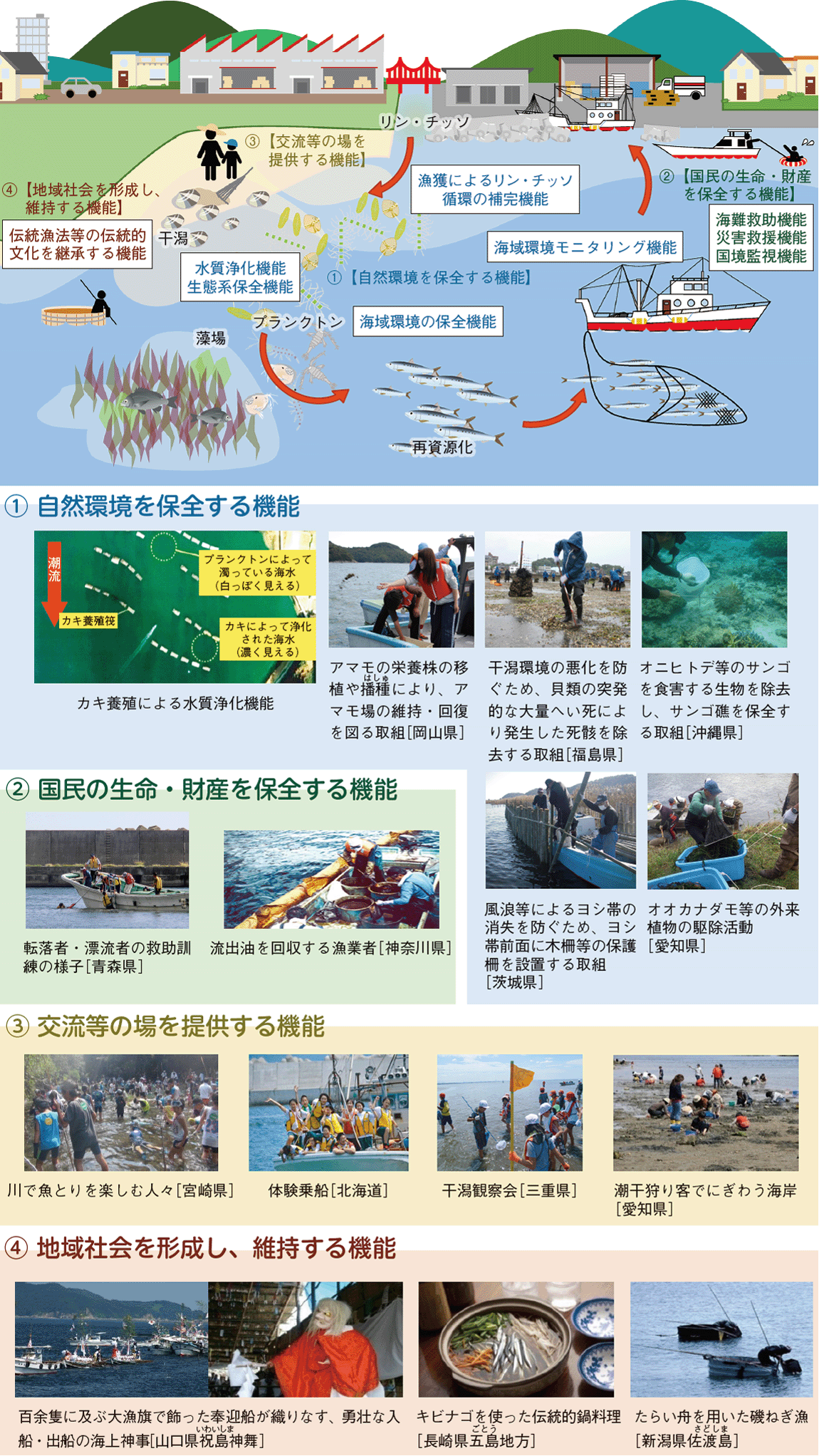
このような水産業・漁村の多面的機能は、人々が漁村に住み、水産業が健全に営まれることによって発揮されるものですが、漁村の人口減少や高齢化が進めば、漁村の活力が低下し、多面的機能の発揮にも支障が生じます。このため、水産基本法*1において、国は、水産業及び漁村の多面的機能の発揮について必要な施策を講ずるよう規定されているとともに、令和2(2020)年12月に施行された漁業法等の一部を改正する等の法律*2による改正後の漁業法*3(以下「改正漁業法」といいます。)において、国及び都道府県は、漁業・漁村が多面的機能を有していることに鑑み、漁業者等の漁業に関する活動が健全に行われ、漁村が活性化するよう十分配慮するものとすることが規定されています。また、水産基本計画においても、水産業・漁村の持つ多面的機能が将来にわたって適切に発揮されるよう、一層の国民の理解の増進を図りつつ効率的・効果的に取組を促進するとともに、海業に関わる人等の漁業者や漁村住民以外の多様な主体の参画を推進すること、また、国境監視の機能については、漁村と漁業者による海の監視ネットワークが形成されていることから、漁業者と国や地方公共団体の関係部局との協力体制の下で監視活動の取組を推進すること等が明記されています。これらを踏まえて、水産庁は、漁村を取り巻く状況に応じて多面的機能が適切かつ効率的・効果的に発揮されるよう、漁業者をはじめとした関係者に創意工夫を促しつつ、藻場や干潟の保全、内水面生態系の維持・保全・改善、国境・水域監視や海難救助訓練等の漁業者等が行う多面的機能の発揮に資する取組が引き続き活発に行われるよう、国民の理解の増進を図りながら支援していくこととしています。
- 平成13年法律第89号
- 平成30年法律第95号
- 昭和24年法律第267号
コラム内水面における多面的機能の発揮に資する取組
森は海の恋人と言いますが、その森と海をつなぐのが川です。森が育んだ栄養塩類が川を通じて海に注ぎ込むことで、豊かな海の恵みがもたらされるのです。また、アユやサケなど多くの魚種が海と川を行き来して生活しています。
川や湖沼においても内水面漁業が営まれ、漁業協同組合(以下「漁協」といいます。)を中心とした環境保全などの活動により、地域の活性化にも寄与しています。
兵庫県矢田川(やだがわ)漁協では、地元の高校、行政、学識経験者等と連携し、地域一体となって魚やカニ等が遡上・流下しやすい河川環境を整備することを目的として、「清流の郷づくり大作戦」に取り組んでいます。具体的には、魚道機能の維持に努めるとともに、魚道設置の効果を確認するため、高校の生徒と一緒にアユの流下・遡上調査や水生生物の観察会を行っています。
また、矢田川流域に古くから伝わる「アユのなれずし」や「モクズガニ飯」といった川の恵みを使った料理、「アユのドブ釣り」や「投網」など地元に根付いた漁法は、地域の重要な伝統文化であり、地域住民を対象にした体験会などを通じて、これらの伝承に努めるとともに、水産多面的機能発揮対策事業を活用した河川清掃活動や地元小学生を対象にした環境学習会を実施し、河川の役割や環境問題、生物多様性の重要性等を学ぶ機会を提供しています。
このような取組により、矢田川の豊かな自然環境や伝統文化などの魅力が維持されることで、アユの釣れる川として多くの釣り人が訪れ、また、川遊びなどを目的とした観光客で地域に賑わいが生まれるなど、漁協による活動が地域の活性化に大きく貢献しています。
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344






