第1節 漁村をめぐる現状と役割
本節では、我が国の漁業生産、水産物の消費、漁業就業者等、水産業をめぐる状況と、このような状況における漁村の現状を記述するとともに、地域を支える漁村の役割、漁村が有する地域資源等を記述しています。
(1)漁業生産、水産物消費等水産業をめぐる状況
〈漁業・養殖業の生産量は減少傾向〉
我が国の漁業・養殖業の生産量は、漁業就業者数の減少等に伴う生産体制の脆弱(ぜいじゃく)化に加え、海洋環境の変化や水産資源の減少等により緩やかな減少傾向が続いており、とりわけ、サンマ、スルメイカ、サケの不漁が深刻化しています。令和4(2022)年の我が国の漁業・養殖業生産量は、前年から24万t減少し392万tとなっています。
〈我が国の食用魚介類の消費量は減少傾向〉
世界では、近年、1人1年当たりの食用魚介類の消費量*1が増加傾向にある中、我が国の消費量は減少傾向にあります。我が国の1人1年当たりの食用魚介類の消費量(純食料ベース)は、平成13(2001)年度の40.2kgをピークに減少傾向にあり、令和4(2022)年度には、22.0kg(概算値)となっています。
〈漁業就業者数・漁業経営体数は減少傾向〉
我が国の漁業・養殖業の生産量及び水産物の消費量が減少傾向で推移する中、我が国の漁業就業者数は一貫して減少傾向にあります。令和4(2022)年は12万3,100人となっており、平成20(2008)年から令和4(2022)年までの間に約10万人減少しました。また、漁業就業者全体に占める65歳以上の割合は約4割となっており漁業者の高齢化に伴い増加傾向となっています。
海面漁業・養殖業の経営体数は、令和4(2022)年は6万1千経営体となっており、平成5(1993)年から令和4(2022)年までの間に約11万経営体減少しました。また、漁業経営体の後継者*2不足も課題となっており、個人経営体のうち、後継者がいる割合は、全体の2割以下となっています。
〈個人経営体(漁船漁業)の漁労収入は横ばい〉
海面漁業・養殖業の経営体数が減少する中、基幹的漁業従事者*3が65歳未満の個人経営体(漁船漁業)の漁労収入は、横ばいで推移しています。
- 農林水産省では、「食料需給表」において、国内生産量、輸出入量、在庫の増減量、人口等から「食用魚介類の1人1年当たり供給純食料」を算出している。この数字は、「食用魚介類の1人1年当たり消費量」とほぼ同等と考えられるため、ここでは「供給純食料」に代えて「消費量」を用いる。
- 満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者のうち、将来、自家漁家の経営主になる予定の者。
- 個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で自家漁業の海上作業従事日数が最も多い者。
図表特-1-1 漁業・養殖業生産量、漁業就業者数等の変化
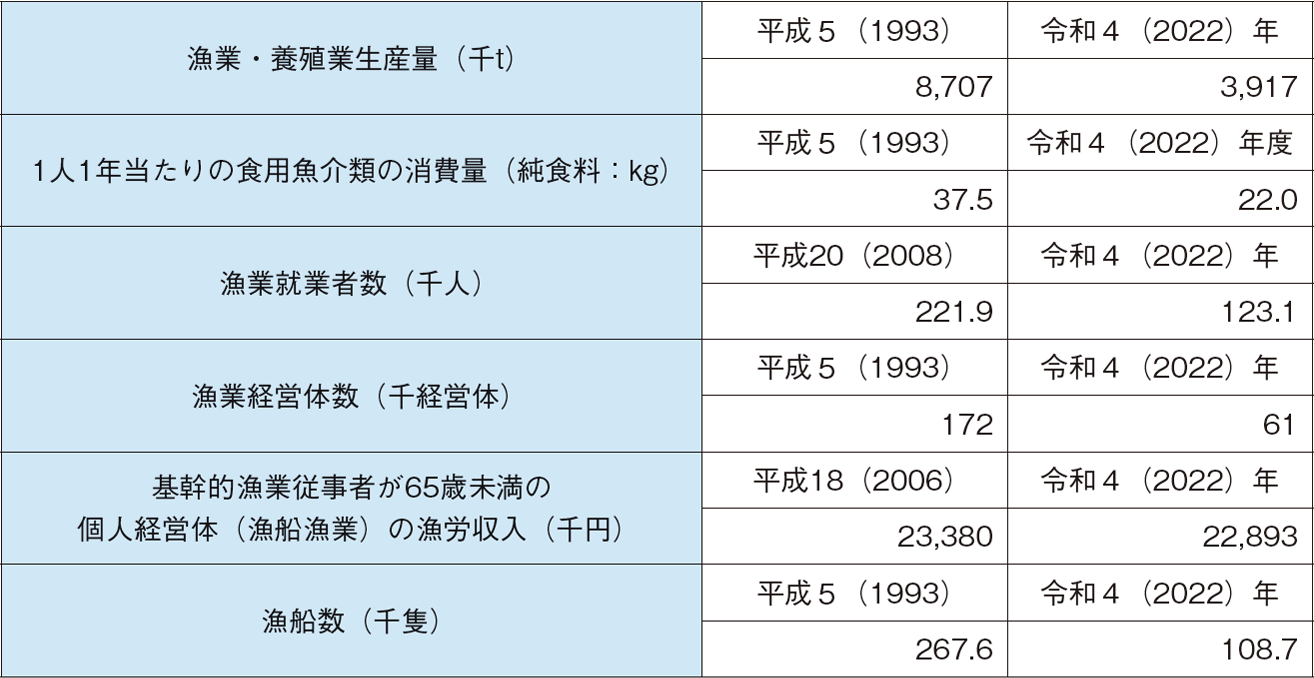
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344




