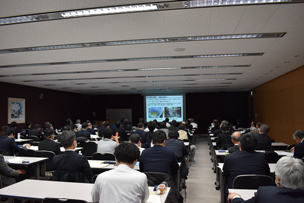(4)資源を積極的に増やすための取組
ア 種苗放流の取組
(全国で約70種を対象とした水産動物の種苗放流を実施)
多くの水産動物は、産卵やふ化の後に捕食されるなどして、成魚まで育つものはごくわずかです。このため、一定の大きさになるまで人工的に育成し、ある程度成長してから放流することによって資源を積極的に増やしていく種苗放流の取組が各地で行われています。
現在、都道府県の栽培漁業センター等を中心として、ヒラメ、マダイ、ウニ類、アワビ類等、全国で約70種を対象とした水産動物の種苗放流が実施されています(表1-2)。
なお、国では、放流された種苗を全て漁獲するのではなく、親魚となったものの一部を獲り残して次世代の再生産を確保する「資源造成型栽培漁業」の取組を引き続き推進しています。また、種苗放流等は資源管理の一環として実施することとし、1)従来実施してきた事業は、資源評価を行い、事業の資源造成効果を検証し、検証の結果、資源造成の目的を達成したものや効果の認められないものは実施しない、2)資源造成効果の高い手法や対象魚種は、今後も事業を実施するが、その際、都道府県と適切に役割を分担し、ヒラメやトラフグのように都道府県の区域を越えて移動する広域回遊魚種等は、複数の都道府県が共同で種苗放流等を実施する取組を促進することなどにより、効果のあるものを見極めた上で重点化することとしています。
また、「秋サケ」として親しまれている我が国のサケ(シロサケ)は、親魚を捕獲し、人工的に採卵、受精、ふ化させて稚魚を河川に放流するふ化放流の取組により資源が造成されていますが、近年、放流した稚魚の回帰率の低下により、資源が減少しています。気候変動による海洋環境の変化が、海に降(くだ)った後の稚魚の生残に影響しているとの指摘もあり、国では、環境の変化に対応した放流手法の改善の取組等を支援しています。
表1-2 種苗放流の主な対象種と放流実績

コラム第39回全国豊かな海づくり大会
全国豊かな海づくり大会は、水産資源の保護・管理と海や湖沼・河川の環境保全の大切さを広く国民に訴えるとともに、つくり育てる漁業の推進を通じて、明日の我が国漁業の振興と発展を図ることを目的として、昭和56(1981)年に大分県において第1回大会が開催されて以降、毎年開催されています。
令和元(2019)年9月に秋田県で開催された「天皇陛下御即位記念第39 回全国豊かな海づくり大会・あきた大会」は、天皇陛下御即位記念の慶祝行事として、「海づくり つながる未来豊かな地域」を大会テーマに開催されました。
式典行事では、豊かな海を願い、天皇皇后両陛下によるハタハタ、サクラマス、エゾアワビ、ワカメの稚魚等のお手渡しが行われ、お手渡しを受けた稚魚等は、後日、秋田県内の各地で放流等が行われました。
次回の第40回大会は、令和2(2020)年9月に、「よみがえる 豊かな海を 輝く未来へ」を大会テーマに宮城県石巻(いしのまき)市で開催される予定です。
イ 沖合域における生産力の向上
(水産資源の保護・増殖のため、保護育成礁やマウンド礁の整備を実施)
沖合域は、アジ、サバ等の多獲性浮魚類、スケトウダラ、マダラ等の底魚類、ズワイガニ等のカニ類など、我が国の漁業にとって重要な水産資源が生息する海域です。これらの資源については、種苗放流によって資源量の増大を図ることが困難であるため、資源管理と併せて生息環境を改善することにより資源を積極的に増大させる取組が重要です。
これまで、各地で人工魚礁等が設置され、水産生物に産卵場、生息場、餌場等を提供し、再生産力の向上に寄与しています。また、国では、沖合域における水産資源の増大を目的として、ズワイガニ等の生息海域にブロック等を設置することにより産卵や育成を保護し増殖を図るための保護育成礁や、上層と底層の海水が混ざり合う鉛直混合*1を発生させることで海域の生産力を高めるマウンド礁の整備を実施しており、水産資源の保護・増殖に大きな効果が見られています(図1-11)。
- 上層と底層の海水が互いに混ざり合うこと。鉛直混合の発生により底層にたまった栄養塩類が上層に供給され、植物プランクトンの繁殖が促進されて海域の生産力が向上する。
図1-11 国のフロンティア漁場整備事業の概要

ウ 内水面における資源の増殖と漁業管理
(資源の維持増大や漁場環境の保全のため、種苗放流や産卵場の整備を実施)
河川・湖沼等の内水面では、「漁業法」に基づき、魚類の採捕を目的とする漁業権の免許を受けた漁協には資源を増殖する義務が課される一方、その経費の一部を賄うために遊漁者から遊漁料を徴収することが認められています。これは、一般に海面と比べて生産力が低いことに加え、遊漁者等、漁業者以外の利用者も多く、採捕が資源に与える影響が大きいためです。こうした制度の下、内水面漁協が主体となってアユやウナギ等の種苗放流や産卵場の整備を実施し、資源の維持増大や漁場環境の保全に大きな役割を果たしています。
このような内水面における増殖活動の重要性を踏まえ、平成30(2018)年12月に成立した「漁業法等の一部を改正する等の法律」による「水産業協同組合法*1」の改正によって、内水面の漁協における個人の正組合員資格について、従来の「漁業者」、「漁業従事者」、「水産動植物を採捕する者」及び「養殖する者」に加え、「水産動植物を増殖する者」を新たに追加するとともに、河川と湖沼の組合員資格を統一しました。
- 昭和23(1948)年法律第242号
コラム内水面漁業の活性化に向けて ~やるぞ内水面漁業活性化事業~
内水面は、アユ等の和食文化と密接に関わる水産物を供給するだけではなく、釣りなどの自然と親しむ機会を提供しており、豊かな国民生活の形成に大きく寄与しています。
しかし、内水面漁場を管理している内水面漁協の多くは、組合員が高齢化・減少しているほか、オオクチバス等の外来生物やカワウによるアユ等の水産資源の捕食による収益悪化等により効果的な漁場管理が困難になってきており、漁場を有効かつ効率的に活用していけるよう、早急に内水面漁協の体質強化を図っていく必要があります。
そのため、水産庁では、令和元(2019)年度から「やるぞ内水面漁業活性化事業」を新たに立ち上げ、全国の内水面漁協等のモデルとなるような漁場管理や内水面漁業活性化等のための先進的な取組を支援しています。
初年度である令和元(2019)年度は、全国で12団体が本事業に採択され、放流に頼らない漁場維持、複数漁協が連携した漁場管理、インターネットを活用することによる遊漁券販売・監視の効率化などの様々な取組が各地で行われています。
この取組の内容や成果が、令和2(2020)年2月18日に東京国際フォーラムで開催された成果報告会で発表され、全国から多くの内水面漁協関係者が参加しました。今後、内水面漁業の活性化に向けて積極的に取り組んでいただくことが期待されます。
表:令和元(2019)年度やるぞ内水面漁業活性化事業における先進的内水面漁場管理推進事業実施者と取組内容
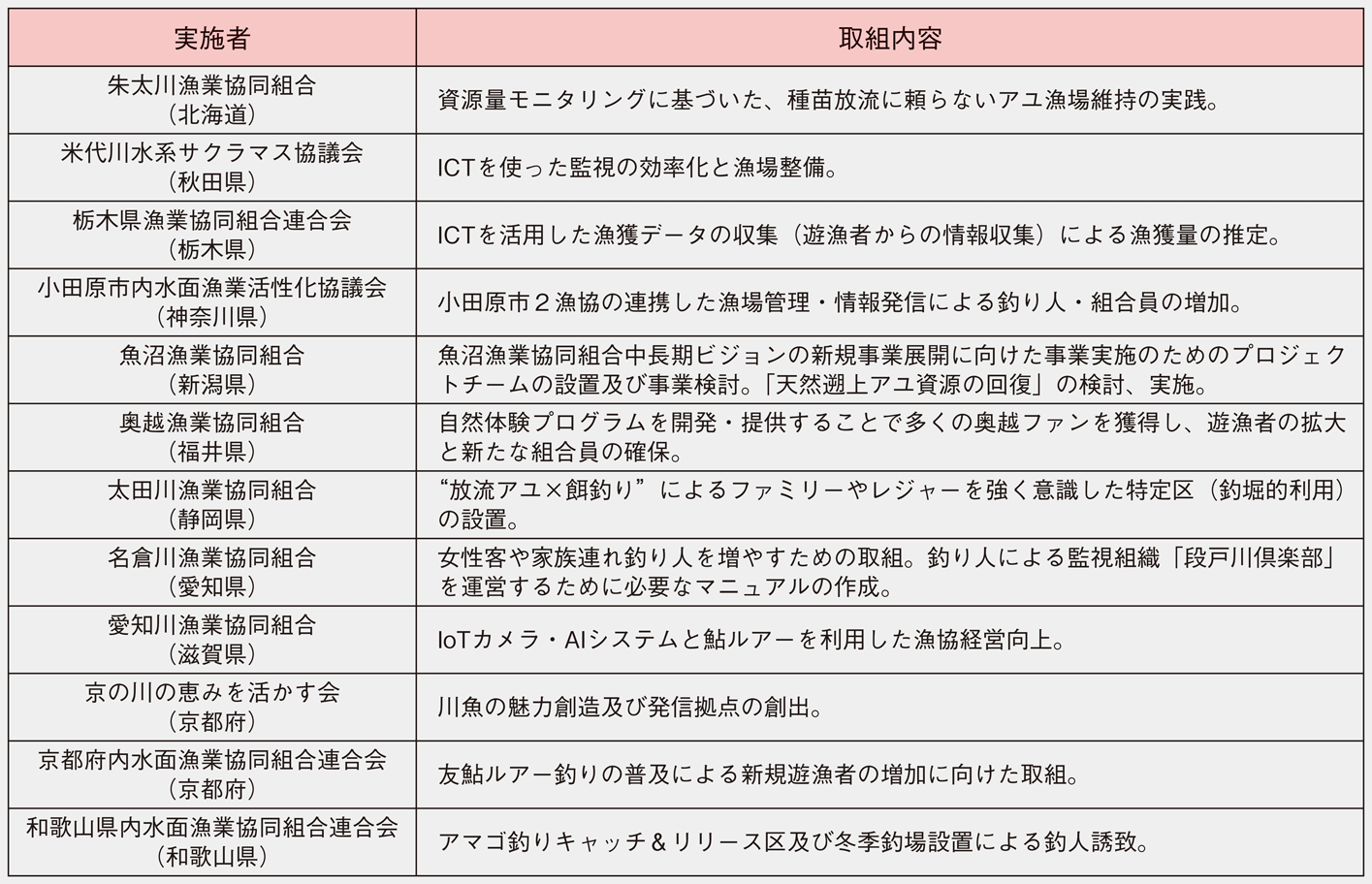
お問合せ先
水産庁漁政部企画課
担当者:動向分析班
代表:03-3502-8111(内線6578)
ダイヤルイン:03-6744-2344
FAX番号:03-3501-5097